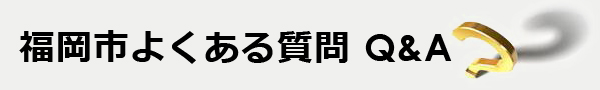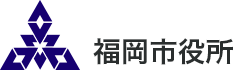質問
市街化調整区域で住宅宿泊事業(民泊)を営むことができるのか。(都市計画法第34条、第43条)
回答
市街化調整区域内では、開発許可制度によって、原則として住宅の建築や用途の変更などが厳しく制限されており、例外的に許可を受けて建築された住宅のなかには、特定の人のみが住むことができる住宅が多くあります。これらの住宅のことを「属人性」のある住宅とも言います。
【属人性のある住宅の例】
●農林漁業従事者のための住宅(農家住宅など)
●世帯構成員等の住宅(分家住宅など)
●収用移転により建築された住宅(代替建築物)
●既存権利届により建築された住宅
これらの属人性のある住宅において、許可を受けた特定の権利がある方が住んでいない状態で、住宅宿泊事業を営むと、法律に違反することになります。具体的に住宅宿泊事業を行うことができるかどうかは、次のようになります。
(1) 属人性がない場合は?→できます。(許可不要)
(2) 属人性があり「家主居住型」の場合は?→できます。(許可不要)
(3) 属人性があり「家主不在型」の場合は?→できません。
<<註>>
※1 「家主居住型」:住宅宿泊事業法第11条第1項第2号。届出住宅に人を宿泊させている間、住宅宿泊事業者が居住していて、不在となるときがない場合は「家主居住型」になります。この場合、日常生活を営む上で通常行われる行為に要する時間の範囲内の不在は不在とはなりません。詳細は、住宅宿泊事業法の本文などにより確認してください。
※2 「家主不在型」:上記の「家主居住型」に該当しない届出住宅はすべて「家主不在型」となります。空家などが該当します。
【お問合せ先】
部署:住宅都市局建築指導部開発・建築調整課
住所:福岡市中央区天神一丁目8番1号(市庁舎4階)
電話番号(1):092-711-4587(東区、博多区、城南区及び早良区の担当:開発指導第1係)
電話番号(2):092-711-4588(中央区、南区及び西区の担当:開発指導第2係)
FAX番号:092-733-5584
電子メール:kaihatsu-kenchiku.HUPB@city.fukuoka.lg.jp
WEB:開発許可申請等の手引き【開発指導ホームページ】(索引附き)
受付時間:月曜~金曜(休庁日除く)午前9時15分~午前12時