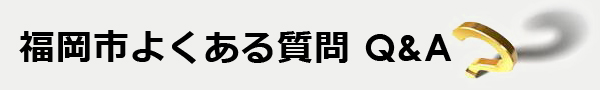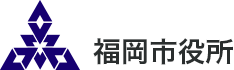質問
区域指定型制度とは何か。(都市計画法第34条第11号及び第12号)
回答
市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域であり、都市計画法に基づき建築物の建築が制限されています。
しかしながら、区域指定型制度では、人口減少などの課題を抱える既存集落において、定住化を目的として地域のみなさんの合意がなされた区域について市が指定を行ないます。
指定された区域内では、誰でも住宅や小規模な店舗などを建てることができ、また、借りて住むことができるようになる制度です。
区域の指定を検討される場合は、下記の【お問い合わせ先】】(地域計画課と開発・建築調整課の両方)に相談ください。
● 区域が指定されればできること
〇 指定区域内であれば、空地(一定規模以上)であっても住宅などを建てることができます。
〇 指定区域内であれば、大きすぎる敷地を分割して、それぞれを宅地として利用することができます。
〇 指定区域内であれば、空家を賃貸住宅や貸店舗として第三者に貸すこともできます。
※ ただし、農地法に基づく農地転用許可など、他法令による許可が下りない場合には、この制度を利用することができませんので、ご注意ください。
住みたい土地が既に指定された区域に入っているかどうかを知りたい方は、次のリンク先をご覧ください。
〇 「都市計画法第34条第11号及び第12号の指定区域及び指定建築物」
※ 既に指定された区域で建築するには、別途、開発許可又は建築許可の手続きを行う必要があります。
この制度については次のリンク先も参考になります。
〇 「市街化調整区域で“住”むこと」 ←※担当課:地域計画課が作成するわかりやすいリーフレットです。
〇 「区域指定型制度運用の手引き」 ←※手続きを進められる方はご覧ください。
【お問合せ先(制度の手続きに関するご相談)】
部署:住宅都市局地域まちづくり推進部地域計画課
住所:福岡市中央区天神一丁目8番1号(市庁舎4階)
電話番号:092-711-4430
FAX番号:092-733-5590
電子メール:chiikikeikaku.HUPB@city.fukuoka.lg.jp
WEB:「市街化調整区域で“住”むこと」
【お問合せ先(開発の許可申請に関するご相談)】
部署:住宅都市局建築指導部開発・建築調整課
住所:福岡市中央区天神一丁目8番1号(市庁舎4階)
電話番号(1):092-711-4587(東区、博多区、城南区及び早良区の担当:開発指導第1係)
電話番号(2):092-711-4588(中央区、南区及び西区の担当:開発指導第2係)
FAX番号:092-733-5584
電子メール:kaihatsu-kenchiku.HUPB@city.fukuoka.lg.jp
WEB:開発許可申請等の手引き【開発指導ホームページ】(索引附き)
受付時間:月曜~金曜(休庁日除く)午前9時15分~午前12時