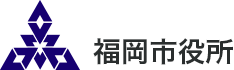「建築許可」の基準と解説(法第43条第1項)
このページではいわゆる「建築許可」の基準と解説を掲載しております。次のリンクから該当箇所へジャンプできます。
※ 法律等の名称については、次の略称を用います。法:都市計画法、令:都市計画法施行令、規則:都市計画法施行規則、市条例:福岡市開発行為の許可等に関する条例、市規則:福岡市開発行為の許可等に関する規則
※ このページの主な内容は、冊子の『開発許可制度と開発許可申請の手引き』(PDF)にも掲載しております。
1 概要
(1) 定義
「建築許可」とは、市街化調整区域における建築行為等であって、開発行為を伴わないものに対する許可のことを言います。開発許可制度においては、都市計画法第43条第1項に基づいて、開発許可権者(福岡市では福岡市長)が与える許可のことです。
「建築許可」というのは通称であり、正式な名称は、「建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設許可」です。
(2) 規制の趣旨
市街化調整区域においては、無秩序な市街化(スプロール)を抑制するために、開発行為は原則として認められていませんが、開発行為をせず、建築行為だけをする場合でも、一部の許可を要しない場合を除き、許可が必要となります。
(3) 許可の対象
市街化調整区域では特例的に認められるものについてのみ許可ができることとなっています。
【技術基準】としては、排水施設の基準と軟弱地盤の対策等の基準が定められています。また、「建築許可」は、開発行為に対する許可である開発許可とは異なり、すでに土地利用が図られていた土地に対して建築行為を認める制度であるため、開発許可と比べて手続きは簡便です。
【立地基準】としては、開発許可の場合に準じた基準が定められています。
(4) 許可が不要な場合
特例的に認められるものについては、開発許可の場合における「開発許可が不要な場合」と同様に、「建築許可が不要な場合」の定めがあります。詳細は次のリンク先をご覧ください。
(5) その他
都市計画法第42条第1項(開発許可を受けた土地における建築等の制限)のただし書き許可も含めて「建築許可」と称する場合もあります。この場合は、同法第43条の許可基準のような具体的な規定がありませんが、これに準じた許可の運用を行っています。
2 基準と逐条解説
ここでは最初に基準(法第43条等)を引用し、必要に応じて、基準ごとに解説等を加えています。
法第43条第1項本文(開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の制限)
【引用】
何人も、市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、都道府県知事の許可を受けなければ、第29条第1項第2号若しくは第3号に規定する建築物以外の建築物を新築し、又は第一種特定工作物を新設してはならず、また、建築物を改築し、又はその用途を変更して同項第2号若しくは第3号に規定する建築物以外の建築物としてはならない。
【解説】
市街化調整区域において、開発行為を伴わない建築行為等について、法第29条第1項(開発許可)と同様の趣旨から制限を行おうとする規定です。
規制の対象となる行為には次のものがあります。
- 建築物の新築
- 建築物の改築
- 建築物の用途の変更
- 第一種特定工作物の新設
ここでいう「新築」とは建築物のなかった敷地内での建築行為に限られず、既存建築物の建替の場合であっても、建替え後の建築物の用途、規模又は構造が従前の建築物と著しく異なる場合には、「新築」に該当します。
法の適用除外として、法第29条第1項第2号(農林漁業用施設・住宅)及び第3号(公益上必要な建築物)が本文に規定され、次に示す同項ただし書き各号の列記とは書き分けられていますが、それは、これらの建築物がもともと市街化調整区域でも禁止すべきではないという性格がやや強いためです。
法第43条第1項ただし書き
【引用】
ただし、次に掲げる建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設については、この限りでない。
一 都市計画事業の施行として行う建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設
二 非常災害のため必要な応急措置として行う建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設
三 仮設建築物の新築
四 第29条第1項第9号に掲げる開発行為その他の政令で定める開発行為が行われた土地の区域内において行う建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設
五 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの
【解説】
「建築許可」が不要となる行為が示されています。
第4号に規定する政令としては令第34条がありますので、次のリンク先をご覧ください。
- 「令第34条」(ページ内のリンク先)
法第43条第2項
【引用】
前項の規定による許可の基準は、第33条及び第34条に規定する開発許可の基準の例に準じて、政令で定める。
【解説】
許可の基準は、開発許可の【技術基準】(法第33条)と【立地基準】(法第34条)に対応して、それぞれ建築許可の【技術基準】(令第36条第1項第1号)と【立地基準】(令第36条第1項第3号)が規定されています。
具体的な基準については、次のリンク先をご覧ください。
- 「令第36条」(ページ内のリンク先)
法第43条第3項
【引用】
国又は都道府県等が行う第一項本文の建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設(同項各号に掲げるものを除く。)については、当該国の機関又は都道府県等と都道府県知事との協議が成立することをもつて、同項の許可があつたものとみなす。
【解説】
国又は都道府県等が行う一定の建築行為については、国の機関又は都道府県等と都道府県知事(福岡市では福岡市長)との協議が成立することをもって、「建築許可」があったものとみなされます。この協議については、協議するだけではなく、協議を成立させなければなりません。
国又は都道府県等とみなされる者は次のとおりです。
- 独立行政法人空港周辺整備機構
- 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
- 独立行政法人都市再生機構
- 地方住宅供給公社
- 日本下水道事業団
令第34条(その開発行為が行われた土地の区域内における建築物の新築等が建築等の許可を要しないこととなる開発行為)
【引用】
法第43条第1項第4号の政令で定める開発行為は、次に掲げるものとする。
一 法第29条第1項第4号から第9号までに掲げる開発行為
二 旧住宅地造成事業に関する法律(昭和39年法律第160号)第4条の認可を受けた住宅地造成事業の施行として行う開発行為
【解説】
次の開発行為が行われた土地の区域内において行う建築行為等が許可不要となります。
- 都市計画事業の施行として行う開発行為
- 土地区画整理事業の施行として行う開発行為
- 市街地再開発事業の施行として行う開発行為
- 住宅街区整備事業の施行として行う開発行為
- 防災街区整備事業の施行として行う開発行為
- 公有水面埋立法(大正10年法律第57号)第2条第1項の免許を受けた埋立地であつて、まだ同法第22条第2項の告示がないものにおいて行う開発行為
- 旧住宅地造成事業に関する法律(昭和39年法律第160号)第4条の認可を受けた住宅地造成事業の施行として行う開発行為
令第35条(開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の許可を要しない通常の管理行為、軽易な行為その他の行為)
【引用】
法第43条第1項第5号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。
一 既存の建築物の敷地内において行う車庫、物置その他これらに類する附属建築物の建築
二 建築物の改築又は用途の変更で当該改築又は用途の変更に係る床面積の合計が10平方メートル以内であるもの
三 主として当該建築物の周辺の市街化調整区域内に居住している者の日常生活のため必要な物品の販売、加工、修理等の業務を営む店舗、事業場その他これらの業務の用に供する建築物で、その延べ面積が50平方メートル以内のもの(これらの業務の用に供する部分の延べ面積が全体の延べ面積の50パーセント以上のものに限る。)の新築で、当該市街化調整区域内に居住している者が自ら当該業務を営むために行うもの
四 土木事業その他の事業に一時的に使用するための第一種特定工作物の新設
【解説】
「建築許可」が不要となる行為の範囲は、開発許可の場合の法第29条第1項第11号及び令第22条の規定に準じるものとなっています。
なお、従前の建築物又は第一種特定工作物の全部若しくは一部を除却し、又は災害等により従前の建築物等の全部若しくは一部が焼失した場合において、従前の建築物等と規模、構造、用途、敷地の位置がほとんど同様の建築物等の建築等をする場合は、当該建築等は新築及び改築には該当せず、法第43条の規制を受けません。
令第36条(開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の許可の基準)
【解説】
本条は法第43条第2項の政令に定める基準です。
令第36条第1項
【引用】
都道府県知事(指定都市等の区域内にあつては、当該指定都市等の長。以下この項において同じ。)は、次の各号のいずれにも該当すると認めるときでなければ、法第43条第1項の許可をしてはならない。
【解説】
「建築許可」の基準として、以下に第1号の【技術基準】と第3号の【立地基準】が定められています。
令第36条第1項第1号(いわゆる【技術基準】)
【引用】
当該許可の申請に係る建築物又は第一種特定工作物の敷地が次に定める基準(用途の変更の場合にあつては、ロを除く。)に適合していること。
令第第36条第1項第1号イ
【引用】
排水路その他の排水施設が、次に掲げる事項を勘案して、敷地内の下水を有効に排出するとともに、その排出によつて当該敷地及びその周辺の地域に出水等による被害が生じないような構造及び能力で適当に配置されていること。
(1) 当該地域における降水量
(2) 当該敷地の規模、形状及び地盤の性質
(3) 敷地の周辺の状況及び放流先の状況
(4) 当該建築物又は第一種特定工作物の用途
令第36条第1項第1号ロ
【引用】
地盤の沈下、崖崩れ、出水その他による災害を防止するため、当該土地について、地盤の改良、擁壁又は排水施設の設置その他安全上必要な措置が講ぜられていること。
【解説】
本号は、「建築許可」の【技術基準】です。開発許可における、法第33条第1項第3号及び第7号に対応するもので、排水施設の基準と軟弱地盤の対策等の基準を定めています。「建築許可」の対象となるものは、ほとんどの場合自己の居住の用又は自己の業務の用に供するもので、その規模も一敷地程度と考えられることから、法第33条第1項各号に掲げる項目(同条第5号に掲げるものを除く。)のうち災害等の当該敷地の周辺部に与える影響を考慮すれば足りるとして、許可基準が開発許可の場合よりも限定されています。
令第36条第1項第2号
【引用】
地区計画又は集落地区計画の区域(地区整備計画又は集落地区整備計画が定められている区域に限る。)内においては、当該許可の申請に係る建築物又は第一種特定工作物の用途が当該地区計画又は集落地区計画に定められた内容に適合していること。
令第36条第1項第3号(いわゆる【立地基準】)
【引用】
当該許可の申請に係る建築物又は第一種特定工作物が次のいずれかに該当すること。
【解説】
本号は「建築許可」の【立地基準】です。開発許可における法第34条に基準に対応するもので、市街化調整区域における「建築許可」の基準となっています。
令第36条第1項第3号イ
【引用】
法第34条第1号から第10号までに規定する建築物又は第一種特定工作物
令第36条第1項第3号ロ
【引用】
法第34条第11号の条例で指定する土地の区域内において新築し、若しくは改築する建築物若しくは新設する第一種特定工作物で同号 の条例で定める用途に該当しないもの又は当該区域内において用途を変更する建築物で変更後の用途が同号 の条例で定める用途に該当しないもの
【解説】
同号ロは、開発許可における法第34条第11号に対応するものであり、同号の条例で指定する土地の区域内において行われ、同号の条例で定める制限用途に該当しない建築行為が規定されています。
令第36条第1項第3号ハ
【引用】
建築物又は第一種特定工作物の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認められる建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設として、都道府県の条例で区域、目的又は用途を限り定められたもの。この場合において、当該条例で定める区域には、原則として、第8条第1項第2号ロからニまでに掲げる土地の区域を含まないものとする。
【解説】
同号ハは、開発許可における法第34条第12号に対応するものですが、令36条第1項第3号イと異なり、同号ハの条例を法第34条第12号の条例とは別に定めることとされています。これは、周辺の市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域において行うことが困難又は著しく不適当と認められる開発行為と建築行為は、必ずしも区域及び用途が一致するものではないとの考えによるものとされています。
なお、福岡市においては、これらは同じ条例としています(福岡市開発行為の許可等に関する条例第11条第2項)。
令第36条第1項第3号ニ
【引用】
法第34条第13号に規定する者が同号に規定する土地において同号に規定する目的で建築し、又は建設する建築物又は第一種特定工作物(第30条に規定する期間内に建築し、又は建設するものに限る。)
【解説】
同号ニは、開発許可における法第34条第13号に対応するものであり、いわゆる「既存権利」の規定です。
令第36条第1項第3号ホ
【引用】
当該建築物又は第一種特定工作物の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域内において建築し、又は建設することが困難又は著しく不適当と認められる建築物又は第一種特定工作物で、都道府県知事があらかじめ開発審査会の議を経たもの
【解説】
同号ホは、開発許可における法第34条第14号に対応するものであり、許可に当たっては、あらかじめ開発審査会の議を経ることとされています。
令第36条第2項
【引用】
第26条、第28条及び第29条の規定は、前項第1号に規定する基準の適用について準用する。
3 参考(関連ページへのリンク等)
(1) 「建築許可」の手続き
「建築許可」の申請で使用する様式や添附資料については次のリンク先をご覧ください。
- 「建築許可の様式」
(2) 許可を要しない場合
「建築許可」が不要な場合については、次のリンク先をご覧ください。
- 開発行為がなく建築許可が不要な場合(市街化調整区域) → 「建築許可が不要な場合を知りたい。」
(3) 許可を要しない場合の手続き
開発許可が不要の場合や建築許可が不要の場合の手続きなどで使用する「開発行為等適合証明申請書」及び「開発行為等適合証明書」の様式については、次のリンク先をご覧ください。
【お問合せ先】
部署:住宅都市局建築指導部開発・建築調整課
住所:福岡市中央区天神一丁目8番1号(市庁舎4階)
電話番号(1):092-711-4587(東区、博多区、城南区及び早良区の担当:開発指導第1係)
電話番号(2):092-711-4588(中央区、南区及び西区の担当:開発指導第2係)
FAX番号:092-733-5584
電子メール:kaihatsu-kenchiku.HUPB@city.fukuoka.lg.jp
WEB:開発許可申請等の手引き【開発指導ホームページ】(索引附き)
受付時間:月曜~金曜(休庁日除く)午前9時15分~午前12時