質問
国民健康保険の保険料の減額・軽減・減免の条件について知りたい。
回答
保険料の減額・軽減・減免の条件は次のとおりです。
1 保険料の減額
前年中の所得が政令で定める基準額以下の世帯に対して保険料の均等割と平等割の7割・5割・2割を減額しています。
また、令和4年度から未就学児の保険料の均等割の2分の1を減額しています。
※詳しくは、保険料の減額をご覧ください。
2 非自発的失業者の保険料軽減
雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」として失業等給付を受ける人は、前年の給与所得をその30/100とみなして保険料の算定を行います。
離職日時点で65歳未満の人が対象です。
(年齢計算ニ関スル法律及び民法143条の規定に基づき、65歳の誕生日の前々日までに離職された人が対象です。)
※「特定受給資格者」とは、雇用保険受給資格者証の離職理由コードが11、12、21、22、31、32に該当する人。
「特定理由離職者」とは、雇用保険受給資格者証の離職理由コードが23、33、34に該当する人。
※特例受給資格者証、高年齢受給資格者証をお持ちの人は対象になりません。
※非自発的失業者の保険料軽減を受けるには、届出が必要です。
3 出産(予定)被保険者の産前産後期間に係る所得割額と均等割額の減額
出産する予定又は出産した被保険者に係る、産前産後期間相当分の所得割額と均等割額を届出により減額します。
産前産後期間相当分とは、出産(予定)日の属する月の前月から、出産(予定)日の属する月の翌々月までの計4か月分です。(多胎妊娠の場合は、出産(予定)日の属する月の3か月前から、出産(予定)日が属する月の翌々月までの計6か月分です。)
※妊娠85日以上の分娩が対象です。(流産、死産、早産及び人工妊娠中絶も含みます。)
※令和6年1月以降の産前産後期間相当分にかかる、出産被保険者の所得割額と均等割額が対象です。
4 保険料の減免
災害、失業、倒産、その他事情により保険料の納付が困難になったときは、申請により保険料の減免を受けられる場合があります。
また、令和3年度から中学生以下の子どもが2人以上いる世帯を対象に多子世帯減免を適用しています(多子世帯減免の事由に該当する世帯からの減免申請は不要です)。
※詳しくは、保険料の減免をご覧ください。
※保険料の減免を受けるには当該年度内に申請を行う必要があります。詳しくは住所地の区役所(出張所)保険年金担当課にご相談ください。
関連リンク
お問い合わせ先
福岡市東区箱崎2丁目54番1号
電話番号:092-645-1102
FAX番号:092-631-6463
hokennenkin.HIWO@city.fukuoka.lg.jp
福岡市博多区博多駅前2丁目8番1号
電話番号:092-419-1118
FAX番号:092-441-0075
hokennenkin.HAWO@city.fukuoka.lg.jp
福岡市中央区大名2丁目5番31号
電話番号:092-718-1122
FAX番号:092-725-2117
hokennenkin.CWO@city.fukuoka.lg.jp
福岡市南区塩原3丁目25番1号
電話番号:092-559-5152
FAX番号:092-561-3444
hokennenkin.MWO@city.fukuoka.lg.jp
福岡市城南区鳥飼6丁目1番1号
電話番号:092-833-4125
FAX番号:092-844-6790
hokennenkin.JWO@city.fukuoka.lg.jp
福岡市早良区百道2丁目1番1号
電話番号:092-833-4323
FAX番号:092-846-9921
hokennenkin.SWO@city.fukuoka.lg.jp


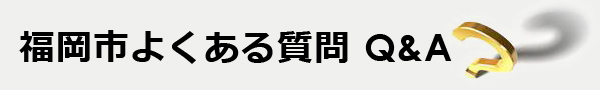

 東区
東区 博多区
博多区 中央区
中央区 南区
南区 城南区
城南区 早良区
早良区 西区
西区