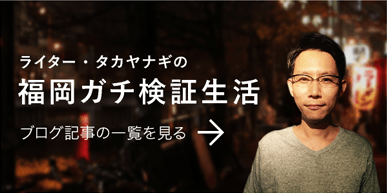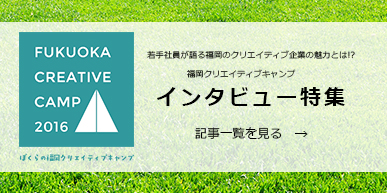ここ最近、にわかに注目を集めている博多うどん。先行の記事(https://www.city.fukuoka.lg.jp/hash/news/archives/102)でご紹介したように、博多うどんは“食べても減らない”の言葉通り、旨味濃厚な出汁(だし)を吸って膨らむ柔らかい麺が特色。もちろん、ごぼ天・丸天といったトッピングも欠かせません。
注目度が高まっているとはいえ、現状では、博多うどんの知名度は「全国レベル」でないのも事実。“コシ”の強さがウリの讃岐うどん店は、地元・香川県に限らず日本全国で無数にあるのに、“やわやわ”な博多うどんは、県外ではあまり見かけないのはなぜだろう……と、疑問を抱く福岡出身者も多いことでしょう(実際に東京でも、博多うどん店を見かけることはあまりありません)。
書籍『博多うどんはなぜ関門海峡を越えられなかったのか~半径1時間30分のビジネスモデル』は、そんな博多うどんの謎に肉薄したグルメ本。
その著者であるサカキシンイチロウさんは、外食産業のフードコンサルタント。どうして、世界中の一流グルメが揃う東京に、あの美味しい博多うどんは進出してこないのか――そんな素朴な疑問を抱いたのをきっかけに、理由を探るべく福岡にて現地取材を敢行。「牧のうどん」「ウエスト」「かろのうろん」「うどん平」「因幡うどん」などを食べ歩き、コンサルタントの立場から、博多うどんの素晴らしさ、福岡にとどまる理由、東京進出へのシミュレーションなどを考察しその謎を分析しています。
そこで今回は、著者のサカキさんに、同書の取材を通じて知った博多うどんの魅力について、お聞きしました!
■とんこつラーメンと違って博多うどんが“内弁慶”なのはナゼ?
“博多うどんはたしかに美味しいけど、(ヨソの人に)自慢するほどのものでもないのでは……”
昨今の博多うどんブームに、内心そう思っている福岡市民も少なくないかもしれません。しかし、美食家でもあるサカキさんは「地元で食べられているような本物の博多うどんは、間違いなくめちゃくちゃ美味しい!」と太鼓判を押します。
にもかかわらず博多うどんは、なぜ“内弁慶”なのでしょうか? 福岡発の「博多ラーメン(とんこつラーメン)」は、いまや世界でもその地位を確立しようとしているのに、です。
サカキさんはこう言います。
「そもそもラーメン屋とうどん屋って、ビジネスモデルはもちろんのこと、経営者のメンタリティがだいぶ異なります。僕のように飲食のコンサルタントをしていると、実は、ラーメン屋からの相談って一番多い。とくに博多ラーメンは作り手=経営者で、タオル頭をに巻いて気合入りまくり、というイメージそのままの“野心の塊”。ところが、うどん屋にはその野心が感じられないんですよ(笑)。とくに、福岡でうどん作っている人を見ると『東京に店を出そう』という気はなく、のんびりした家業経営の店がほとんど。『ビジネス』ではなく『商売』をやっている感覚なんです。そこが、博多うどんが関門海峡を越えていない一因でしょうね」
博多うどん店の経営者は、そもそも東京など「外」に進出する気がないというのがサカキさんの分析。もちろん家業感覚が大半だという博多うどんでも、「牧のうどん」のように県内に20店舗展開しているお店もあります。サカキさんもその点に注目しているとか。
「『牧のうどん』は、この時世に公式サイトも持たず、ネットで検索しても個人ブログや食べログしか引っかからない。にもかかわらず、大繁盛なんです。ただ、取材してわかったのですが、その『牧のうどん』ですら、『ビジネス』をやっているのではなく『商売』なんですよね。事実、同チェーンの出店エリアは、より収益が見込める市中心部ではなく郊外ばかり。以前、キャナルシティ博多に出店したものの、“お客さんが来すぎてクオリティが保てない”という理由で撤退しているのも象徴的です。博多うどんは東京どころか、福岡中心部にすら出られない、と言えるかもしれません」(サカキさん)
同書では博多うどん東京進出シミュレーションの顛末も描かれていますが、この道30年、1000店以上の新規開拓を手掛けて来たサカキさんをしても“博多うどんを東京に持ってくるのは無理”と断言します。
「もちろん家業経営的に1店舗だけでやるなら無理ではないですが(それでも結構大変でしょう)、『牧のうどん』のようにチェーン展開を考えた場合、やはりコストの壁が立ちはだかる。まず、東京都内に、ある程度大きな麺工場と出汁工場を設ける必要があるので、その設備投資を回収する必要があります。また、そうした工場から品質を劣化させずに麺や出汁をお店に輸送するには、1時間半までに届けなければいけない。そうなると、山奥に工場を作るわけにもいかず、コストはかさむばかり。同書でも検証しましたが、東京で本格的な博多うどん店をやるには、『1杯2000円』という設定にしなければいけません(苦笑)。要は再現するのがかなり困難だということ。そこがさぬきうどんとの大きな違いで、博多うどんが東京に進出できない最大の要因と見ています」(サカキさん)
東京在住の福岡人にとっては残念すぎる分析結果ではありますが、一方で地元に戻らなければ食べられない味だと思うと、博多うどん愛は深まるばかりなのではないでしょうか。
最後にサカキさんも、福岡人の博多うどんに対する特別な感情についてこう語ります。
「僕自身の経験でも、福岡を訪れて“ 呼子のイカを食べ、中洲で一杯、そして豚骨ラーメン食べて帰る”うちは、まだまだお客様扱いされている感覚がありました。そこから一歩進んだな、と感じたのが、うどんを話題にした時です。『よく行くうどん屋はどこですか?』と尋ねた途端、スイッチが入ったかのように喧々諤々の議論が始まり、それぞれ自分の贔屓のお店に連れて行きたがる。福岡人のそんなうどん談義の場に入れて、相槌が打てたら、それはもう地元の人同然ですよね」
なお、同書では、地元・福岡の人にお気に入りのうどん屋アンケートを実施。それによると、1番人気は「牧のうどん」と「因幡(いなば)うどん」、その次に来たのがニューウェーブの裏打ち系(※北九州市発祥の「裏打ち会」という「うどん系列」)で、さらに「ウエスト」が続いたとのこと。
まだ当分の間、関門海峡は越えそうもない博多うどん。福岡に行った際には、是非、気になるお店を訪れてみてはいかがでしょうか?
【プロフィール】
サカキシンイチロウ
1960年、愛媛県松山市生まれ、慶應義塾大学卒。著書に『おいしい店とのつきあい方。』(角川文庫)がある。2015年12月『博多うどんはなぜ関門海峡を越えられなかったのか~半径1時間30分のビジネスモデル』を出版。
【関連リンク】
サカキノホトンブログ
http://sakakishinichiro.com/