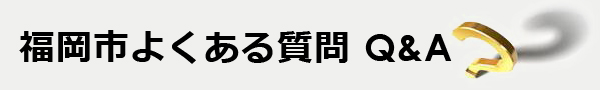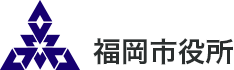質問
「開発行為に関する区域」とは何か。(都市計画法第4条第13項関係)
回答
「開発行為に関する区域」とは、開発許可制度において、開発区域に隣接する土地で切土や盛土などの造成工事を開発区域内の工事と一体的に行うことにより、構造や工事施工の観点から安全性・合理性がある場合に、開発区域とは別に設定する土地の区域のことです。
例えば、「開発行為に関する区域」を設定すれば、開発区域の隣接地にある窪地を埋めたり、塚を削ったりすることにより、地盤面の高低差が小さくなり、擁壁を設置する必要がなくなります。
■開発行為に関する区域の取扱い
(1) 範囲は必要最小限とします。
(2) 一体開発と認められる土地の区域については、開発区域として取扱います。
(3) 「開発行為に関する区域」の区域内には原則として擁壁等の構造物を設置することはできません。設置する場合は、開発区域として取扱います。
(4) 手続き上は、開発区域には含みませんが、「開発行為に関する区域」として扱います。
(5) 「開発行為許可申請書」等に記入する地番及び面積はそれぞれ分けて書きます。
(6) 造成に関して権利者(土地所有者等)の施行同意が必要です。(都市計画法第33条1項第14号)
(7) 「土地利用計画図」に「開発行為に関する区域」の範囲を明示します。
(8) 工事完了検査の対象となります。ただし、工事完了公告には記載されません。
■申請書の記入例
「開発行為許可申請書」等への記入例については次の通りです。
●(例) 開発区域に含まれる地域の名称:天神一丁目8番1(開発行為に関する区域:天神一丁目8番2の一部)
●(例) 開発区域の面積:2,000平方メートル(開発行為に関する区域:100平方メートル)
【お問合せ先】
部署:住宅都市局建築指導部開発・建築調整課
住所:福岡市中央区天神一丁目8番1号(市庁舎4階)
電話番号(1):092-711-4587(東区、博多区、城南区及び早良区の担当:開発指導第1係)
電話番号(2):092-711-4588(中央区、南区及び西区の担当:開発指導第2係)
FAX番号:092-733-5584
電子メール:kaihatsu-kenchiku.HUPB@city.fukuoka.lg.jp
WEB:開発許可申請等の手引き【開発指導ホームページ】(索引附き)
受付時間:月曜~金曜(休庁日除く)午前9時15分~午前12時