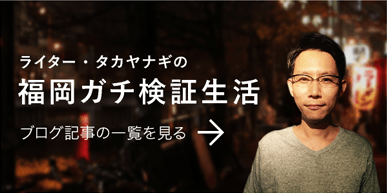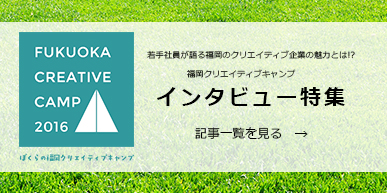福岡と東京を拠点に空間設計を軸とする「ケース・リアル (CASE-REAL)」と、プロダクトデザインに特化する「二俣スタジオ (KOICHI FUTATSUMATA STUDIO)」を主宰する空間・プロダクトデザイナーの二俣 公一(ふたつまた・こういち)さん。
昨年は、超カリスマ的な人気を誇るLA発のセレクトショップ「UNION」の東京進出にあたって、「UNION TOKYO」の店舗デザインを手がけたことが国内外で話題となりましたが、その他にも福岡の老舗和菓子店「鈴懸」やミシュランも認めたフレンチ・シェフの新店「レストランSOLA」など、福岡の物件を数多く手がけていることでも知られています。
今回は、福岡在住のまま国内外で活躍する二俣さんの事務所を訪れ、仕事の話、福岡の話をじっくりとうかがいました。
―まずは現在どのようなお仕事をされているのか教えてください。
二俣 「ケース・リアル」という設計事務所と「二俣スタジオ」というプロダクトデザインに特化した名義の2つで仕事をしています。生活のベースは福岡で、飛行機で東京にある事務所に通っていて、月の半分は東京にいます。昔に比べると移動がしんどくなってきてはいますが(笑)、こういう生活を13年間続けて慣れているので、特にストレスはないですね。
―なぜ二拠点で活動されているのでしょうか?
二俣 僕は九州産業大学の建築学科で学んでいたのですが、当時から企業に就職するという働き方は、自分に向いてないと考えていて。ですから就職せずに自分自身でデザインや建築の仕事をしたいと思っていました。となれば、まずは物を作って人にアピールする必要があった。そこで、大学3年から卒業した後1年くらいまで、外部スタッフとして福岡で建築家の方のお手伝いをしながら、プロダクトの試作品を作っては東京で発表することを続けました。4〜5年はそうしていたので、生活の拠点は福岡に置いたまま東京でも活動するというスタイルがその頃に自分の中でも定着し、それが今でも続いている形ですね。
―下積み時代は長かったんですか?
二俣 短かったわけではないですが、ありがたいことに大学を卒業して間もない時期に「CONCENTS」というキューブ型コンセントタップなどのプロダクトデザインで少しだけ注目を集めることになりました。その後、製品化もされ、それがデザインの世界でやっていく第一歩になりました。
―建築やデザインを通じてどのようなことを表現したいと考えていますか?
二俣 プロダクトでも建築でも、自分の作品を作ろうという思いはあります。とはいえ独りよがりな表現も違うかなと。建築やインテリアの仕事は、発注主や施主の目的や目標を達成するために、きっちり機能を満たさなければならない。だから打ち合わせにもしっかり時間をかけて、コンセプトを練ることを重視しています。そして形に落とし込む中で、機能美や僕らにしかできない表現を追求していければなと思っています。

(天井から吊り下げて使うモビール「IN THE SKY(edition HORIZONTAL(E&Y))」。福岡事務所の近くにある鳥飼八幡宮に参拝に訪れた際、枯れ枝が引っかかり止まっている様子を美しいと感じて、そこから着想したプロダクト。固定具を一切使わず、本体の自重のみでバランスを保っている。)
家賃が安く、環境の良い福岡なら個人でもダイナミックな試みができる
―二俣さんは日本各地でさまざまな物件をデザインされています。場所によって、たとえば東京と福岡では求められるデザインの傾向は異なりますか?
二俣 かつては「東京は大規模で外に向けて発信できる」だったり、「福岡だから地元に向けて小規模で」みたいな考え方があったと思うんですが、最近はあまり変わらなくなっている気がします。地方には、素晴らしい発想や高い志を持っている方がたくさんいますからね。逆に、東京よりも発想や志を形にしやすかったりもするんです。例えば地価が高い東京で初めて飲食店をオープンするとなれば、ランニングコストを抑えるために店舗は小さくなりがちです。そもそも広いスペースを探すのが大変だったりもする。ところが福岡は、東京に比べれば地価が安く、周りには豊かな自然環境が広がっています。だからダイナミックな試みが可能じゃないかと。最近、福岡にできた「レストランSOLA」という100坪ほどある大きなレストランをデザインしたんですが、地方だからこそのスケール感かもしれません。世界トップレベルの技術と意識を持った吉武広樹さんというシェフの力量でもあると思いますが、オーナーシェフとしてあの規模を仮に東京でやるとなると、かなり大変ですよね。

(博多ベイサイドプレイスにある食のスペース「レストランSOLA」。店内にはレストラン、バーのほか、フードラボを併設し、九州の食材を用いたメニューを展開している。)
二俣 それと、ちょっと変わったところで言えば、数年前に筑後にある養豚農場の一部も手がけました。巨大な敷地の中の使わなくなった豚舎を改築したんです。生産したブランド豚を使った料理会や展示のためのスペース、茶室や寝泊まりに使える和室に、品種改良のラボ、あとは事務所スペースもあります。一個人がそういうアイデアを思いついてから比較的すぐに実現できる可能性が高いのも、福岡を含めた地方の環境ならではかなと思います。
外の世界を知ることで中の魅力を知る
―二俣さんは、常に福岡と東京を行き来しています。何か見えてくるものはありますか?
二俣 福岡の外を見ること、知ることによって、より客観的に福岡の良さが分かるようになったと思っています。福岡に鈴懸という老舗の和菓子屋があって、11年前から全国各地にある店舗のデザインをお手伝いさせていただいています。この鈴懸の三代目社長は非常にクリエイティブな方で、生粋の博多っ子ですが、決して内に引き籠もることがないんですね。常に視線や思考を日本全国や海外といった外に向けている。地域に根ざしたブランドであるだけでなく「場所がどこであれ自分たちの考えをきちんと表現していこう」というスタンス。そういう精神的な部分でもとても共感を持って、お仕事させていただいています。

(福岡市博多区に本店を構える創業九十余年の老舗和菓子店「鈴懸」。新宿伊勢丹、東京ミッドタウン日比谷、名古屋高島屋にも出店している。)
向き不向きはあっても、「ほど良い」街・福岡
―二俣さんが考える福岡の良さを教えてください。
二俣 一言で表現するなら「ほど良い」かなと。仕事だけをするなら東京の方が良いかなとも思うんです。でも少し、しんどいかもしれませんね。福岡は、一生懸命働いて時には休むことも許される、ほど良い空気感。情報もモノもある程度は持っている。かといって「ハードに働いて、とにかくたくさん稼ぐのがいい」と考えているようでもない。福岡には、お金がたくさんなくても豊かな生活ができる側面があるからだと思うんですよね。それなりに楽しめる生活が送れて、近くに山や海もあって。
―では、どんな人が「福岡向き」だと思われますか?
二俣 福岡に限った話ではないですが、自分がやるべきことや目標がはっきりしている人ですね。福岡には色んな顔があります。例えばコミュニティが小さくて、関係性が濃密。良いことである反面、クールというかドライな関係性に慣れている人には息苦しいかもしれません。移住してきた人が、なんとなく小さなコミュニティに巻き込まれて、そのうち面倒になって東京に帰るというパターンも聞きます。ただ目的さえはっきりしていれば、環境の良さを利用していけるんじゃないでしょうか。
―最後になりますが、今後の展望について教えてください。
二俣 将来どうしたいというような展望は、特にないんですよ。この20年ずっとそうです。結局は一つひとつのプロジェクトに対して、まっすぐ向き合って、しっかりと答えを出すことが大事だと思っているので。強いて言うなら仲間やスタッフと「この仕事を続けられるだけ続けたい」ということですね。
―なぜデザインの仕事を続けてこられたんだと思いますか?
二俣 僕は、小さいときからモノを作ることや絵を書くことが本当に好きでした。結局、今もその延長線上にいて、ちょっとずつ形を変えながら好きなことを続けています。ビルのような建築でも、個人宅でも、手のひらのプロダクトでも、それは変わりません。いつまでもモノを作ることを考える人間でいたいし、依頼してくださる人たちと一緒に新しい挑戦をしていきたいなと思っています。
<プロフィール>
二俣 公一(ふたつまた・こういち)さん
空間・プロダクトデザイナー。昭和50(1975)年鹿児島生まれ。福岡と東京を拠点に国内外でインテリア・建築・家具・プロダクトからオブジェクト作品に至るまで多岐にわたるデザインを手がける。「ケース・リアル(CASE-REAL)」「二俣スタジオ(KOICHI FUTATSUMATA STUDIO)」両主宰。