消防吏員
消防局などで火災、救急および救助といった有事の緊急活動はもちろん、「火災予防運動」などの防災意識の啓発も行います。

多くの市民の命と健康を守るために最良の判断を
消防局 東消防署 警備課 箱崎出張所(第2) 日髙
(平成27年度入庁)
Q1 どうして福岡市職員になろうと思いましたか?
地元の宮崎で消防職員になるという選択も考えましたが、福岡市のように大きな組織なら業務の幅が広く、より高度な業務に携わることができると考え、福岡市の消防職員になることを目指しました。
Q2 実際に入庁してみてどう感じましたか?
入庁後、消防隊・指揮隊・救助隊・救急隊や日勤業務など様々な業務に携わらせていただきました。色々な業務を経験する中で「消防」という枠組みの中でも業務の幅がかなり広いことを体感するとともに、それぞれの業種にプロフェッショナルな職員が在籍しており、福岡市消防局職員の質の高さを感じました。
Q3 現在の業務内容を教えてください。
警備課では、指揮隊、警防隊、救助隊、救急隊など消防における実働部隊が配置されています。
私は救急業務に従事しており、市民からのけがや急病などの救急要請に対し、救急車で出動し、必要な処置を行いながら救急搬送することが主な業務です。
出動以外にも、出動に伴う報告書作成などの事務作業や、教育、訓練など行っています。
Q4 業務の中で特にやりがいや魅力を感じるところを教えてください。
多くの救急現場に出動してきましたが、1つとして同じ現場はなく、その場その場で状況に応じた最良の判断を行う必要があります。判断に迷うような場面もあり、簡単ではない業務ですが、そこにやりがいを感じています。
ある一日のスケジュール
- 午前8時45分 勤務明けの救急隊からの申し送り、個人資器材の準備
- 午前8時55分 全体ミーティング
- 午前9時00分 大交代、交代後ミーティング、朝の体操
- 午前9時15分 資器材点検、無線テスト
- 午前 救急出動、事務処理
- 正午 昼休み(出動状況により変わる)
- 午後1時00分 救急出動、事務処理
- 午後6時30分 夕食(出動状況により変わる)
- 救急出動、事務処理
- 午前0時00分 仮眠、救急出動
- 午前6時00分 救急出動、事務処理
- 午前8時45分 次の勤務の救急隊に申し送り
- 午前8時55分 全体ミーティング
- 午前9時00分 大交代、個人資器材撤収

Q5 現在の職場の雰囲気を教えてください。
現在の職場は、隔日勤務で24時間寝食を共にしており、必然的に会話などのコミュニケーションが普通の職場よりも多くなります。
救助隊と救急隊が勤務しており、どちらも平均年齢は30歳程度の若い職員を中心に構成されています。そのため職場は明るく活気があり、良好な職場環境が整っていると感じています。
ただ働きやすいだけではなく、お互いに意見なども言いやすく、それが現場や訓練などの業務にも活かされ、業務全体の質の向上につながっていると感じています。
Q6 業務の中で苦労したことや大変だったことを教えてください。
救急現場は1つとして同じ現場はなく、時間的余裕がない中で、その場に応じた適切な判断を下す必要があることに、日々苦労しています。現場活動が終わった後、「活動中のあの判断は正しかったのか」と考えることも多々あります。
特殊な現場(危険な現場、救急隊以外の隊との連携が必要な現場など)では、特に判断に迷うことがあり、適切な判断力を身に付けることが今後の課題です。
Q7 仕事を通じて発見したことや感動したことを教えてください。
仕事を通じて、コミュニケーションの大切さを改めて思い知りました。
救急業務では、傷病者、その家族などの関係者、搬送先の病院スタッフ、一緒に出動する隊員など、様々な相手とコミュニケーションをとる必要があります。救急現場でそれら全てと良好なコミュニケーションを築くためには、対人間の接遇、プレゼンテーション能力、医学的知識、救急の技術など様々な要素が必要とされますが、そのすべてがうまく噛み合い、結果として良い活動ができると、感動を覚えます。
Q8 これから経験したいことなどを教えてください。
令和5年度に半年間の研修を経て、救急救命士の資格を取得し、救急現場で傷病者により多くの処置を行うことができるようになりました。この資格を最大限に生かせるように、今後も引き続き救急業務に従事したいと考えています。救急隊員として経験を積み、より多くの市民の方の命や健康を守ることができる救急救命士になることを目標にしています。
Q9 休日はどのように過ごしていますか。
交代制の24時間勤務であるため、非番日は次の勤務に備えてできるだけ休息をとるようにしています。
休みの日は、家族と過ごす時間を大切にしています。時間がある時は趣味の登山や、TVゲームをするなどしてリフレッシュすることもあります。
Q10 最後に、これから福岡市職員を目指す人へのメッセージをお願いします。
消防局には、消防隊や救急隊などの警防部門、火災予防や建物の査察などを行う予防部門、組織や職員の管理を行う総務部門、119番通報を受ける情報指令部門など様々な業務があり、そこで働く職員一人一人が「福岡市の安全を守る」という一つの目的のために日夜業務に励んでいます。
福岡市消防では、幅広い業務に携わることができるため、自分に合った分野で「福岡市の安全を守る」ことは、とてもやりがいのある仕事になると思います。
これまで経験した部署
- 平成27年度 福岡市消防学校(初任教育)
- 平成28年度 早良消防署 警防隊
- 平成29年度 早良消防署 指揮隊(調査係)
- 平成30年度 早良消防署 救助隊
- 令和元年度 博多消防署 救急隊
- 令和2~3年度 消防本部 救急課(日勤)
- 令和4年度 消防本部 救急課(救急隊)
- 令和5年度 西消防署 救急隊(救急救命九州研修所(救急救命士資格取得))




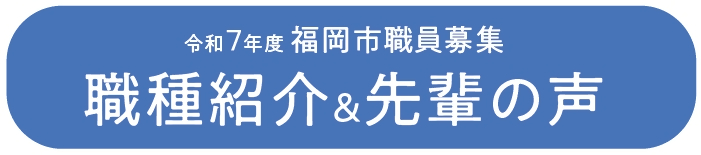

 東区
東区 博多区
博多区 中央区
中央区 南区
南区 城南区
城南区 早良区
早良区 西区
西区