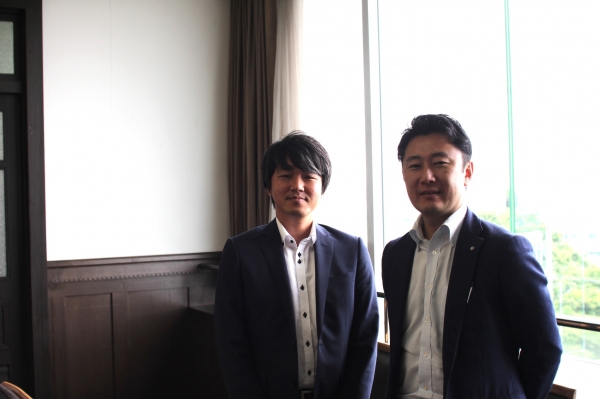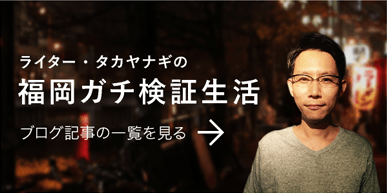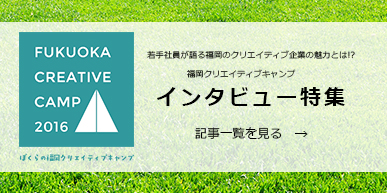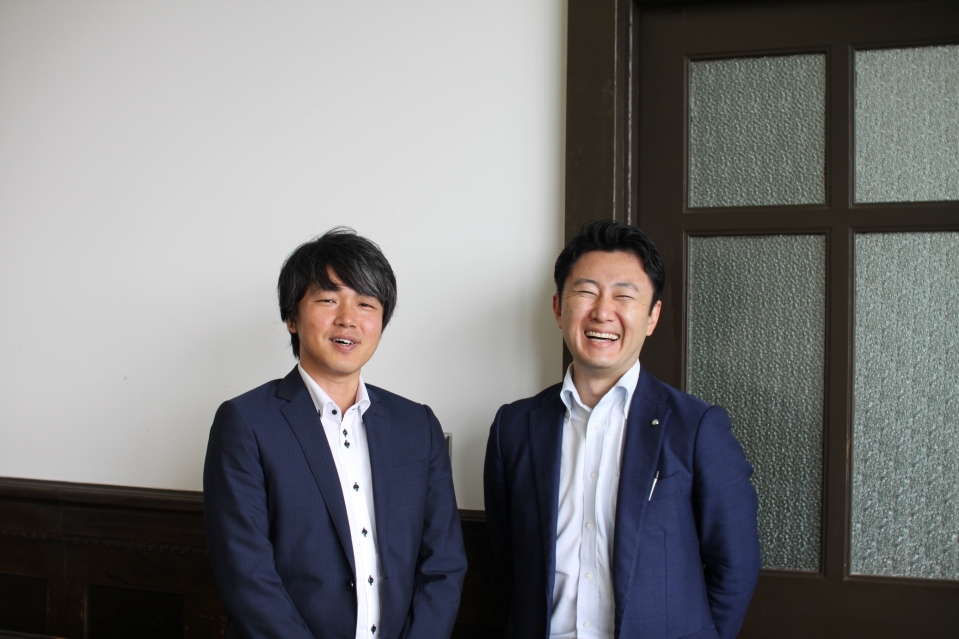
平成26(2014)年度よりスタートした、クリエイティブ人材のU/Iターン支援プロジェクト「福岡クリエイティブキャンプ(FCC)」。この2年間の活動で、着実に実績を上げてきました。平成27(2015)年度の、東京等から福岡市への移住・転職者は、前年度から倍増となる31名。FCCへの登録者数は159名、参加企業数は71社となり、どちらも前年比の約2倍。IT・クリエイティブ業界の人が、新たなチャレンジの地として福岡市を選択するという流れが加速していると言えそうです。
今年度もついに始動したFCC。今回は、そんなFCCを担当する福岡市企業誘致課の山下龍二郎さんと、福岡市の職員ながらクリエイティブコミュニティに深く関わり、現在は公益財団法人「福岡アジア都市研究所」に所属する中島賢一さんにインタビュー。福岡がいま求めている人材と、今後の展望についてお聞きしました。
――まずは過去2年間のFCCの活動を振り返り、感じたことを聞かせてください。
山下 FCCの前身となった、平成25(2013)年度のU/Iターン支援イベント「ぼくらの福岡移住計画2014 in Tokyo」から数えると3年が経ち、確実に成果が出てきていると思います。イベントの参加者は年々増え、参加意欲も高まっていると感じています。当初は業界に偏りがありましたが、WEB系に加えてゲーム系やデジタルコンテンツ系など、業種の幅も広がってきました。おかげさまで昨年は、クリエイター31名の移住・転職が決定し、(株)レベルファイブや空気(株)、(株)ヌーラボをはじめ、福岡を代表するクリエイティブ企業で活躍されています。
中島 FCCだけでなく、移住イベント全体が盛り上がっていますね。自分のライフスタイルを考えて、UターンやIターンというのは、選択肢のひとつとしてすでに当たり前になってきているんだと思います。
――なるほど。移住に興味があったり、実際に移住してくるのは、どんな方なんですか?
山下 これまでの実績でいうと、20代後半から30代前半の男性が多いですね。前職を経験した上で、実力も付き、年齢的にも働き盛りといえます。独身者も多いのですが、移住を機に結婚される方、「子育てを福岡で」とお考えになる既婚の方など多種多様なケースがあり、人生の転機を迎える決断をされているんだと思います。
――では、福岡の企業の側は、FCCの試みをどう捉えていますか?
山下 福岡の企業は、常に優秀なクリエイティブ人材を求めておられます。FCCにも多くの企業に参加していただいていますが、まだまだ満足いただけるサポートができていません。ただ、人材を求めるということは、企業が成長していることの証拠。昨年度からは、生活の質の高さやバランスの良さを考えて福岡に移り住みたいという人だけでなく、「この企業で働きたい」という積極的な理由で移住される方も増えてきました。企業の魅力が、福岡移住の呼び水になっているようです。
――福岡は、他の地域に比べても、移住しやすい土地なんでしょうか?
中島 IT・クリエイティブシーンについていえば、これだけコミュニティができあがって、今でも機能している地域は珍しいと思います。コミュニティが運営するイベントも数多くありますし、花見や忘年会などにも、ものすごい数の人が集まります。人を紹介し合う文化もありますし、東京から来ても新しい人と関わりやすい面はあると思いますよ。
――中島さんはそんなコミュニティの活動に、積極的に関わってますよね。福岡のIT・クリエイティブコミュニティが運営している年に1回のイベント「明星和楽」でも、主催者の一人に名を連ねてらっしゃいますが、そういう“民と官の垣根の低さ”も福岡ならではというか。
中島 「明星和楽」は、第一回(平成23年開催)から関わっていますし、最初は会場のゴミを集めて捨てる係をやってましたよ(笑)。それぐらい垣根が低いというのが福岡の特徴ですね。
――どうしてそこまでコミュニティ活動に熱心なんでしょう?
中島 まず単純に、コミュニティを動かしている彼らのことが、人間的に好きだし、話していて面白いこと。それに、行政の人間って、現状を把握しないまま政策を立案して、民間に押し付けるみたいなことを、してしまいがちなんですよ。それでは、政策と現状が乖離して、予算だけ消化する効果のない事業になってしまったりするんですよね。コミュニティにきちんと関わって、人間関係ができあがっていれば、いま民間でどんな動きがあって、何が必要とされていて、そのために行政に何ができるかを、把握できますから。
山下 そうですね。皆さん世代が近く、何よりも気さくな人が多いので相談しやすい。行政でサポートできることを考える際に、彼らの意見を聞くことはとても大切なんです。
――福岡市の課題として、クリエイティブコミュニティの中心人物の一人、ブランコ株式会社の山田ヤスヒロさんは、以前のインタビューで、「他の都市と差別化し、クリエイティブ都市・福岡としてのブランディングを成功させる必要がある」とおっしゃっていました。福岡がクリエイティブ都市としてのブランドを確立させるためには、現状何が足りていないと感じていますか?
中島 僕はいま、福岡アジア都市研究所に所属しているので、福岡がグローバル都市として発展するために何をすべきかは、そこでの研究テーマでもあります。わかってきたのは、「福岡は何の街?」という疑問にスッと答えられる必要があること。「福岡は住みやすい街」と評価されるのは大変喜ばしいことですが、日本に移住しようとする海外の人には、少々決め手に欠けるという意見もあります。もっと、キャラクターが立っていないといけない。そのために、象徴的な場所やイベントが必要だと思っています。東京だったらオタク文化に触れたければ秋葉原、スタートアップだったら渋谷というような、外の人を案内できるゾーンやイベントがあるといいんです。明星和楽は、そんな象徴的なイベントになれる可能性を持っているので、大きくなってほしいですね。
――では、おふたりが考える「いま福岡に足りない人材・求める人材」を教えてください。
山下 いまの福岡のクリエイティブコミュニティは、アラフォー世代が中心になっているように思います。これからは、20~30歳代の一世代、二世代若い人たちの力で、さらにシーンを盛り上げて欲しいと思います。FCCは、外から人を呼び込めるので、そこでの化学反応が、福岡に新しい刺激を与えてくれることを期待しています。
中島 クリエイティブや技術の高い人たちももちろん必要なのですが、外から移住してくる人には、仕事を作り出していけるプロデューサーが入ってきてほしいと思います。プロデューサー不足は以前からの課題ですし、プロデューサーが移住すれば、そのプロデューサーの周りに仕事も発生するので、及ぼす影響は大きいです。最近は、自社だけでは解決できない課題も多いので、まとめ上げる力のあるプロデューサーが求められてきています。特に、福岡ではプロデューサーとして大きな仕事を動かしてきた実績のある人が少ないので、自由に活躍できるチャンスがあります。ポテンシャルは高い都市なので、ぜひ福岡を舞台に積極的なチャレンジをしてほしいですね。
【関連リンク】
福岡クリエイティブキャンプ(FCC)2016インタビュー
https://www.city.fukuoka.lg.jp/hash/fcc/index