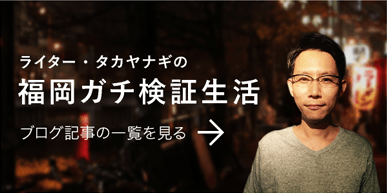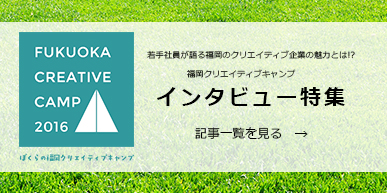さて今日は、福岡滞在中のメインイベントのひとつ、博多祇園山笠に行ってまいりました!
博多祇園山笠の起源については諸説あるようなのですが、一般的には、鎌倉時代(仁治2年:1241年)に博多で疫病が流行した際、聖一国師(しょういちこくし)というお坊さんが施餓鬼棚(せがきだな)に乗って祈祷水をまいたのが始まりと言われています。実に、800年近い歴史のあるお祭りなんですね。
毎年7月1日から7月15日にかけて開催される博多祇園山笠ですが、今回見に行ったのはそのクライマックス「追い山笠」。追い山笠とは、博多区にある櫛田神社(くしだじんじゃ)に七本の山笠を順次担ぎ込む行事です。スタートが午前4時59分とむちゃくちゃ早朝なので、今回はオールナイトでのぞみました。
午前3時半ごろに櫛田神社に向かうと、途中、櫛田入りの準備をするいくつかの山笠に遭遇しました。締め込みをした凛々しい博多の男達の姿に、こちらの気分も高揚してきます!
櫛田神社の前は、すでにこの人だかり。さすが期間中、300万人もの観客を集めるお祭りだけはあります。
テレビ局のクルーもたくさん取材にきていました。
では、櫛田神社の中に入ってみましょう!
境内はたくさんの屋台が出店されていて、完全にお祭り状態です。僕も気分を盛り上げるためにビールを購入して、一気に飲み干しました(笑)。
櫛田入りが行われる祭場も熱気がムンムン! いよいよ、祭りがはじまります!
午前4時59分、いよいよ一番山笠(一番最初に櫛田神社に入る山笠のこと)の櫛田入りです。緊張が高まる中、大太鼓の合図とともに今年の一番山笠である大黒流(だいこくながれ)が入ってきます! 流(ながれ)とは、山笠を担ぐグループの単位ことで、地区ごとに分かれています。大黒流以外に、東流(ひがしながれ)、中洲流(なかすながれ)、西流(にしながれ)、千代流(ちよながれ)、恵比須流(えびすながれ)、土居流(どいながれ)の七流と、最後に走る飾山笠と言われる八番山笠の上川端通(かみかわばたどおり)が参加します(※今年の櫛田入り順)。
清道旗(せいどうばた:櫛田神社内に立てられた、高さ約6.5mほどのポール。櫛田神社以外に2箇所立てられています)を廻ったところで、いったん止まります。一番山笠だけが唄うことを許されている「博多祝い唄」を大黒流が大合唱。気づくと、「祝いめでたーのー」とよくわからないまま、連られて僕も口にしていました(笑)。これが終わると、博多の男たちが再び山笠を担ぎ、博多の街に駆け出していきます。
櫛田入りした山笠は、写真のように清道旗をグルっと廻り、また櫛田神社を出て行きます。その間、わずか30秒ほど。追い山笠のコースは約5kmあります。その距離を約1トンある山笠が30分ほどで担がれるのです。男たちが懸命に担ぐ姿は本当に感動モノでした! 櫛田入りは西流が30秒78、全コースでは東流が28分39秒というタイムでそれぞれ1位を獲得しました。
休みの日には寺社仏閣を巡るなど日本文化好きを自認する僕ですが、“動く伝統”というものは今回はじめて見ました。その迫力は、本当に凄まじいものです。もしかしたら、国家戦略特区、創業特区に指定され、地方の中でも圧倒的な盛り上がりを見せる福岡の根底に流れるのはこうした祭り魂なのではないかと思った次第。
それでは、また明日!