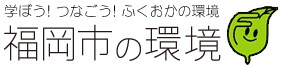1.外来生物法の概要
(外来生物法:特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律)
(1)目的
もともといなかった国や地域に、人間の活動によって持ち込まれた生きものを外来生物といいます。
外来生物法は「特定外来生物」による生態系、人の生命・身体、農林水産業への被害を防止することを目的としています。
<特定外来生物とは>
外来生物(海外起源)であって、生態系、人の生命・身体、農林水産業への被害を及ぼすもの、又は及ぼすおそれが
あるものの中から環境省が指定したもので、159種類が指定されています。
※環境省ホームページ「日本の外来種対策(特定外来生物等一覧)」をご覧ください。
(2)規制
特定外来生物に指定されたものについては、以下のようなことが原則禁止されます。
- 飼育、栽培、保管および運搬
- 輸入
- 野外へ放つ、植える及びまくこと など
(3)罰則
特定外来生物は、たとえば野外に放たれて定着してしまった場合、人の生命・身体、農林水産業、生態系にとても
大きな影響を与える可能性があるため、行為の内容によっては厳しい罰則が課せられます。
最高:個人の場合懲役3年以下もしくは300万円以下の罰金 / 法人の場合1億円以下の罰金
詳しくは環境省ホームページ「日本の外来種対策(罰則について)」をご覧ください。
2.福岡市で確認されている特定外来生物
(1)人への危害の可能性のある特定外来生物
以下の特定外来生物の疑いがある場合は、触らない、刺激しない、安全を確保してください!
被害にあった場合の救急医療機関については、救急医療・消防でご確認ください。
| 分類・名称 | 説明 |
|---|---|
クモ類 セアカゴケグモ |
貨物や資材にまぎれて持ち込まれたと考えられる。 メスには毒がある。 ※詳細は「セアカゴケグモ・ハイイロゴケグモにご注意ください!」をご覧ください。 |
クモ類 ハイイロゴケグモ |
貨物や資材にまぎれて持ち込まれたと考えられる。 メスには毒がある。 ※詳細は「セアカゴケグモ・ハイイロゴケグモにご注意ください!」をご覧ください。 写真提供:環境省 |
サソリ類 キョクトウサソリ科 |
貨物や資材にまぎれて持ち込まれたと考えられる。 尾端に毒針がある。 ※詳細は「特定外来生物の解説(環境省ホームページ)」をご覧ください。 |
昆虫類 ヒアリ |
貨物や資材にまぎれて持ち込まれたと考えられる。 腹部に毒針がある。 刺されると強い痛みを伴い、アレルギー症状がひどくなると重症化することがある。 ※詳細はヒアリ・アカカミアリについてをご覧ください。 写真提供:環境省 |
昆虫類 アカカミアリ |
貨物や資材にまぎれて持ち込まれたと考えられる。 腹部に毒針がある。 ヒアリと同様に刺されると強い痛みを伴い、アレルギー症状がひどくなると重症化することがある。 ※詳細はヒアリ・アカカミアリについてをご覧ください。 |
昆虫類 ツマアカスズメバチ |
大陸から交通機関や物資を介して侵入したと考えられている。 体は全体的に黒っぽく、腹部の先端がオレンジ色。大きさは女王バチ30mm、働きバチ20mm前後。 国内では長崎県対馬で定着が確認されている。 樹木の高い位置に営巣することが多い。主にミツバチなどの昆虫類を捕食するため、生態系や養蜂業への影響が懸念される。 在来のオオスズメバチ等と比較して、特に人体に関わる影響が大きいことはない。 参考 ・特定外来生物の解説(環境省ホームページ) ・ツマアカスズメバチ注意喚起チラシ(環境省) ・ツマアカスズメバチ識別参考シート (1,252kbyte) ・福岡市におけるツマアカスズメバチ生息状況調査(令和5年秋季調査)の結果について (649kbyte) 写真提供:環境省 |
(2)その他の特定外来生物
| 分類・名称 | 説明 |
|---|---|
哺乳類 アライグマ |
ペットとして飼育されていた個体が逃げ出したり捨てられたりして国内に定着し、各地で農業被害や生活被害が発生している。 ※詳細は「特定外来生物アライグマについて」をご覧ください。 写真提供:環境省 |
両生類 ウシガエル |
食用として各地で放逐され、国内に広く定着している。 大型できわめて捕食性が強く、口に入る大きさであればほとんどの動物がエサとなる。 |
鳥類 ソウシチョウ |
飼育が容易で、姿が美しく声がきれいなため、多数の個体が飼育された。 また、伝統的な化粧製品であるウグイスの糞粉の代替品として飼育されていた。 それらの個体が逸出したり大量に放たれたりして野生化したとされる。 本種と生息環境が類似するウグイスなどの鳥類や、捕食される小動物等への影響が懸念される。 写真提供:環境省 |
鳥類 ガビチョウ |
飼育個体の逃亡や故意の放出が野外への定着の主因である。 羽色は焦げ茶が主体で、比較的地味。大きく複雑な音色でよくさえずる。 今後個体数が増加すれば在来種を駆逐する恐れがある。 写真提供:環境省 |
魚類 カダヤシ |
ボウフラ(蚊の幼虫)退治のため各地に放流され、定着している。 各地でメダカと競合し、駆逐している。 メダカに似ているが尾ひれが丸く、シリビレの基部(下部後方にあるヒレ)が短い。  (メダカ:絶滅危惧種) 写真(カダヤシ)提供:福岡県保健環境研究所 |
魚類 ブルーギル |
釣り魚や観賞魚として持ち込まれ、各地の湖沼やため池、堀などに侵入・定着し、優占魚種の1種になっている。 雑食性で様々な生物を捕食し、生態系の影響や漁業被害の可能性も示唆されている。 |
魚類 オオクチバス |
コクチバスとあわせて通称ブラックバスと呼ばれる。 釣魚として人気種であり、各地で意図的な放流が行なわれてきた可能性も指摘されている。 一部の観賞魚店では販売もされていた。 オオクチバスが定着・急増した湖沼やため池では、捕食や競争により在来種にさまざまな影響を及ぼしている。 |
昆虫類 ハヤトゲフシアリ |
貨物や資材にまぎれて持ち込まれたと考えられる。 人への直接的な被害は無いが、アブラムシやカイガラムシを強く保護するため、増殖したこれらの害虫による農業被害が懸念される。 触角や脚が長く、在来種のアリでは見られないような素早さで移動する。 |
植物 オオキンケイギク |
観賞用や緑化のために持ち込まれた。 強靭なため、一度定着すると在来の野草を駆逐してしまう。 写真提供:環境省 |
植物 オオフサモ |
1920年頃にドイツ人が持参し、野生化した。 抽水植物(根は水底の土壌中にあり、茎や葉の一部が水面上で育成)であり、湖沼・河川・池・水路などの浅水中に群生する。大繁茂して水流を妨げたり、在来種と競合して駆逐するとされている。 写真提供:環境省 |
植物 ボタンウキクサ |
観賞魚の浮き草等として熱帯魚店、ペットショップ、園芸店、ホームセンターなどで広く流通・販売があった。 浮遊性の水草で、水面を覆い尽くし、水中の光や酸素不足から他の植物や魚介類への影響が指摘されている。水路の通水障害も引き起こす。 写真提供:環境省 |
植物 アレチウリ |
輸入大豆に種子が混入していたためとされる。近年は輸入飼育用の穀物に混入し、全国の飼料畑や河川敷で多くみられる。 全国で大繁茂し、河原の固有種との競合や駆逐のおそれがある。 ※福岡市では平成18年度の調査で一度発見されているが、平成23年度の調査では発見されず、定着状況は不明 写真提供:環境省 |
植物 ブラジルチドメグサ |
魚の飼育用や観賞用として輸入され、ペットショップやインターネット上で市販されていた。 泥に根を張って生活するとともに、水面を浮遊して分布を拡大する。 水面を覆い尽くすため、水中の光や酸素不足から他の植物や水生生物への影響のおそれが指摘されている。 |
植物 ナルトサワギク |
開花期はほぼ一年中であり成長段階の早い時期でも開花結実する。 急速に分布を拡大し、在来種と競合するおそれがある。 アルカロイドの一種であるセネシオニンやセネシオフィリンなどを含むため、家畜等の草食動物に対して有毒である。 |
植物 ナガエツルノゲイトウ |
鑑賞用水草として意図的に導入後、逸出・野生化したと考えられる。 茎切片による栄養繁殖が極めて旺盛で、日当たりのよい肥沃な条件下では急激に増殖することから、在来種との競合、水生動物の生息環境悪化が懸念される。 写真提供:福岡県 |
注)現地調査等により確認されたものを記載しています。これらの種すべてが定着しているとは限りません。
(3)条件付特定外来生物
| 分類・名称 | 説明 |
|---|---|
は虫類 アカミミガメ |
ペットとして輸入され、飼育されていた個体が野外に放たれることなどにより、全国に分布。 在来のカメ類と餌や日光浴場所等を巡って競合し、定着地域では在来のカメ類や水生植物、魚類、両生類、甲殻類等に影響を及ぼしていると考えられる。 レンコン畑のレンコンの新芽食害等の農作物被害の報告がある。 写真提供:環境省 |
甲殻類 アメリカザリガニ |
ウシガエルなどの餌として持ち込まれた個体が野生化。飼育個体の放出等もあり、全国に分布。 水草を切断したり、水生昆虫や魚類を捕食するなど生態系に大きな影響を与える。 写真提供:環境省 |
※条件付特定外来生物の規制等については、「令和5年6月1日よりアカミミガメ・アメリカザリガニの規制が始まりました!」でご確認ください。
3.福岡市未確認の特定外来生物(人への危害の可能性のあるもの)
以下の特定外来生物の疑いがある場合は、触らない、刺激しない、安全を確保してください!
被害にあった場合の救急医療機関については、救急医療・消防でご確認ください。
| 分類・名称 | 説明 |
|---|---|
は虫類 カミツキガメ |
以前はペットとして輸入されており、安価で販売されていた。大型に成長し攻撃的になるため、飼育個体が故意に放出され野生化したとされる。 甲羅の長さは最大約 50cm、重さは約34kg。長い首を伸ばし、素早い動きでかみつく。 参考 ・特定外来生物の解説(環境省ホームページ) ・カミツキガメ注意喚起チラシ(環境省中部地方環境事務所) 写真提供:環境省 |
昆虫類 クビアカツヤカミキリ

|
貨物や木製梱包材にまぎれて侵入したとされる。 体長は22~38mmで首は赤く体全体が光沢のある黒色。 サクラ、ウメ、カキ、モモ、ポプラなどの樹木に寄生して枯死の原因となり、落枝や倒木により人に危害が及ぶことがある。 幼虫が入り込んだ樹木の根本からはフラスと呼ばれる木屑とフンの混合物が大量に排出される。 参考 ・クビアカツヤカミキリ注意喚起チラシ(環境省) ・侵入生物データベース(国立環境研究所ホームページ) 写真提供:環境省 |
~生態系被害防止外来種リストについて~
生態系被害防止外来種リストとは、外来種について日本における侵略性を評価し、生態系等に被害を及ぼすおそれのある外来種をリスト化したものです。特定外来生物に指定されている生物を含め429種類が指定されています。「総合対策外来種(310種類)」「産業管理外来種(18種類)」「定着予防外来種(101種類)」のカテゴリに分類されています。特定外来生物以外の掲載種については外来生物法の規制はないものの、生態系に悪影響を及ぼすおそれがあるため、取り扱いには注意が必要です。
※「生態系被害防止外来種リスト(環境省ホームページ)」をご覧ください。
※生態系被害防止外来種リストの策定により「要注意外来生物リスト(環境省ホームページ)」は発展的に解消されました。
※福岡県の定着状況や被害実態を踏まえた「福岡県侵略的外来種リスト」はこちら。
4.外来生物の被害を予防するために
環境省では侵略的な外来生物による被害を未然に防ぐため、被害予防の3原則を提唱しています。
- 入れない
悪影響を及ぼすかもしれない外来生物をむやみに日本に入れない - 捨てない
飼っている外来生物を野外に捨てない - 拡げない
野外にすでにいる外来生物は、他地域に拡げない
<ペットを飼う前に>
駆除されている外来生物の中にはもともと人間の都合でペットとして連れて来られ、飼いきれなくなって捨てられたものもいます。ペットを飼い始めたら最後まで面倒を見ましょう。ペットも私たちと同じ命ある生きものです。ペットが一生を終えるその時まで責任を持って一緒に暮らしてあげて下さい。
ペットを飼う前には、以下のような点についてよく調べておきましょう。
- どのくらいの大きさになるのか
- どのくらい生きるのか
- 飼うのにどれくらい費用がかかるのか
- 気性が荒くなったりしないか など