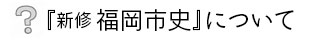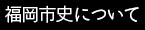
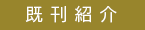
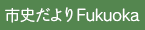
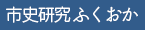
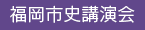
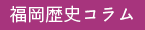
福岡市では、本市発展の指針とするため、また貴重な歴史資料の継承を目指して、福岡市史の編さん事業に着手し、平成22年から『新修 福岡市史』を刊行しています。
編さんの指針として、以下の5点を目標としています。
編さんの指針として、以下の5点を目標としています。
- 内容は、政治、経済、社会、文化、風俗、習慣、自然、環境などあらゆる分野を対象とし、地域・市民の視点に立って編さんする。
- 正確で格調高い内容を保ちながら、わかりやすい文章表現などにより広く市民が親しめる市史をめざす。
- 資(史)料の調査・収集にあたっては、本市に関連のあるものは日本国内だけでなく諸外国を含めて調査・収集することに努める。
- 収集・記録された資(史)料等は、市民の財産として保存・管理し、郷土の歴史研究および学術・文化などの振興に活用する。
- 市史の編さんおよび公開にあたっては、情報技術等の活用についても検討する。
※巻名をクリック(またはタップ)していただくと各巻の内容紹介ページに移動します。
- 2010年
- 資料編 中世1 市内所在文書
- 2010年
- 特別編 福の民 暮らしのなかに技がある
- 2011年
- 資料編 考古3 遺物からみた福岡の歴史
- 2011年
- 資料編 近世1 領主と藩政
- 2012年
- 資料編 近現代1 維新見聞記
- 2012年
- 民俗編一 春夏秋冬・起居往来
- 2013年
- 特別編 自然と遺跡からみた福岡の歴史
- 2013年
- 特別編 福岡城 築城から現代まで
- 2014年
- 資料編 中世2 市外所在文書
- 2014年
- 資料編 近世2 家臣とくらし
- 2015年
- 資料編 近現代2 近代都市福岡の始動
- 2015年
- 民俗編二 ひとと人々
- 2017年
- 特別編 活字メディアの時代
- 2018年
- 資料編 近世3 町と寺社
- 2021年
- 資料編 古代1 文献資料1
- 2021年
- ブックレット・シリーズ①
わたしたちの福岡市 歴史とくらし
- 2023年
- 民俗編三 夜
- 2024年
- 資料編 近現代3 モダン都市への変貌
- 2025年
- ブックレット・シリーズ③
ふくおか歴史探検隊
- (以下続刊/順不同)
- 資料編 古代2
- 資料編 中世3
- 資料編 近世4
- 資料編 近現代4
- 特別編 地図・絵図(仮)
※各編の構成及び刊行年次については、資料の収集、調査研究の進捗状況により計画的に見直しを行います。
『新修 福岡市史』編さん事業は、以下の組織で進めています。
- 福岡市史編集委員会
- 市史編さんに関する基本計画に基づく各種計画の作成、市史編さん事業に必要な資史料の調査・収集・整理・研究、『新修 福岡市史』の制作、市史編さんにかかる広報・普及活動などを行います(委員は令和7年4月現在)。
- 委員長 有馬 学 (九州大学名誉教授/近現代専門部会長)
- 副委員長 柴多 一雄 (長崎大学名誉教授/近世専門部会長)
- 委員 宮本 一夫 (九州大学名誉教授/考古専門部会長)
- 委員 重松 敏彦 (公益財団法人 古都大宰府保存協会/古代専門部会長)
- 委員 伊藤 幸司 (九州大学大学院教授/中世専門部会長)
- 委員 関 一敏 (九州大学名誉教授/民俗専門部会長)
- 各専門部会
-
福岡市史編集委員会には「考古」「古代」「中世」「近世」「近現代」「民俗」の6つの専門部会が設けられています。各学問分野の見地から、資史料の調査・収集、研究、原稿の執筆、校正などを行います(下の「部会紹介▼」をクリックすると各専門部会の紹介文が開きます)。
考古専門部会
- 大陸の窓口として栄えてきた福岡市は遺跡の宝庫でもある。弥生時代の到来を物語る板付遺跡、古墳時代の渡来人の痕跡を示す西新遺跡、古代の迎賓館である鴻臚館、中世都市の博多遺跡群、元の襲来を防いだ元寇防塁、近世の城跡である名島城や福岡城など数多くの重要な遺跡が存在している。これら各時代の遺跡は大陸との関係を示すとともに、日本の歴史を考える上でも重要な遺跡ばかりである。この度の市史編さん事業にあたって、考古専門部会では、このような遺跡を中心として、福岡の歴史を原始から近現代に至るまでビジュアルに叙述する予定である。しかも単なる一都市の歴史というのではなく、東アジア全体の歴史からみた位置付けができればと心がけている。また、このような遺跡は、福岡市の豊かな自然を反映し、あるいはその自然を人間が開発して作られている。福岡市の地形環境や自然環境の変化と人間の営みである遺跡や歴史との関係を、わかりやすくビジュアルに示した特別編を編集する予定である。さらに、資料編では貴重な遺跡や遺物資料を網羅的に示すとともに、埋もれた資料の集成や公開を目指したい。そこでは、遺跡から出土した動物の骨や炭化種実などの自然遺物を分析し、人々がどのようなものを食べて生活してきたのかといった、歴史記録には存在しない庶民の歴史を復元できればと願っている。
- 宮本 一夫(みやもと・かずお/九州大学大学院教授)
-
古代の博多(那津)は、一貫して高度な先進文化をとりいれた"アジアの窓口"として位置づけられます。ところが、平安前期の大宰府の役人は、博多を海外からヒト・モノが集まる「隣国輻輳」の港で、「警護武衛」の要だとも述べています。古代の福岡市は、変動する東アジア世界とそれに対応する国内事情が常に交差していたところだったのです。市史の編さんにあたっては、人びとがどんな生き抜く智恵と力を発揮したかを探るのが大きな課題になると思います。資料編は、海外をふくめて一世紀から十二世紀中頃まで、広い分野で収集する計画です。具体的には木簡などの出土文字史料や、『万葉集』などの文学作品、あるいは絵画、彫刻、工芸品なども調査の対象とします。また通史編では、主に五世紀から院政期におよぶ十一世紀までをとりあげます。特に鴻臚館跡や九州大学の移転先となった元岡・桑原遺跡など、貴重な古代遺跡については発掘調査の成果にかかわる史資料を見直して、遺跡の価値を高められたらと願っています。
そして専門部会は、多様な分野に取り組むために、広く県内外から実績のある方々に参加していただく対策をとりました。なお、現在の市域に所在・保管されている史資料は、この機会に是非関係機関および所有者の協力をえて、悉皆調査をしたいと考えていますので、特別編の古代の歴史地図作成とあわせて、皆様方のご協力をお願い致します。 - 田中 正日子(たなか・まさひこ/元第一経済大学教授)
-
中世の福岡市は、「東アジアの国際都市」博多を中核として、筥崎・今津といった周辺の港町を包摂し、政治・経済・流通のみならず文化や貿易の拠点都市として、力強い歩みと展開を歴史のうえに刻してきました。
より具体的にいうと、たとえば十五世紀から十六世紀にかけての室町・戦国時代には、博多はそのような重要さゆえに、様々な地域権力(大名)たちの争奪の対象となり、戦いが繰り広げられました。そうした合戦を本業とする武士たちの活躍が目立つ一方で、他のいろいろな階層の人々(農民、商人、職人、僧侶、宣教師など)もきちんと日々の生活を営んでいます。そうした人々の生活文化を明らかにするための史料は決して多く残存していませんが、中世都市博多を支えた人々の生活の様子をうかがうのは大変大事なことです。
そのためには、市内に所在する板碑(石造りの卒塔婆〈そとば〉)、寺社などに伝わる棟札(建物の由緒書き)、仏像の胎内銘(胎内に書かれた文字)、梵鐘銘(梵鐘に付された文字)などの金石・在銘資料、それに紀行文・和歌・連歌といった文芸資料、僧侶の語録・経典奥書・画像賛などの宗教関係資料など多種多様の資料に、往時の人々の生活の様子を丁寧にたどらねばなりません。
中世資料編では、そうした福岡市に関係する文書・記録資料、金石・在銘資料、文芸資料、宗教関係資料などを収録し、また中世通史編では、諸資料をふまえて、福岡市の中世のすがたを、大きな歴史の流れのなかで、平易で親しみやすく、しかも学問的な批判に耐えうる形で叙述します。
こうした遠大な世紀の文化事業を実りあるものにするためには、福岡市民をはじめとした皆様の暖かいご支援とご協力がどうしても必要です。もし、「うちにこんな資料があるよ」とか「どこそこにこういう資料があるよ」といったような情報があれば、是非、編さん室にお知らせ頂きたいと思います。すぐ調査させて頂きます。よろしくお願いいたします。
- 森 茂暁(もり・しげあき/福岡大学教授)
-
近世専門部会では、豊臣秀吉の九州平定にはじまる安土・桃山時代から江戸時代を中心とする、資料編および、通史編の刊行を計画しています。幕末・維新期については、近現代専門部会と協力して別途通史編を刊行する予定です。また、福岡市域の変化を地図や絵図によって明らかにする地図・絵図編や、福岡城の建設から現代の整備事業に至るまでの変遷を追う福岡城編などの特別編の刊行も計画しています。
福岡市の近世は、豊臣秀吉による博多の再興に始まります。その後、黒田長政によって博多の隣に城下町福岡が建設され、全国的にも珍しい双子都市が形成されます。近世専門部会では、この福岡・博多に住んでいた武士や町人の仕事や生活、福岡・博多と周辺の農村や漁村との交流、さらには藩領外との関係などにも注目しながら、これまでにないユニークな市史を目指します。
市史を編さんするには、非常に多くの資料を集めなければなりません。近世専門部会では、現在、市内の大学に所蔵されている資料の調査・収集を行っていますが、これからは図書館などの公共機関や個人所蔵の資料の調査・収集も行う予定です。また、これまでの県史や市町村史では古文書などの文献史料に比べて後回しにされがちであった、地図や肖像画などの絵図資料についても積極的に収集していきたいと考えています。
- 柴多 一雄(しばた・かずお/長崎大学名誉教授)
-
近現代専門部会は福岡市史の中で主に明治維新から現代までを担当します。現在の福岡市域を核としながら、福岡都市圏を構成する周辺市町村との関係にも留意し、あらゆる角度から地域の近代をとらえることをめざしています。
政治・行政や経済が重要なのはもちろんですが、地域の近代はそれだけではありません。近現代専門部会は、政治史や経済史だけでなく、文学、美術(絵画・写真・映画)、地理学、建築・都市計画等のさまざまな分野を横断した編集体制をとるべく、今後も多くの専門家の協力を得ていくつもりです。
もちろん近世専門部会や民俗専門部会など、関連の深い部会との共同作業も重要であり、これらの部会とは合同部会を開催しています。その中で、たとえば幕末維新期から明治十年頃までを通して叙述する通史編を、近世、近現代両専門部会が共同で編さんするといったプランも検討されています。
近現代専門部会は従来にないユニークな自治体史の編集をめざしていますが、当面の活動は地道な史料調査です。市の行政史料はもとより、市長経験者、市職員OB、議員経験者等およびその遺族の個人文書の調査を行い、また民俗専門部会と緊密に協力しつつ、一般市民を含むさまざまな地域・職種の人々のインタビューを行うなど、様々の調査を計画し、その一部はすでに実施されています。今後の展開にご注目いただければ幸いです。
- 有馬 学(ありま・まなぶ/福岡市博物館総館長・九州大学名誉教授)
-
銭湯が減ってしまった。理由はかんたんで、家風呂がふえたから。この二年間で箱崎界隈の五軒のうち二軒が店を閉めた。うち一軒は筥崎宮参道うらてにあって、放生会のときには深夜営業サービスをしていた。汗を流しに来ていた香具師連中は今年はどうしたのか。故郷を離れてひとり暮らしをする学生たちも世間の窓をひとつなくしたのではないか。理由はかんたんでも、その影響は大きい。
民俗専門部会が行うのは、われわれの暮らし方とその気風についてだ。これからの生き方を占うには、これまでの先人たちから学ぶことである。時代の変化のなかでしぶとく時代を超えるものを見分ける力が必要だ。そのために少し昔のこと、戦前から戦後、高度成長期をへてメディアが大きく変わった八十年代頃までの人生譚を中心に集めはじめている。世間の知恵は仕事がら、場所がら、人がらによってさまざまであり、おまけに当人にはあたりまえすぎて話すに価しないと思われるかもしれない。ところがどっこいさにあらず。都会と農村、本土と離島、サラリーマンから商人・職人・役人・遊び人たちの生き方の知恵を学ぶことは、時代が大きく変わりつつある今にしかできない大切なことなのだ。福岡はひとを魅了する町だが、その気風と誇りは市民ひとりひとりの底力に支えられている。この力の秘密をなんとか明らかにして、未来の福岡の糧にしたい。どうか、みなさんのご協力・ご支援をお願いいたします。
- 関 一敏(せき・かずとし/九州大学名誉教授)