CONTENTS(主な内容)
ハートフルフェスタ福岡2025開催案内
人権啓発フェスティバル「ハートフルフェスタ福岡」は、市民一人ひとりが人権問題を自分自身の問題として身近に感じ、考えてもらうきっかけをつくる人権啓発イベントです。今年で28回目を迎えます。
詳細については、ハートフルフェスタ福岡2025のページをご覧ください。

ココロンセンターだより100号記念特集 
平成12年に誕生した「ココロンセンターだより」も、ついに100号となりました。今回は、「100号記念」として、2つの特集を掲載します。
ココロンセンターだより100号記念に寄せて
福岡市人権啓発センターの開設と同時に発行が始まったココロンセンターだよりも今回で100号を迎えました。100号を記念して、福岡市人権啓発センターの歩みと役割を改めて振り返りつつ、これからの人権啓発について考える機会としたいと思います。
まずセンター設置の背景ですが、平成6年に国連で「人権教育のための国連の10年」の取組みを決定され、国内でも人権の尊重と擁護を図るための取組みが進む中、本市でも市民啓発を推進するための総合的な機能を持つ拠点設置の機運が起こり、平成8年11月に人権啓発センター検討委員会から提言書を受けました。
その提言には、センター設置の基本理念として、まず「市民の皆さまに開かれた場であること」、次に「時代とともに変化する多様なニーズに柔軟に対応できる組織であること」、そして「市民が利用しやすく親しみやすい場であること」、の3つが挙げられ、この考え方のもと、人権啓発センターの設置検討が進められました。
その後、平成10年には市役所内に一部署として人権啓発センターを設置、平成12年7月に博多区下川端町の博多リバレイン10階に移転し、一般公募により施設愛称を「ココロンセンター」と決定。それ以前からも実施してきた、ハートフルフェスタや人権尊重週間の啓発や講演会を行いつつ、図書スペースで人権に関する図書・ビデオの閲覧・貸出や、研修室、共用室を設け、登録した人権活動団体の活動の支援もできる施設として本格的に運営を開始しました。
平成27年には現在の中央区舞鶴のあいれふ8階へ移転し、人権に関する図書・DVDの閲覧・貸出、人権総合講座(ココロンセミナー)や人権尊重週間市民の集い等の講演会、ハートフルフェスタ、大学生を対象としたココロンキャンパス、人権啓発音源「こころのオルゴール」や人権啓発CMの作成、企業研修や講師派遣、人権に関する相談窓口など様々な取組みを行い、より市民に身近な拠点として機能を磨いています。
今後も、人権啓発センターは、様々な人権問題の解決に向けた人権啓発の拠点(コアセンター)として、市民に開かれた施設でありつづけるともに、新しい可能性も目指しながら、市民一人ひとりが人権について考える機会を増やしていきたいと考えます。そして、人権という普遍的文化の構築および人権の多様性を認め合う共生社会の実現を目指してまいります。
福岡市人権啓発センター所長 吉田 命
ココロンセンターだよりに見る25年間のあゆみ
平成12年に誕生した「ココロンセンターだより」も、ついに100号となりました。
ここで、これまでの福岡市人権啓発センターのあゆみを、人権に関するトピックを交えて振り返ります。
No.1 博多リバレインに移転・オープン

福岡市人権啓発センターは博多リバレインに平成12年7月1日に移転・オープンしました。それと同時に創刊されたのが「ココロンセンターだより」です。掲載画像は記念すべき第1号です。
ちなみに、コンテンツは、当センターの紹介、「ハートフルフェスタ福岡2000」の各研修案内、人権に関するトピックなどでした。
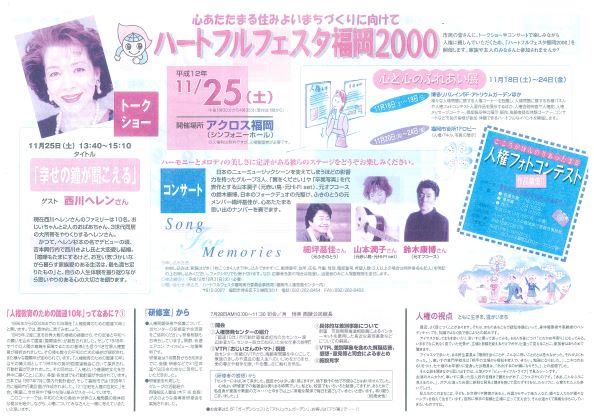
No.8 それから、月日は流れ…3年目を迎えました

オープン3年目を迎え、ココロンセンターだよりも8号になりました。
このころになると、蔵書やDVDも増え、利用者も増えてきました。
1面には、「オープン以来、女性、子ども、高齢者、同和問題など、様々な人権問題の解決を目指して活動する市民グループの会合をはじめ、PTAや校区人権尊重推進協議会などの研修の場として、また、夜9時まで開館している都心の小さな図書室として子どもからお年寄りまで、グループのみならず、個人で利用していただく方々も随分増加してきました。」とあります。
No.40 オープン10周年を迎えました

平成22年4月に発行された40号です。
1面には「みんなが集う誕生会―ハートフルフェスタ、初の野外大型企画に―」が掲載されています。
この年、ハートフルフェスタ福岡は、市役所ふれあい広場で開かれました。記事では、本センターの10年間の歩みが確認できます。
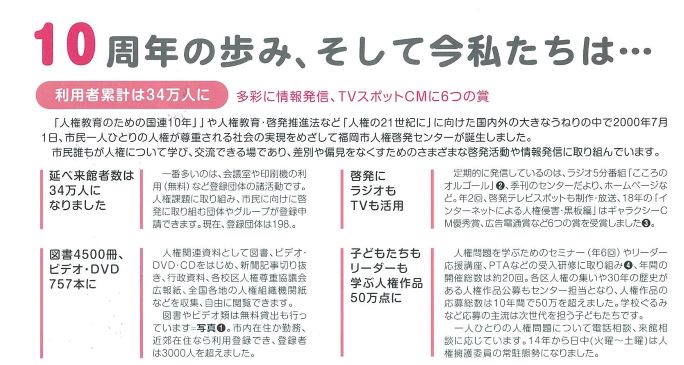
No.59 現在地に移転しました
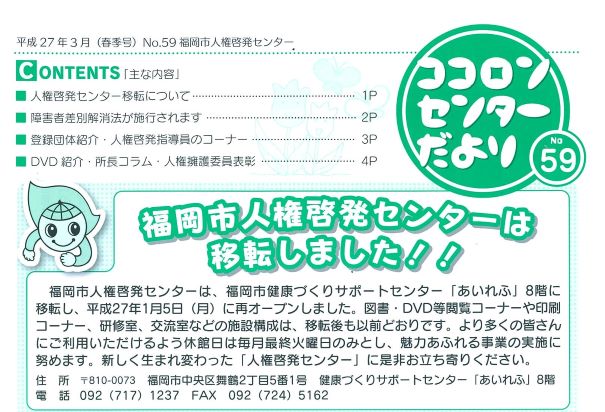
平成27年1月5日、福岡市人権啓発センターは、現在の福岡市健康づくりサポートセンター「あいれふ」8階に移転し、再オープンしました。
No.83 時は令和。新型コロナウィルス感染症大流行

令和2年2月、新型コロナウイルス感染症が流行したため、緊急事態宣言が発令。「3密」を避けるために、マスクの着用、移動の自粛などが求められました。町では店が休業に追い込まれる事態が発生。学校では休校措置が取られ、分散授業等が行われました。感染を避けるため、マスクの着用等、様々な制限が課され、研修会の開催は難しくなり、当センターへの派遣研修依頼も減少しました。
83号(令和3年3月発行)1面に「なくそう!コロナ差別」の文字が見えます。医療従事者への差別、感染者やその家族への差別も問題になりました。
また、このような社会の要請を受け、文部科学省のGIGAスクール構想が前倒しで実施になり、この年、福岡市でも小・中学校に1人1台端末が配備されました。オンライン授業の始まりです。
その後、令和4年度福岡市人権に関する市民意識調査では「尊重されていないと思う人権問題」の1位が「インターネットによる人権侵害」になりました。
No.99 新時代到来。WEB版に

99号。令和7年6月にアップされた、初のWEB版です。ココロンセミナーの紹介、図書DVD人気ランキング、指導員コラム、新刊図書DVD紹介などを掲載しました。
ご覧になっていない方は、ぜひご覧ください!
書籍等紹介・コラム
ココロンセンターライブラリー紹介 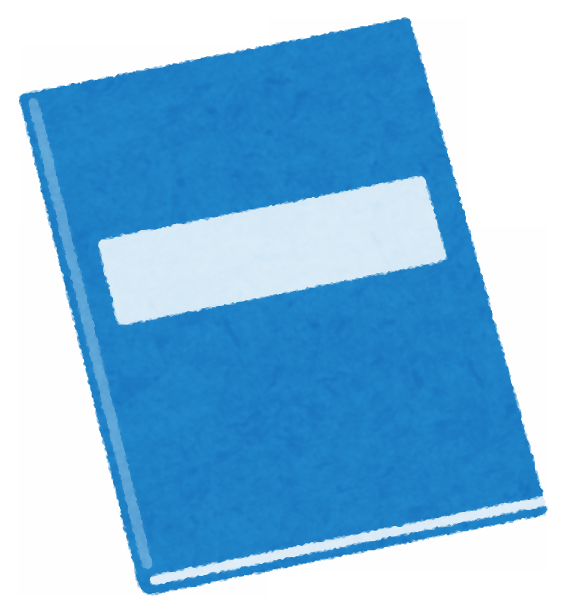

ココロンセンターでは、人権問題に関する書籍、まんが、絵本、DVDの貸出を行っています。ぜひ、ご利用ください。
マイクロアグレッションを吹っ飛ばせ ーやさしく学ぶ人権の話ー 【書籍】
出版年:2024年
出版社:高文研
著者:渡辺雅之
「マイクロアグレッション」。耳慣れない言葉ですが、人権侵害につながる言動として、最近、注目を集めています。
マイクロアグレッションとは「誰かを差別したり、傷つけたりする意図があるなしとは関係なく、対象になった人やグループを軽視したり侮辱するような敵対・中傷・否定のメッセージを含んでおり、それゆえに受け手の心にダメージを与える言動」(本書「はじめに」より引用」)です。
この本の表紙には、その具体例として「日本人よりも日本人らしいね。」「韓国人だから絶対キムチ好きだよね。」「男の子はなんだかんだいってさっぱりしてるよね。」などの吹き出しがあしらわれています。
筆者は、中学校の教員として22年間勤務されました。その間、いじめ問題に取り組まれた実践がテレビドラマ「3年B組金八先生」のモデルとしてそのまま取り上げられています。現在は大学教授として人権問題に関する講演なども行っておられます。
各分野の人権問題を豊富に取り上げ、具体的なエピソードを随所に盛り込むなど、筆者の幅広い知見がうかがわれます。また、「try」というワークが所々に入っており、内容について自分で確認しながら読み進めることができる点もお勧めの1冊です。【人権全般】
あなたのいる庭(35分)【DVD】
出版年:2024年
出版社:東映
企画:兵庫県・(公財)兵庫県人権啓発協会
阪神・淡路大震災で夫と幼い娘を亡くし、心を閉ざしたまま生きる主人公。しかし、近くにある児童養護施設で暮らす子どもたちと出会って、少しずつ癒やされていきます。
ある日、施設の職員から児童養護施設のことや、「ケアリーバー」(社会的養護のケアを離れたこどもや若者)について聞きます。その際、親しくなったもうすぐ18歳を迎える施設の子に、母親から虐待を受けて施設にいること、その母親から突然連絡があったことを明かされます。戸惑いながらも、楽しみにしていた母親との再会後、彼女が行方不明になったと施設から連絡が入り…
「寄り添うこと」の意味、自分ができることは何かを考えさせられるストーリーです。【子ども】
コラム
付けられなかったマタニティマーク
福岡市営地下鉄には、各車両の優先席近くにヘルプマーク、マタニティマーク利用推進の掲示がある。
2年ほど前のある日の七隈線車中。座っている私の前に若い女性が立たれた。バッグのマタニティマークに気付き、席を替わろうと立ち上がったら、隣の方も同時に立ち上がられた。2人分の座席が空き、妊婦さんは困ったようなうれしいような笑顔で座られた。
それからほどなく、娘から待望の妊娠の報告。空港線で通勤する娘に「マタニティマークを付けたら?」と提案してみた。すると「付けていたら、わざと押されたりするらしいよ。」との言葉。
妊娠初期に切迫流産を経験し、子を失った経験のある母としては、何としても娘を守りたい。そこで、ネットを検索。検索候補に「席を譲ることを強制するな。」、「子持ち様」等の文字が躍る。ある調査では妊婦の3割がマークを付けないと回答したとのこと。これでは、娘が躊躇するのも納得。妊娠は病気ではないが、切迫流産等のリスクを知らない人が多すぎるのでは?
その後、娘はお腹のふくらみが目立つ頃には、席も度々譲っていただき、職場では温かい配慮のもと、マタハラとは無縁のまま、無事に出産。育休に入った。最後までマタニティマークの出番はなかったという。
今年も、出生率の低下は記録を更新した。無事に生まれた初孫を抱きながら、安心して子を産み育てられる社会にするにはどうすれば…と考える今日この頃である。(淀川)
カラフルな「感覚」を呼び覚ませ!
昨年上映された映画「インサイド・ヘッド2」を観る機会があった。この映画は人間たちが抱く「感情」の世界を擬人化した作品だ。
思春期を迎えた主人公の感情には、「ヨロコビ」「カナシミ」「ムカムカ」「ビビリ」「イカリ」という感情に、「シンパイ」「ハズカシ」「イイナー」「ダリィ」という新たな感情が加わる。そして、不安や混乱など、大人ならではの複雑な感情に支配されながら成長していくというのである。
私は最近、歳を重ねるごとに感情を封印し、浅くなってきているように感じている。それは妥協の世界に入り込んでいるからではないだろうか。以前、感情は自分にとっての信号機のようなものだと聞いたことがある。危険を知らせる「赤」は不快、安全な「青」は快、「黄」は不安というように、感情は身を守ってくれるものであると。今の私は危険を回避するあまり、「メンドクサイ」に支配され、感情が浅くなっているのではないか。
この映画も擬人化された「感情たち」をその特性に合わせたカラーで表現している。心配は「オレンジ」、ハズカシは「ピンク」など、9つの感情が織りなし複雑な色合いの魅力的な主人公へと成長させていく。
映画を観ながら、懐かしい思春期の頃を思い出し、カラフルな感情を呼び覚ましたくなった。「メンドクサイ」を少し端に置き、カラフルな感情を復活させようと決意した。また、違った生きがいが生まれてきそうだ。(堀内)
