魅力発信 中央区
このページは、福岡市政だより中央区版において連載された、区の魅力を発信するコラム「魅力発信 中央区」の記事を掲載しています。名称や内容等は掲載時のものです。
なお、本記事を無断で転載・引用等することはご遠慮ください。
第15回 平尾山荘
平尾山荘(平尾五丁目)は、幕末の福岡藩士・野村貞貫(さだつら)と歌人として活躍した野村望東尼(ぼうとうに)が、俗世から離れて穏やかに過ごそうと暮らした場所です。
雨待の滝
夫婦は、和歌を詠んだり、桜や梅を植えるなどの庭作りをしたりして山荘での日々を楽しんでいました。
庭には小さな滝を作り、草庵の近くの池から水を引きますが、水量が足りず思うように水が流れ落ちなかったことから、この滝を「雨待の滝」と呼んでいました。
望東尼の山荘時代の和歌を収めている『向陵集』には、「雨待の滝」について詠んだ和歌があります。
「水はまだ流れいでねど君とわが心たぎつせ岩づたひする」(水はまだ流れ出ていないけれども、あなたと私の心の中では、すでに勢いのよい流れが岩を伝う様子が思い浮かんでいますよね)
この歌からは、完成した滝をイメージして、水が流れるのを待ちわびている望東尼の様子が伝わってきます。
現在の草庵は明治42(1909)年に復元されたもので、「雨待の滝」があった場所には、今では井戸が残されています。
草庵、資料を展示している管理棟は午前9時から午後5時まで見学できます(最終入場は午後4時30分)。
※12月29日~1月3日を除く。

「雨待の滝」の名残りの井戸

平尾山荘周辺地図
市政だより中央区版 令和7(2025)年9月15日号に掲載されました。


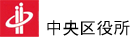
 東区
東区 博多区
博多区 中央区
中央区 南区
南区 城南区
城南区 早良区
早良区 西区
西区