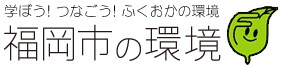ごみ処理施設(中間処理施設)
排ガス規制基準値の順守(ダイオキシン)について
工場からの排ガスについては、大気汚染防止法ほかによりSox、Nox等の排出量に規制基準値が設けられています。
ここではそのうち、ダイオキシンについて解説します。
どのようにして発生するの?
ダイオキシンとは、ものを燃やすと発生しやすい有機塩素化合物で、無色の固体でほとんど水には溶けません。炭素、酸素、水素、塩素が熱せられる過程で意図せずに発生してしまうため、ごみの燃焼で発生してしまいます。日本では、ダイオキシンの約9割がごみの焼却炉から発生しているといわれています。また、ダイオキシンは森林火災や火山活動でも発生するため、自然界にも存在しています。
安全性の評価は、どうやって行うの?
ダイオキシン類の安全性の評価では、耐容一日摂取量(TDI)を指標に用います。耐容一日摂取量とは、ダイオキシン類を人が生涯にわたって継続して摂取したとしても、健康に影響を及ぼすおそれのない一日あたりの摂取量です。人の体重1kgあたり4pgと定められています。実際に人体内に摂取した量と耐容一日摂取量を比較して、安全性の評価を行います。
通常の環境では、どのくらいのダイオキシンが存在するの?
ダイオキシン類は、ものを燃やすところから発生し、大気中に出ていきます。大気中の粒子などに付着したダイオキシン類は、地表に落ちてきたり川に落ちてきたりして土壌や水を汚染します。福岡市では毎年度、一般環境のダイオキシン類濃度を調査しています。
(調査結果についてはこちらをご参照ください)
ダイオキシンは危険な物質?
ダイオキシンは人に対して発ガン性があります。また、動物実験において妊娠中のダイオキシン摂取が胎児に奇形を起こすこともわかっています。しかし、日本の通常の環境でのダイオキシン汚染レベルでは、ダイオキシン類によりガンになることも奇形を生じることもないと考えられています。
ダイオキシン対策でどんなことをしてるの?
- 廃棄物処理法やダイオキシン類対策特別措置法により、一定規模以上の廃棄物焼却炉については、構造、維持管理、排出ガスの濃度基準等が設定されています。
- 福岡市では、平成8年度から排ガス中のダイオキシン濃度を測定しています。調査結果では、すべての工場でダイオキシン類対策特別措置法で定められた排出ガス基準をクリアしています。(調査結果についてはこちらをご参照ください)
- 焼却処理施設でのダイオキシン対策としては、焼却炉で約800度以上での良好な燃焼を行いダイオキシンの生成を抑制する、そして排ガス中のダイオキシンは、排ガスを200℃程度まで冷却してダイオキシンを固体化させてバグフィルタにて回収する等の対策を行っています。下図は、西部工場にて実施したダイオキシン対策例を模式的に示したものです。

余熱利用(ごみ発電)について
焼却炉でごみを燃焼させると、ガスが発生します。発生したガスは、この後に各種装置を通って無害化され工場外へ排出されますが、各種装置が耐えられるくらいまでガスの温度を下げなければなりません。工場では高温ガスを冷やすためにボイラを設置しています。ボイラでは、熱いガスを冷たい水の流れる配管に当ててガスを冷やしますが、このときに水はガスに温められて蒸気になります。この蒸気を、給湯や冷房に利用したり、タービン発電に利用して電気を起こして工場内や近隣の公共施設で使用したりします。さらに残った電気を電気事業者に売っています。