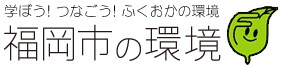現在位置:
福岡市ホーム
> の中のくらし・手続き > の中の環境・ごみ・リサイクル > の中の福岡市の環境 > の中の環境保全・自然環境 > の中の福岡市の環境影響評価 > の中の福岡市環境影響評価審査会 > の中の議事の要旨 平成24年7月31日
更新日:2012年9月11日
平成24年度第2回福岡市環境影響評価審査会
議事の要旨 平成24年7月31日
| 日時 | 平成24年7月31日(火曜日)午前10時00分~午後12時00分 |
|---|---|
| 場所 | 福岡国際ホール16階「志賀」 |
| 議題 | 1 若久団地団地再生(全面立替)事業環境影響評価準備書について 2 福岡市環境影響評価条例施行規則・技術指針の改正について 3 その他 |
| 出席者 | 浅野委員,小島委員,佐々木委員,薛委員,野上委員,萩島委員,平田委員, 藤本委員,柳委員,山田委員(50音順) |
| 会議資料 | 資料1 若久団地団地再生(全面立替)事業環境影響評価の手続き 資料2 準備書論点整理資料 資料3 意見概要及び見解書提出書 資料4 福岡市環境影響評価条例施行規則・技術指針の改正について(案) 参考資料1 方法書に係る環境保全の見地からの意見について(方法書市長意見) 参考資料2 若久団地団地再生(全面立替)事業環境影響評価準備書のあらまし 参考資料3 「本市における環境影響評価のあり方について」中間取りまとめ 参考資料4 福岡市環境影響評価審査会委員名簿 参考資料5 福岡市環境影響評価審査会規則 |
【議事概要】
議題1 若久団地団地再生(全面立替)事業環境影響評価準備書について
| 発言者 | 発言内容 |
|---|---|
| 会長 | 朝早くからお集まりいただいてありがとうございました。 本日は、まず若久団地の準備書の審査ということでございます。早速でありますが、準備書に記載されております事業概要と意見概要について事務局から説明いただきます |
| 事務局 | (説明及び事前送付された欠席委員の意見の読上げ) 【以下に意見原文を掲載】 ・もともと残されている自然環境が脆弱ですので、自然環境の面積を極力広く残すように、また可能な限りの多くの樹木の植栽等ができるように、計画段階だけでなく工事中においても工夫をお願いいたします。 事後調査ですが、生物は「スミレ」だけとなっています。しかし、生物・生態系に関する多くの予測結果は、「団地の存続により環境が改変されないため」あるいは「樹木の植栽が行なわれるため」、生息・生育に影響を及ぼすことは無いと評価されています。 評価の段階としては理解できます。しかし、存続環境あるいは樹木の植栽いずれも非常に脆弱であることから、事後本当に工事の影響が小さかったのか?樹木の植栽は機能しているのか等、対象種、対象地域および調査期間を絞ってでも、確認していただきたいと考えます。 ・準備書の内容に関して、全体として特に意見はありません。これでよろしいと思います。専門分野の生物(特に植物)につきましては、影響が出るのはどうやっても避けられないと思いますので、影響を出来る限り軽減するような工事と、工事後、保全措置の検証のために実施予定のモニタリングをきちんと実施することを強くお願いします。 ・準備書のP.45、4行目には「ふっ素は環境基準を超過している」ことが指摘されています。しかしながら、それがどういう原因によるものかについては言及されていません。平成18年福岡市地下水汚染対策委員会議事録(ネットで公開)などを引用して、花崗岩を帯水層とする裂罅水中に特有の自然由来ふっ素であることを明記しておく必要があります。 また、同ページの表2-1-23には水温、pHの値の記載がありません。水質の基本的な情報なので是非とも引用し記入してください。ちなみに、この時の水温は22.0度、pHは7.8でした。このことから、地下水としては温度が通常のものよりも4~5度も高いこと、pHも高く、弱アルカリ性を示すのでこれも普通の地下水ではないことを暗示しています。したがって、この地下水は近くの温泉(博多温泉)の影響を受けている可能性が読みとれます。 |
| 会長 | ただいま、事務局からご説明、事務局としてのチェックをした結果のコメントをいただきました。また3名の欠席委員からの意見の紹介がありましたが、これ以外にご質問等がありましたらお願いします。 |
| 委員 | 大気質についてお聞きします。157ページに、建設機械の稼働に伴う二酸化窒素の予測結果が出ていますが、バックグラウンドに対して結構大きな値ですね。例えば先工区No.2では2.5倍くらいの値になっている。次の159ページに、環境保全措置の検討ということで4項目出ていて、その下の2)のところに「環境保全措置は予測に反映しています」と書かれていますが、それぞれの措置によって、どれだけの低減効果があったかが、明確に書かれていないんですね。上の表6-1-1-1-22のところで建設機械配置の分散化を図るということだけなんです。 騒音については、200ページの表6-1-1-4-7の分散化の効果のところで、仮に寄せて集中させてやると騒音の場合は1デシベル高くなるのと、ちゃんと分散化の効果ということを評価しているのですが、二酸化窒素の場合はそういった評価が書かれておりません。もし騒音と同じように集中させた場合には、どれくらいの値になるのでしょうか。 |
| 事業者 | 大気質につきましては、154ページの建設機械の排出源区域図というところで書いております。一応これは各住棟を解体する部分で、この位置に配置している状況です。予測対象時期としては、解体から造成工事までを対象としていまして、解体工事の部分での配置をここで記載しています。解体工事の後に造成工事が入ってくる訳ですが、分散化という意味では、各住棟の解体で確実に1ユニットずつ置いて計算しております。スペースの問題がありますので、これ以上建設機械を置けません。特に解体工事に関しては詰め込んで2ユニット、3ユニットを入れていくというのは無理がございます。必要な部分に建設機械を配置しているのが現状でございます。 |
| 会長 | という説明を聞くと、ちょっと準備書の記述ぶりがあやしくなってきませんか。つまり保全措置でなくて、もともとそういうふうにやるのでしたら、何もそれは保全措置とはならない。説明がおかしくなると思います。もともとその機械しか入らないのですね。そうであれば、最初の計画どおりでしかない。それが、なぜ保全措置になるのですか。 この工事で出るNOxの数値はたいして大きくはないし、増えたからとい言っても、特に問題とすべき増え方ではないというくらいの量なので、私はそれ自体をあまり問題にする気はないと思っています。だから、そんなに厳しく保全措置によってどのくらい効果があるかを述べよという気もないのですが、今の説明は、いくら何でも説明になっていないのではないですか。そういう説明であるならば、評価書の段階で書き直してもらわなければいけない。 |
| 事業者 | ちょっと説明不足のところがあるので、ご説明いたします。 |
| 会長 | ちゃんと説明してください。 |
| 事業者 | 大気質につきましては1年間のピーク時を対象に予測をしております。解体工事に対しては各住棟を解体する部分に配置しているという状況なのですけれども、解体工事の後から造成工事が入ってきます。造成工事も予測対象としている訳でありまして、解体をひととおり終わった後で造成工事に入るということにしています。解体と造成を同時に進行していくと排出量的にはマックスなると思うのですが、そうではなく、解体工事を確実に終わらせた後で造成工事に入ることで、建設機械の分散化を図っているということを申し上げたいところです。 |
| 会長 | それは、建設機械の分散化ということよりも、工期の適正な調整を行うことによってピーク時を防ぐという方が適切な説明ということになりませんか。 工事期間中に、コンスタントに同じだけ建設機械からNOxが出るわけではないでしょう。その時々の工事の形態によってNOxの出方というのは違いますね。それを全部平均してこういう形で表記をしているという感じがするのですけど。 間違いなくちゃんと予測してあるのでしたら、この工期のこういう工事ではこれだけです、こういう工期はこれだけですという基礎資料があるはずですね。それを示してもらいましょう。計算の根拠はある訳ですよね。 |
| 事業者 | はい。ございます。 |
| 会長 | これじゃなくても構いませんから、見れば我々が納得できるように、それを出してください。 |
| 事業者 | 簡単なものは153ページの窒素酸化物の排出量のところで、解体工事と造成工事の建設機械ごとの年間排出量を出しています。 |
| 会長 | 153ページで分かるという訳ですね。 |
| 事業者 | そうですね。これで建設機械ごとの年間延べ台数を出していますので、年間排出量が出ています。 |
| 会長 | 私が疑問と思うのは、12か月間、全部これだけの機械がまるまる動くのですか。そうではないのでしょう。 |
| 事業者 | はい、そうです。 |
| 会長 | それぞれの工事の段階・段階でどういう機械が動くかということで違ってくるわけでしょう。 |
| 事業者 | はい、そうです。 |
| 会長 | 全部足し算して計算するってことは、安全側によっていて大きめの予測をしているという説明であれば、それはそれでいいですよ。むしろ、そういう説明をしていただいたほうがよっぽど安心できる。聞けば聞くほど、この計算はずいぶんずさんな感じがしますね。 まあ、いいでしょう。もともと全体としてそんなに大きな数字ではないので、環境基準を超えてどうこうという話ではない。しかし、信頼性を欠くという問題となってくる。もうちょっと、ちゃんと信頼できる説明をするようにしてください。 |
| 委員 | 騒音の場合と二酸化窒素の予測の建設機械の配置は同じものですよね。200ページの騒音は、検討結果の経緯を詳しく書いてあるのですね。ここを見れば、しっかり検討しているのが分かるのですが、一方で159ページは、同じものであるにもかかわらず、何らそういうふうに書かず、何か全部入れていますよという書き方をされています。 |
| 会長 | 逆にそうなると、大気の説明が正しいなら、騒音の書き方がおかしくなる。 |
| 委員 | ええ、だから、どっちかに統一する必要がある。 それともう一点、これに関してなんですが、4番目の措置の排出ガス対策型建設機械の採用ということで、排出量の低い機械を使いますと書いてあるのですが、予測値はこの機械を使った予測ではないのではないかと思いますが、いかがでしょうか。 |
| 会長 | 同じく私も思いますね。 保全措置を講じた結果が全部予測に反映されていると書いてあるから、おかしくなるんですね。要するに前と後両方比較しなければ、話はできないはずです。それなのに保全措置が予測に全部入っていると言われると、それは普通のアセスでは考えられないですね。保全措置がない場合、つまりウィズアウトの場合の予測がどうなっているのですか。通常ウィズアウトを出しておいて、それでこうなりますからこうなりますというのが、ノーマルではないですか。 それが保全措置は既に折り込み済みでございますということなのですね。それでよろしいのですか。 |
| 事業者 | 基本的に建設機械に関しましては、対策型建設機械を使うという前提がございます。規格にあった建設機械を実際使いますので、それに従って予測をしているというのが現状でございます。ですから対策型建設機械が入ってこない場合が想定できないという状況なので、実際に使う建設機械を今回の予測に用いているのが現状でございます。 |
| 委員 | 計算するのに用いた数値が153ページの表6-1-1-1-11にあります。エンジン排出係数原単位は、おそらく下の説明にある2007年度版から持ってきた数字だと思うのですが、今の御説明だと排出量低減した機械が何割入ってというふうになっていない。したがって今の説明はおかしいかと思います。 ちなみに159ページでは可能な範囲で採用すると書いてある。全ての機械が排出ガス対策型建設機械だとは書いていないのですね。この2007年版のエンジン排出係数原単位というのはおそらく普通の標準的な機械の原単位と思うので、これを用いて計算したのち、削減したものを何割使えば、排出量が何割減るという形で予測評価をすべきではないのかと思います。 |
| 会長 | 指摘されたことはご理解いただきましたか。 |
| 事業者 | ご指摘していただいたことはよく理解できます。 |
| 会長 | 評価書の段階では、もうちょっときちんとした表現に直してください。 予測をしてこうなるので、さらに対策を加えたらこうなりますというのが普通のやりかたなのだけど。最初から対策型のものを使うという前提であるならば、最初からそういう書き方しておいた方がいいと思います。 |
| 事業者 | 了解いたしました。 |
| 会長 | もともと環境基準を超えていないからいいと言っていただくのなら、それはそれで、よっぽどその方が分かりやすい。なまじ、何か対策をしているという点を強調しようとするからよけいおかしくなる。 つまり、これは何も特段の対策じゃない訳で、当たり前のことをやっているだけです。 当然、今は防音シートを付けなくて実施するというにはあり得ないことですから、たぶんその発想で同じように書いたのはないかと思われます。 全体に信頼性を損なうということになりますので、もう少し指摘されないように直されたほうがいいのではないかと思います。ただし、これは市長意見としてまでおおげさに書く気はありません。 |
| 委員 | 準備書の200ページの対策をやると、評価がこうなりましたというのが201ページにあります。201ページの右下の表6-1-1-4-10に4つほど対策した後の予測値の騒音が80から83となっています。みんなクリアしているからよろしいのじゃないかと言われれば、そうなんでしょうけれど、No.4の83は基準の85に近い値になってしまっている。 どうして、このNo.4だけが高くなるのかを少し説明をしていただきたいと思います。対策としては、期間の平準化と機械配置の分散化と低騒音機械を採用と仮囲いとなっています。仮囲いが全部あるかどうかはこれだけ見ても分からないのですけれども、差が出てくるのはどういう機械を使うのかということと、予測点までの距離とか位置関係、そういうものとの関連で値が変わってくるのだろうと思いますが。 それからもう一点は、機械配置の分散化っていうのが具体的にイメージしにくいのですよ。こういう工事でこんな機械を使うというのは必然的に決まって、その場所も1箇所になるべくならないように工事の目的に適うようにできるだけバラバラにというようなニュアンスは分かる訳ですが、具体的には対策としてどんなことをなさるのですか。 No.4がどうして高くなるのかと、分散化の意味について説明をお願いします。 |
| 事業者 | まず、なぜNo.4の予測値が高いのかというご質問についての回答ですが、それは198ページのほうを見ていただくと分かるんですが、No.4の地点に隣接する形で解体対象の住棟があるところで、敷地境界からかなり近いギリギリのところにあるというところで、どうしてもNo.4につきましては予測値が高くなる。距離的な問題で高くなるという状況があります。 あとは、解体工事につきましては、予測対象は解体工事を対象にやっているのですが、ユニットの構造物取り壊しが2ユニット近傍で動いた場合ということで予測をしております。これが3ユニット4ユニットと増えて入った場合は、もう少し騒音値が上がってくる可能性もあります。それを行った場合、寄せてユニットを固めて施工させた場合は、1dB程度高い値となってしまう。 ここに書いてございますとおり、必要な建設機械を入れていって行うと下げられるというところで、建設機械の分散化という表現でこれを記載しております。 |
| 委員 | 1つのユニットで解体工事をやるのに、1つのユニットでは使う機械は同じですよね。それが2ユニットというのは、近接したところに2つの機械を設置するという意味ですか。それが3とか4とかを2とかにできるのはどういう意味ですか。 |
| 事業者 | 1つの住棟を壊す時に左右両方から壊していく方法と、真ん中から壊していく方法というのがあるんですが、なるべく内側から壊していって、1ユニットで1棟を壊すというやり方で、効率的に解体を行うことで、建設ユニット数を減らしている、ということをこの予測でやっております。それを保全対策として、建設機械の分散化ということで、記載しております。 |
| 会長 | もう一回基本的なことをお尋ねしますけれど、1ユニットで仕事をするのですか、常に2つセットでないと仕事ができないのですか。 この書き方を見ると、ユニットっていうのは1つでちゃんと仕事をしてくれると理解で読んでいたのですけれどもどうですか。手順からいってできるだけ近いところを同時に壊していったほうが、残骸の処理も楽だし後の始末もいいから、そんなふうにやっていくのだろうと単純に考えていた訳です。 2ユニットが同時に動かないと、仕事にならないという訳ではないんですね。 |
| 事業者 | 1ユニットで十分解体工事はできます。 |
| 会長 | これはやっぱり手順を考えると、どうしても近傍のところを同時にやっていったほうがガラの搬出にしても何にしても始末がいいからそうなるだろう。 そうであれば、何も分散化などと大げさなことをいう話にならないのではないですか。 まったくこの予測は正直ベースで予測をしてあるのでしょう。このようにやります。だから、これもさっきと同じで保全措置と言っておられるけど、保全措置も何もあったもんじゃないわけで、要するにこのような手順でやったらこうなりますと言っているだけじゃないですか。 麗々しく保全措置といって、いかにも対策を特別に加えてやってるように言うからいけないのではないですか。 |
| 委員 | そうするとですね、85の基準ギリギリというのはちょっとまずいかと思うんです。少し安全を見てどこまで落とすかという目標値に対して、この地区だったら3ユニットまでは許される、ここは1ユニットで留めたいとか、そういう対策を明示していただくと、ちゃんと環境に配慮した工事計画を立てたということがわかるのですけど、そういうのが見えないのですね、これを見ていると。 近接しているところで、大きな音を排出してしまうのは明らかなことなので、近接しているところであれば、例えばできるだけ発生騒音を小さくするのに1ユニットでやるという措置をしました。少し離れているところだったら、工期短縮につながる訳ですから、長期間騒音をたて続けるよりは、ある程度の音を出しても一気に工事を済ます方が、それはトータルから言うと環境保全になる訳ですから、例えば3ユニット4ユニット出しても基準をある程度安全率を見ても守れていますというシナリオにして欲しいのです。 |
| 会長 | これは、コンサルタントの話ではなく、むしろ事業者の方の話です。基準はクリアできていますということでいいのかということなので。特に住宅近傍でやる場合は、より低減するのがいいのか、それとも工期を短くして影響のある期間を短くするのがいいのか、それはいずれかの選択の問題ですよね。それはどちらでもいいのですけれども、もっと明確にしておかなければならないと思います。 他に御意見等ございますか。 |
| 委員 | 23ページの切土というところですけれども、黄色い部分が切土ですが、切土をする目的というのはフラットにする目的なのか、あと建設しやすくするためいろいろあると思うんですが、現状で何でいけないのか。景観的にはある程度高低があったほうが、デザイン的にはいいものができることが多いんですけれども、その切土の目的とか、あとの状態がどうなるのか教えてください。 |
| 事業者 | 現状の若久団地というのは、結構起伏に富んでいます。擁壁があったり階段があったりしています。かなり難儀をして皆さん階段を上がられたりしています。ここで目指そうと思っているのが、極力段差がないなだらかな感じで造成をして住宅を建てようということで、どうしても土を削っていくというようなことが発生いたします。 それでこのように黄色が目立つ形になっていますけれども、これで段差解消を目指す作り方をしていきたいと思っています。 |
| 委員 | 切ったものをどこかに盛土することはしない。 |
| 事業者 | 中でバランスを取れるところは取っていこうと思っています。ですから、黄色いところを切って緑の部分に持って行くとか、そういう方策を採りたいと思ってはいます。 |
| 委員 | これでは表現されてはいないのですね。 |
| 会長 | 工程が先工区と後工区があって、一遍にやるのでしたら完全にバランスを取ることができるのだけれども、時期がずれる。そうするとトータルでは差し引き計算そんなにずれないんだけど、それぞれの工期ごとでいくと出入りが出てくるということらしいです。 |
| 委員 | やはり、残土が出ますよね。それを極力減らすことは考えていらっしゃるのですね。 |
| 事業者 | この図面の上の方になるんですけれど、先行区のほうはどうしても土を仮置きする所がございません。それで、多少は場外の方に残土を搬出すると思っています。後工区、図面の右側半分については、バランスを取っていこうと思っています。 |
| 委員 | 241ページの表に二酸化炭素の対象とするかどうかで、樹木の伐採で量が確定していないため対象としていませんと書いてあります。先ほどの切土とか盛土を見ると、エリアはとりあえず綺麗に更地になるんですよね。そうすると伐採量はカウントできるじゃないかなと思うんです。これは、そうではなくて、移植量が分かってないという意味でしょうか。 |
| 事業者 | 御指摘のように23ページの絵を見ると、かなり切ると、切るということは樹木が宙に浮くことになります。かなり立派な木もありますので、それにつきましては事業に入る前に極力、駐車場など地べたがあるところがございますので、そういうところに仮置きしようと思っています。全ての木を残すという訳にもいきませんので、現在造園部隊のほうで、居住者の皆さんの思い入れのある木とか、台風時期にも耐えられるような健康な木とか、そういった木を選定しているところでございます。まだ設計が間に合ってはいませんけども、そういう木については極力活かすということです。それをキーワードにこの団地は建替をやっていこうと思っているところです。そこで今の241ページの書きぶりになっています。 |
| 会長 | あそこにある木くらいで何トンベースの吸収量という話になりっこないので、むしろ言ってる方がかわいそうな気がします。あくまでも吸収源としての減少として考えると、ここはプラスマイナスゼロみたいなとこがあって、植えてもらえるほうが古い木より本当はいいんで、どんどん植えてくださって1本切ったら3本植えてもらったらもっといいですよね。 |
| 委員 | カウントしても問題はないんじゃないかというくらいです。移植できるエリアを考えると、大半はなくなると考えていいんですよね。カウントしてもそれほど問題ない、書いてもいいんじゃないかなと思ったくらいです。 |
| 事業者 | 地元の人も勉強会を始めておられまして、建てて40年以上経つ団地なもので、次源田池の周辺とかに鬱蒼とした森がございます。皆さんそれを気にされています。極力残す方向でいって、どうしても伐採しないといけないのは、会長もお話しされたように新植で対応しようと考えています。立派なサクラも結構ございます。ただ、もう腐って台風でどうなるのかわからない木も結構ございます。そういうところは、新しい木を植えて対応することで努力していきたいと思っています。 |
| 会長 | 他に。 |
| 委員 | 質問ではなくて意見なのですけれども、65ページの社会的状況は人口とか産業とか工業、農業になっていますが、社会的状況で将来の問題になるのは少子高齢化ですよね。いかに良好な都市型住宅を造るというようなことが事業の目的でもあると明確に出されていますので、人口構造的にどういう現状になっていて、将来どうなっていくのかという将来予測のところまで、2035年くらいまでは出してもらった方がいいと思います。高齢化だけではなくて少子化も将来どのように進んでいくのかが、福岡市と各校区まで全部出ていますので、校区の将来予測まで出して欲しいと思います。 それに、この産業というのは、あまり意味がないというか、今から就業人口というのは減っていく訳なんで、就業人口というのが減っていく中で今後住宅というのはどうあるのかっていうことが分かるような社会的状況にした方が分かると思います。 平成31年に工事が終わるということなので、高齢化率を含めて、せめて2035年くらいまでの社会的状況が分かるものに変えたほうがいいのかなと考えています。 もう一つは、486ページですけれども、いわゆる人と環境との関わりです。今こんな気候になってきています。484ページの将来図を見て欲しいのですけれども、真夏の時期に日陰もないようなこんな道は歩けないですよ。 あっという間に洪水になる雨量の中でどこに水が吐けていくのかとか、道路幅が広くなれば、車椅子の人たちも歩けるようになるのですよね。それにはやっぱり日陰が必要になります。今、団地を見ても、日陰がないので高齢者の方たちが歩けないという状況があって、それをいかに造っていくのか。反対に、樹木が40年経ってものすごい大木になって、歩道の木が邪魔になって、木を伐採しているところもあるんです。 そういうことが、今、結果的にあっているので、新しい日陰を造るとか、たまった水をどうやって逃がすのか、具体的な提案がほしい。住宅地としての環境が確保されると予測されますと書いてあるのですけれども、まちかど広場とか、歩道とか、安易に使い過ぎていて、まちかど広場とはどんなものなのか、人との関わりのある道路とか、人が休める広場というものがどんなものなのかを、もうちょっと優しく考えて欲しいなと思います。 |
| 会長 | 他にございますか。 |
| 委員 | 環境保全とは違うかも分かりませんけれども、災害ということでひとつ気になったのがございますので、ご質問させていただきたいと思います。16、17ページの排水計画でございますけれども、この時の流出量を計算するにあたっての雨量はどういう雨量を使われたのか、それをまず1つ教えてください。将来予測も同じ流量を使われたかどうかを教えていただきたいと思います。 |
| 会長 | おそらく、都市計画側の数字を使っているのじゃないのかと思うのですが。 |
| 事業者 | 20ページを開いて頂ければと思います。ここに書いてある図面の右下の方、三宅3号公園が薄く書かれていると思います。こちらの方で、大雨が降ると水につかるんだよという話が地元からございました。何を考えたかというと、こちらに流す水を減らそうということで、福岡市さんと去年の暮れからずっと協議をして参りました。実は、降水量につきましては、福岡市さんのお持ちの計算式がございます。それで雨量を出しているということでございます。 もう一つ従前と従後ということですが、今はかなり芝地とか草地が結構ございます。それと建替後の芝地とか草地の面積を図面に書いて調べましたら、建替後のほうが水が余計に地区外に流れるというということが分かりました。今の流出係数が0.48、48%が流れていくのが、建替後には0.6、60%、100降った雨が60外に流れてしまいます。それで、0.48と0.6の差、建替によって増える分については地下貯留で溜めようということで、今福岡市さんと協議をしているところです。 それと、この絵を見ると水も吐けないのではないかというような御指摘がありましたけれども、歩道については、透水性舗装を設けまして、地下水のかん養と歩行し易いような形で、福岡市さんがよくされているレンガ色みたいな舗装をして、雨水が地中にしみこんでいくという方策を今考えているところでございます。 |
| 会長 | 都市計画のほうの数値を使われているとなるとしょうがないのかなと思うんですけれども。そもそも降水の形態がまったく変わってきていることをどう反映させるかという問題なんですね。なかなかそうはいうものの数字を的確に把握できるかという話があります。 |
| 委員 | いま、会長のいわれたとおりなのですけれども、どういう数字を取るかというのは非常に難しいです。計算式があるということであれば、その式で妥当なのかどうかを検証はぜひともやりながら進めていただきたい。ここ10年単位で平均を取るとやはり、降雨量はものすごいですね。その辺をやはり考慮しないと、せっかく造ったが容量が足りなくて、それからさらに溢れてしまったということになりかねないので、十分注意してやっていただければと思います。 |
| 会長 | 少し長期の予測をしてみると、たぶん24時間雨量ではあまり変わらない、短時間にものすごく降る、いままでよりも降雨の時間が短くなる。トータルで24時間雨量でみると、あまり変わらない。問題は24時間雨量ということで想定している防災の施策が合理的なのかということが問題になっているというのが専門家のお話ですね。 今この段階で、直ちに事業者にお願いするのは難しいかも知れませんが、ご指摘があったことは留意していただきたいと思います。 |
| 委員 | 欠席委員の指摘といいますか御意見があったことで、地下水が1箇所調査をされていて、そこでふっ素が超過をしていることなんですけれども、準備書の77ページで地下水の利用で触れられてはいないのですが、災害時に水道が供給されない時に、そこの地区で例えば出る地下水とか、利用できる地下水があるのは、防災の観点からも重要な1つの側面ではないかと思うんです。1箇所三宅地区の地下水の調査で、それがふっ素が超過していて飲めない水であるというときに、できたらこの新しく建て直される団地の中で飲用もできるような地下水をどこかに確保できないものかなと思います。77ページを見ると硝酸性窒素が高いので、地質由来の部分だろうから無理な側面もあるんではないかと思うんですけれど、飲用としての地下水というのを見直され織り込まれてもてもいいのかなと思いました。 |
| 会長 | 地下水の調査は、市がやった環境調査がそのまま使われているだけです。事業者が調査した訳ではありません。 欠席委員のご指摘は自然由来であることをはっきりさせろというご指摘だったと思います。それは、特段意見として書くんじゃなくで、事業者の方で欠席委員のご指摘に沿って加筆されたらいい思います。 |
| 委員 | 動物のところと生態系の生息保全のところは、直接失われるものがないこともあって、影響についての書き方も措置についての書き方も適切だと思います。一時的に環境が低下するけれども、回復するだろうというような書き方になっており、適切だと思います。 ただ、植物のところだけスミレというのが、直接これはなくなりますということでした。この予測結果と保全措置というところの前後の関係が、先ほどの措置を織り込んで予測したような書き方はおかしいのではないかというお話がありましたが、そのとおりと思います。343ページにスミレが団地の存在によって影響を受けることになる、ただ、343ページの予測の中に移植を実施する計画となっていることから、その影響は極めて小さいと予測されますと書いてあります。措置として移植をしますといっているのはその次の工程にいく訳でして、こういう書き方は意味があるのかどうか知りませんけど、予測としては最後に言うのではなくて、何らかの措置をしなければ消失するというのが343ページのことであってもよさそうな気がしています。その後でこういうものだと評価すればよいと思います。 344ページの保全措置については、スミレの措置については極めて適切な書き方であると思います。それが着いている芝ごと持って行って適切な環境におけば、それは生き延びることは確かですけれども、スミレというのは種子で、相当広がります。できれば、危険分散として種子を採取して、できあがった場所にばらまくということもやってもいいのかなと思っています。 |
| 会長 | ありがとうございました。貴重なアドバイスだろうと思います。 書き方はさっきから一貫して問題になっているので、評価書の段階で書き方は考えてもらいましょう。予測と保全措置を一緒にしないでもらいたい。 |
| 委員 | 若久川にウナギやアユが上ってきている。びっくりいたしました。三面張りの河川に回遊魚が上ってきている。住民の方の今後のまちづくりを考えますと、かなり勇気が出てくる魚種だと思います。住民の方、ご存じなのでしょうか。 |
| 事務局 | 地元の方は、たぶんご存じないかも知れません。 |
| 委員 | それでしたら、ぜひ事後調査をきちっとされて、この川にはウナギも上ってきている、アユも上ってきていると、ぜひ宣伝されたほうがいいと思います。 |
| 会長 | とたんに捕りにいく人が出てくる。 |
| 委員 | 工事中のこれらの魚種を守る方法としまして、雨水流出抑制装置と書かれていますけれども、これはどういう装置でしょうか。 |
| 会長 | さっき説明されたように、雨水の超過分について調整池みたいなものを作って、地下貯留する装置ですね。それで流量調整をします。 |
| 委員 | あともう一つ、アユなんかがおそらく川の三面張りのどっかの岩石についている付着珪藻があって、その調査があるんですけど、それを食べていると思うんですけれど、それの最大の敵であるSS、特に軽い粒子が最大の強敵なのですけど、それに対しては椰子などのフィルターを付けて対策をすると書かれているんですけれど、これらの効果については、もし他に実際に使用されてその時の効果についてデータをお持ちでしたら教えてください。 |
| 会長 | 準備書では効果が十分あるという書き方になっています。たぶんURはあちこちで経験済みだから、経験に基づいて書かれていると思って読んだのですが。 |
| 事業者 | 委員が懸念されていることは、もちろん私どもも懸念しています。特に解体すると地べたが露わになりますので、そういうときにゲリラ豪雨とかが来ると、そのまま泥水が川に流れてしまいます。それに、かなり土を削るものですから、解体後の造成の時も同じような懸念があります。 そういうときに対処するように、泥水を流さないように敷地のまわりに溝を掘って、その流末には板で囲んだ池を造ります。 準備書に書かれているように、椰子の繊維で蓋をして、そこを通過する泥水の泥はなるべく中に置いて、水の分だけ外に流すという装置を付けます。これは、ここに限らず今までいろんな建替をやってきましたけれども、いろんな現場でやっております。かなり効果はあると思っています。 |
| 委員 | 沈砂地を造って、それに椰子のフィルターを付けるというのは、私は初めて伺いましたので、効果はいかほどなのかということを知りたかったので、これもパーセンテージとかで表せられると説得力があると思います。 |
| 会長 | よろしいですか。 この他に、市民意見の中にアスベストのことが出ています。 調査したけどありませんということなので、それはそれでいいのですが、万一発見後で分かった場合は、法律に基づいてちゃんと対策をたてますという書き方になっていますけれども、これはできれば、住民の方々が不安を感じないよう配慮することが必要だと思いますから、もし万一出てきたという場合には隠さず、それは町内会を通じてこういう対策をかけます。これで全く問題はなくなりますということをきちんと言わないと、かえって混乱がおこってしまうと思われます。いま、大防法改正をやろうかとしています。恐らくかなり大きく報道される可能性がありますし、他の事例でも、ちゃんと入っていますということを強調して、お互いに話し合って、対策をこういってやりますというのが、はるかにましだという話はききました。万一出てきた場合は市民意見にあるようにちゃんと住民対策を講じて公表することはやっていただいた方がいいと思います。たぶん大丈夫だとは思うのですけど。 他に何かございますか。 |
| 委員 | 今回の計画は、団地内にある高木といいますか大径木というか実際活かせそうなものは移植して利用する計画ですよね。この団地内の樹林が、たとえば生態系の上であるいは生物生息環境として特に大事だというようなことが指摘されていませんから、準備書はこれはこれでよいのかも知れません。しかし、URの工事はきっちり調査されて使えるものは活かすということをしっかりやってこられたと思います。今の緑地面積はこれだけ、工事後の緑地面積はこうなるという面積で十分だという説明ですけれども、たとえて言えば、今現在何センチ以上の高木が何本あってそのうち使えるのは何本、そのうち何本移植する、また、後の緑化においても、これぐらいの大きさの木を何本植える、結果的に今の高木なり大径木なりが、工事直後においてもあまり減った状況にはなりませんというような約束、面積の約束と同時にそれくらいの簡単な約束はできるのでないかと思うので、今後そういうことを考えてくださればと思いました。 |
| 会長 | わかりました。 事業計画がまだ詳細が決まらない段階でアセスが行われる訳でもあるわけですが、どの段階でそれを記述していただくのかということには問題があるとしても、定量的に知らせてほしいという意見には留意していただきたいと思います。評価書までにもし間に合うようであったら、やっていただきたいし、その後であればその後でもいいと思います。 それから事後調査について、欠席委員からの意見が別途出ていまして、スミレだけの事後調査でいいのかという話、これも気をつけていただいた方がいいかも知れません。 それでは他に、特にご指摘はございませんようでしたら、ただ今まで出されたご意見の中で、特に市長意見として取りあげておかないといけないものは何かということについては、私の方で検討させていただきたいと思います。 とりわけ、保全措置のあり方についてはもう少しきめ細かく考えてほしいというようなあたりですね。どういう方法をとるかは、それは事業者がお考えになることですが、いろいろある。これでやらなきゃいけない、決め打ちでこうしろと言う気はないんですけど、まだまだ工夫の余地がありそうだというご指摘があった訳です。 それから、アスベストについては、書くかどうかは別ですけど、ぜひ検討しておいていただきたいと思います。 他の御意見の中で、これは是非意見に入れておいて欲しいというものがありますでしょうか。 後でもう一回議事録をよく精査して提示させていただきたいと思います。 いつものとおりなのですが、この点については、私の方に一任していただけますでしょうか。 整理をして改めて委員のほうにこういう市長意見にしますということについては、ご了解を求めることにいたします。 |
| 委員 | (一同異議なし) |
| 会長 | それでは、ご了解いただけましたので、市長意見については市長に対する意見をまとめさせていただきます。 それでは、若久団地に対する審査は以上で終わりたいと思います。この点についての今後の予定について事務局から説明をお願いします。 |
| 事務局 | どうも、ご審議ありがとうございました。本日いただきましたご意見、先ほど会長からお話がありましたように、こちらの方で議事録と内容の整理を行いまして、再度皆さまに見ていただくようにしたいと思います。最終的に審査会の意見をいただきまして、それをもとに福岡市長の意見を作成して、事業者あて提出にしたいと思います。 |
| 会長 | それでは、この件については以上で終わりたいと思います。 どうも、事業者の皆さん、関係者の皆さん、長時間ありがとうございました。 どうぞ、よろしくお願いします。 |
議題2 福岡市環境影響評価条例施行規則・技術指針の改正について
| 発言者 | 発言内容 |
|---|---|
| 会長 | それでは続いて議題(2)でありますが、環境影響評価条例施行規則・技術指針の改正について事務局から説明いただきます。 |
| 事務局 | (説明) |
| 会長 | それではただいま事務局から説明がありましたことについて、何かご質問はございましょうか。 審議会の委員をかねておられる方は説明を聞いておられると思いますが、国の法律が変わることに伴って条例を変えるということで検討しております。条例が変わった以上は細かい技術的なことについても変えないといけませんので、それは当審査会で検討してほしいという趣旨でございます。それは全員でするのは大変なので下請けに出そうということです。 部会を設置することができるという規定がありますから、部会を設置し、部会委員については私が指名すればいいということになっています。加えて専門調査員として古山先生に加わっていただくことを考えています。部会長としては藤本委員にお願いしたいと考えておりますがいかがでしょうか。 |
| 委員 | (一同異議なし) |
| 会長 | ではご異議ないようですので、このように進めさせていただきます。 |
| 委員 | 部会で検討していく事項について、意見があります。 私の理解では、SEAに関しては、事業の計画段階からアセスをしていくということで、事業の複数案、それもなにもしないという選択肢も含めた複数案について検討するという方向で部会で議論されるのでしょうか。法律ではそこまで規定していないようですが。 |
| 会長 | 複数案を検討することが原則であるということははっきりしています。ただ、ゼロオプションという点は、環境省でガイドラインを作ったときに議論したのですが、ゼロオプションを検討することが意義ある場合はやります。つまりやらなかったらもっと悪くなるという場合にはやったらいいと思います。 既に環境省で作っているガイドラインでは、それをやることに意味があるという時にすると書いています。このガイドラインに沿ってやることになると思います。 複数案についても、必ず複数案ということができるかというと、公共事業は土地の取得が強制的にできますが、民間事業は限られていますからレイアウトの複数案も考えられます。 いずれにせよ単一案でないほうがよいです。どうして複数案かというと、定量的に基準化できないようなものを見るときには複数案が一番分かりやすいからです。単一案だと定量的な基準でしか判断できません。定量的な基準がないと何もないということになると、複数案を比較するのがよいと思います。形式的な複数案は必要ありません。できないことについて比較するとかえって空洞化しますから。 |
| 委員 | 今回、風力とか太陽光発電とかを対象事業に入れていますけれども、これから先にどのような未利用エネルギーが出てくるのかわかりませんが、もし出てきたときに対応できる余地というものがあるのでしょうか。例えば、潮力など。 |
| 会長 | 実際に実用化されたことのないようなものまで入れるわけにはいけません。福岡市条例ですから、福岡市内で可能性のないものについて書いてもしょうがないと思います。 潮力は全く議論されていません。他に、地熱はたぶん福岡市では考えられないと思います。 太陽光については業者がかなり広い範囲で設置しています。たぶんいないとは思いますが、山を削って設置しようという人が出てきたときに今の規模要件ではやりたい放題ということになりかねませんので、入れようとしているわけです。 それでは議題(2)については今出されたご意見ご質問を踏まえたうえで議論を進めていくことにしたいと思います。 |
議題3 その他
| 発言者 | 発言内容 |
|---|---|
| 会長 | それでは事務局よりその他事項についてお願いします。 |
| 事務局 | (説明) |
| 会長 | 今後は少し忙しくなりそうですがよろしくお願いします。空港滑走路増設のアセスについては配慮書の対象ではないのですが準ずる図書を出したいと考えておられるようです。ただし、これは審査の対象ではありません。 それでは、本日の審査会はこれで終了いたします。どうもありがとうございました。 |