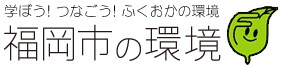現在位置:
福岡市ホーム
> の中のくらし・手続き > の中の環境・ごみ・リサイクル > の中の福岡市の環境 > の中の環境保全・自然環境 > の中の福岡市の環境影響評価 > の中の福岡市環境影響評価審査会 > の中の議事の要旨 平成18年4月12日
更新日:2011年3月9日
福岡市環境影響評価審査会
議事の要旨 平成18年4月12日
西鉄天神大牟田線雑餉隈周辺連続立体交差事業環境影響評価方法書
| 日時 | 平成18年4月12日午後3時05分から午後4時35分 (1時間30分) |
|---|---|
| 開催場所 | 福岡市役所本庁舎15階 第4会議室 |
| 議題 | (1)会長選出 (2)西鉄天神大牟田線雑餉隈駅周辺連続立体交差事業環境影響評価方法書に関する審査 |
| 出席者 | 浅野委員,荒井委員,鵜野委員,近藤委員,島田委員,薛委員,田中委員,田村委員,中園委員,久留委員,藤本委員,柳委員(50音順) |
| 会議資料 | 資料1 西鉄天神大牟田線雑餉隈駅周辺連続立体交差事業環境影響評価方法書 資料2 福岡市環境影響評価条例第9条第1項の規定による意見の概要 参考資料1 福岡市環境影響評価審査会規則 参考資料2 福岡市環境影響評価審査会委員名簿 参考資料3 環境保全上緊急を要する新幹線鉄道振動対策について(勧告) |
【議事概要】
議題1 会長選出
| 発言者 | 発言内容 |
|---|---|
| 事務局 | 各委員の選任後の初めての審査会につき会長の選出をお願いする。 |
| 委員 | 浅野委員を推薦する。 |
| 委員 | 賛同(全員) |
| 会長 | 会長代理に藤本委員を指名。藤本委員承諾 |
議題2 西鉄天神大牟田線雑餉隈駅周辺連続立体交差事業環境影響評価方法書に関する審査
| 発言者 | 発言内容 |
|---|---|
| 会長 | アセスの重要性は現在策定中の第三次環境基本計画(環境省)で謳われている。 本日は方法書の審査であり、都市計画アセスであることを踏まえて審査いただきたい。 |
| 事務局 | (方法書の概要及び住民意見の概要を説明) |
| 会長 | 審議進行について、[1]事業計画に関する意見、[2]方法書によればアセスで取り上げない環境要素に関する意見、[3]方法書による予測評価手法に関する意見の3点から審査を進める。 |
| 会長 | [1]事業計画並びに使用データに関して意見はないか。 |
| 委員 | 計画路線の両側に6メートルの側道を設けることで理解してよいのか。 |
| 事業者 | 基本的に標準で6メートルの道路を計画する予定であるが、詳細検討していく中で場所によっては若干広めにとる必要性も想定されている。 |
| 委員 | 路線の両側で用地買収が行われるのか。 |
| 事業者 | 買収をお願いするところが出てくる。 |
| 委員 | 路線の大野城市側との連携は取れているのか。高架下の利用はどのようになるのか。 |
| 事業者 | 大野城市側は県が既に事業に着手している。スケジュールは県と十分調整していく。高架下の利用は国の旧建運協定に基づき、高架下用地の15%は公共が優先して利用できる。例えば他の事例では駐輪場などで利用している。残りの85%は鉄道事業者が利用する。 |
| 委員 | 雑餉隈駅周辺の計画はどうなっているのか。 |
| 事業者 | 地元の商業関係の組合の方とも将来のまちづくりについて勉強中のところである。 |
| 会長 | 駅前広場の事業手法等は未定なのか |
| 事業者 | まだ検討中である。 |
| 会長 | [2]方法書で選定した環境要素と選定しないものに関して意見を、[3]併せて手法についてのご意見を。 |
| 会長 | 地下水に関する事業者の見解は。 |
| 事業者 | 今回の施工は基礎地盤まで杭を部分的に打ち、地下水を遮断するような連続した構造物は作らないため影響はないと考えられる。 |
| 委員 | 過去、都市高速5号線の工事の際に井戸から自然由来の水銀が検出されている。当地でも、方法書記載井戸の11カ所以外で検出される可能性がある。 工事前に調査した方がよい。 |
| 会長 | 土壌、残土について事前調査が必要と思う。 |
| 事業者 | 方法書の手続きとは別に現地の実態についてということで調査しておきたいと考える。 |
| 委員 | 工事中の重機はどのようなものを使うのか。 |
| 事業者 | 静音型のエンジンの建設機材を使う予定である。 |
| 会長 | 重機の排ガスの件は後ほど審議する。 |
| 委員 | 生息の場としての環境が残っている。線路脇に生息している動物の生息の場と高架後の移動の連続性を考慮しながら工法の段階で考慮されたい。 盛土に生息しているは虫類中心になると思うが、あまり細かに見る必要はなく、今生息している主な種を中心に見ていたただいたらどうか。現況を調査してある程度の種が生息できる環境を残すようにしてはどうか。 |
| 会長 | 現況を調査するということか。 |
| 委員 | 現況を調査し、ある程度の種を確認し、それらが生息できる環境を確保する方がよいと考える。現況調査は非常に大変だと思うが、は虫類あたりを中心に見ていただければいいかなという気がする。 |
| 委員 | 線路の両側の法面の緑地の植物・カナヘビ等の生物に対する高架化への影響はどうなるのか。できたら残るようにして欲しい。付近のため池に冬場にカモが飛来しているが、影響はあるのか。大きな連続した建造物ができた場合にカモが来るのかどうか見ておいた方がよい。高架化の影響はどうなのか。 |
| 会長 | 影響が大きく出ると予測されるだろうか。 |
| 委員 | 可能性がなきにしもあらずで、よく判らない。 |
| 委員 | 工事があると自然環境としての質は落ちていくので、高架下跡地を前よりも環境を良くする必要があるのではないか。 |
| 事業者 | 高架直下は例えば駐車場や店舗などが想定される。 |
| 会長 | 少なくとも盛土部分などについてはミティゲーションでの対応が必要と思う。 |
| 事業者 | 車が通らないような側道は、ご指摘のような使い方もあると思う。 |
| 会長 | 方法書の議論にはなじみにくいが、意見として盛土部分において、全部をコンクリートで固めたりしないようにしてもらいたい。 |
| 事業者 | 承知した。 |
| 委員 | ため池の使われ方はどうなっているのか。地下水の連動の関係はどうか。 |
| 事業者 | 過去は農業用水として活用され、現在は遊水池ではないか。 |
| 事業者 | ため池はあまり水がきれいではないので、これが流れ込む方が問題ではないか。地元からは親水ため池整備の要望や一方で埋めて使わせるようとの要望があがっている。地下水の連動についてはないと考える。 |
| 委員 | 平野部の砂層から掘れば水はすぐにでる。その水は鉄分が多いため、この周辺は20~30メートルのところの花崗岩からの水を飲み水に利用している。しかし環境基準を超えて水銀がでることが頻繁にある。 |
| 会長 | ここまでをまとめると、若干、ミティゲーション的な考え方を取り入れるべきだと、事業者の方でご理解頂いたようである。ため池について構造物が鳥の飛来に影響を及ぼすのではという意見が出たことだけは申し上げておきたい。 |
| 会長 | 選定している環境要素での意見はないか。 |
| 委員 | 予測項目の粉じん等の等に工事用車両からの排ガスは入るのか。 |
| 事業者 | 降下ばいじんのことである。 |
| 委員 | 工事の重機からの窒素酸化物の排出が想定される。 |
| 会長 | 局所の予測が必要ではないか。遠方の測定局の風で代表できるのか。 |
| 委員 | 非常に地域的なことなので、アセスメント手法に基づくとこうなる。 |
| 会長 | 近くに、鉄道が管理している風向計があったが利用できるか。 |
| 委員 | 建物の状況等、場所で違うので難しい。アセスメント手法以外でオーソライズされている方法はない。 |
| 事業者 | 窒素酸化物の予測について、マニュアルでは環境基準を超えていて、かつ工事影響が長期に及ぶ場合に選定することになっている。それに基づいて項目から外している。 |
| 会長 | それが、正解に近いと思われる。しかし、局地的な予測は非現実的でないのか。もっときめ細かく現地の状況に即してやった方がいいと思われるがどうか。 |
| 委員 | ケースバイケースでやるしかない。 |
| 委員 | 方法書の段階ではこれでよいと思うが、低周波音に関して、現状把握はしておいた方がよいのではないか。また低周波音の予測は技術的に可能か。 |
| 会長 | 方法書に記載しているような既存事例はあるのか。 定性的には理解できるが、既存事例で定量的にできるのか。 |
| 委員 | 既往のデータをフルに活用するしかないのでは。 |
| 事業者 | 現在高架になっている地点で現地調査を行い、その結果を基に予測しようと考えている。 |
| 委員 | 問題となるような低周波が発生するかどうかは地盤と構造物の関係に依存するので、地盤が違う所で調査しても予測にはつながらない。 しかし、現状の技術レベルで難しいのであればやむを得ない。 |
| 会長 | 騒音についても、実測をするときに既存の構造物でバッファー効果があるので、そこは補正する必要がある。〇委員とよく相談のこと。実測して、データの評価は周辺建物の状況を入れて評価を行うべき。 |
| 委員 | 騒音の調査地点の設定の根拠はなにか。 周辺の戸建てや病院はしなくてよいのか。 |
| 事業者 | 高架で音源が上がるので、マンションの上層階への影響を考えた。戸建ては逆に下がる傾向なので、現地を見た中で判断した。 |
| 委員 | 振動はどうか。 |
| 会長 | 同様な地盤であれば室外では、どこで測定してもほぼ同じ。 |
| 委員 | 木造の場合、家の中の方が大きな振動となる場合もあるので、弱い建物で評価するのがベストであるが、現実的には選定しづらい。本事業では、高架の基礎を岩盤まで敷設するようなので悪くはならないと思う。したがって、今回の場合、評価点は現実的に選べるところでよいと思う。 |
| 委員 | 工事中はどうか。 |
| 委員 | 工事中については、方法書の問題ではないが、工事に当たっての注意を盛り込むようにしていただきたい。 |
| 委員 | 日照時間が確保できない場合はどうするのか。 |
| 委員 | 高架部の防音対策のための壁と日照問題は相反するが、どう考えるのか。 |
| 事業者 | 建築物には日影規制がかかり、用途地域が商業系と住居系の場合で違う。 問題になるのは住居系の地域である。構造物の高さと側道の幅を考えると日影規制にかかる状態は出てこないと推測されるが、これは次の準備書の段階で予測する。 |
| 委員 | 高架構造物には日照に関する法的な規制が適用されるのか。 |
| 事業者 | 規制はかからないが、建築基準法等を準用して評価する。 |
| 委員 | 諸岡川の状況はどうか。 |
| 事業者 | 三面張りコンクリートである。改修済みである。 |
| 委員 | 高架になった場合はどうか。 |
| 会長 | 先行して河川改修工事は終わっているということですね。 |
| 委員 | 筑紫通りと鉄道とのオーバーパス部に公園があり子供達が遊んでいたが、工事の安全に配慮していただきたい。 |
| 会長 | 意見として伺っておく。 盛土部分の工事で道路を下げるとのことであるが、現況の土地利用形態が変わってくる。同様の事例で補償を求めるものは訴訟になっている事例がある。 |
| 事業者 | 逆のケースだが、過去の街路事業で嵩上げ補償をしたことがある。 |
| 会長 | いくつかの要望的なご意見については事業者で配慮するということで、方法書としては、NOxについては、現状でも環境基準を超過していないし、環境基準をオーバーする恐れはないので評価をしない。〇委員これでよろしいか。 |
| 委員 | はい |
| 会長 | 騒音については、予測の際に配慮してほしい事項あり。どこまで文章化するかは別として少し整理をする。 ミティゲーション等については、お分かりいただけたと思いますが、こちらとしては特に書面は出さないのでよろしくお願いします。 ため池については、本事業とは直接つながらないが、意見があったので、今後の周辺整備の中で勘案してほしい。 |
| 会長 | 議事録は整理して、どの部分を文書化して市長に審査会として提出するかは、会長に一任いただけるか。 ご一任いただいたので、私の方から取りまとめて市に報告したいと思う。 |
| 会長 | 今後の予定は。 |
| 事務局 | 本年12月頃に準備書の審査会を予定している。 |
| 会長 | ただいま説明があったように本件について次回は12月頃との予定です。 外に何か。 |
| 委員 | 方法書で選定されなかった理由は、再度準備書にも収録されるのか。 |
| 会長 | 準備書では扱わない。 |
閉会