さわら人権啓発だより(第35号)
「さわら人権啓発だより第35号」を早良区人権啓発連絡会議にて発行いたしました。
本号では、令和6年10月の主催講演会及び同年12月の福岡市人権尊重週間講演会等をご紹介します。
私たち早良区人権啓発連絡会議は、各校区の人権尊重推進協議会、自治協議会などの各種機関・団体の代表者で構成しています。私たちは、あらゆる差別をなくすために、地域ぐるみの自主的な推進組織である校区人権尊重推進協議会等の活動に取り組み、区民の人権意識の高揚を図り、差別のない明るいまちづくりを目指して活動しています。
今年度は、早良市民センターホールにおいて、早良区人権講座(6月、9月、10月、11月の計4回)をはじめ、早良区人権を考えるつどい(7月)、人権を尊重する市民の集い(12月)を開催することができました。また、映画以外の講演会について、講師のご厚意により、録画配信を実施しました。
この「さわら人権啓発だより」では、皆様に10月の人権講座と12月の講演会等についてご紹介します。
第3回 早良区人権講座
「学校に行くのがつらい子どもたちへ
~不登校になったからこそ気づいた無限の可能性~」
- 講師: 古川滋章さん
- 開催:令和6年10月23日(水曜日) 14時~
- 参加:会場156名、録画配信252回
古川滋章さんは、「家族支援カウンセラー」、通信制高等学校の「教員」として20年以上活動され、現在、福岡城西学園の学園長としてご活躍です。講演内容の一部をご紹介します。
通信制高等学校で働くきっかけ
22年前、通信制「屋久島おおぞら高等学校」の設立に携わってこの仕事に就きました。現在のおおぞら高等学校長は、脳科学者の茂木健一郎氏で、1万人超の生徒さんをお預かりしています。
城西学園と卒業生たち
11年前創設した福岡城西学園(通信制)は、昼間通学を重視しています。約400名の子どもたちが、福岡県内全域から通学しています。プロゴルファー、役者、Youtuberなど、自分の能力を発揮して活躍する卒業生の姿は嬉しいものです。ある生徒は、中2で不登校になりましたが、本校に入学後、塾には通わず、自宅・高校・図書館で自主学習し、高3の全国模試では900点満点で全国1位、志望校の東大理ⅢのA判定を獲得しました。こんな凄い才能のある子はなかなかいないと思います。
日本の教育について
戦後、日本では、皆と同じようにできること、協調性があることが重視され、得意なことを伸ばすより、不得意なことなどを平均値まで上げることに力が割かれました。協調性は美点だし、通学できる子はそれで良いのです。ただ、学校に行けなかったらお先真っ暗ではなく、人はそれぞれ個性があって、他人と比べる必要は全くありません。中国やアメリカでは、学校に行けなくても自宅で勉強して卒業する「ホームスクール制度」があり、「不登校」という概念はありません。
生徒から教わる
いじめに遭い不登校になったある中学生は、楽しい高校生活を送りたい一心で猛勉強して高校に進学し、楽しく過ごしていました。ある時、クラスメイトへのいじめのエスカレートを見過ごせず、それを止めたそうです。そしたら今度は彼女がいじめの対象となりました。「頑張ったけれど、エネルギーがなくなってしまった」と、話してくれました。長袖の下は両腕ともリストカット痕だらけで、私は「今までよく頑張ったね」と、傷が1本でも2本でも自分に移ればいいのにと願い、その子の腕をさすりました。その後、彼女は我校に転入し、楽しく過ごして卒業しました。在学中、「この学校で、もしいじめがあったら私を呼んで。先生がいじめた子を怒る時、いじめられるのはどんなに辛くて悲しいか、経験した私が伝えてあげる」と彼女は言ってくれました。私たちは通信制高等学校の教員として働く中で、子どもたちに教えられること、子どもたちに助けられることばかりです。子どもが本来持つパワー、エネルギー、考えていることは物凄いです。不登校を「休んでいる」とか「怠慢だ」と捉える向きもありますが、学校に通っている子たちよりも、何十倍も自分と向き合って考えています。
卒業生のメッセージより
開設11年間1,000人以上の卒業生のメッセージから、一部を紹介します。「私は中学の途中で不登校になり、理由は自分でも未だに分かりません。そんな私がこの学校に入学して今まで幸せな毎日を過ごすことができたのは、先生方が、仲間が、とても温かかかったからです。この学校で大人を頼っていいことを知り、苦しかったことも時間が癒してくれることを知り、何より人の優しさが救えるものの多さを知りました。友達と一緒に笑ったり泣いたり、時には本気でぶつかり合えることがどれだけ幸せなことなのか、3年間で実感しました。この学校で過ごした1日1日がどれもかけがえのない思い出です。早く先生方と皆でお酒が飲めるのを楽しみにしています。私と出会ってくれて本当にありがとう。皆のことが大好きです」
子どもたちの声を聴く
いろんな思いを持って子どもたちは生きています。子どもたちが思っていることを聴く機会は、現在、とても少なくなりました。我が子はもちろんのこと、皆様の地域の子どもたちはどんなことをどんな風に思ってるんだろうかと、是非、耳を傾けて15分間、聴いてみてください。大人に思いを聴いてもらえると、その子たちはとても救われるんじゃないかなと思います。本日は私のお話を聴いていただいて、本当にありがとうございました。
第53回 人権を尊重する市民の集い(早良区会場)
「認知症とともに生きる」
- 講師:おれんじドア実行委員会代表 丹野智文さん
- 開催:令和6年12月9日(月曜日)14時~
- 参加:会場320名、録画配信201名
講師の丹野智文さんは2013年、若年性アルツハイマー型認知症と診断されました。そのため、営業職から事務職に異動し勤務を続けながら、2015年より、認知症当事者のための物忘れ相談窓口「おれんじドア」を開設され、自らの経験を語る活動に力を入れておられます。講演内容の一部をご紹介します。
39歳の時に認知症に
私は営業職をしていた11年前、39歳の時に認知症と診断されました。認知症とわかった後、妻と二人で社長と上司に話をしました。社長から長く働ける環境をつくるからとの話をいただき、とても嬉しかったのですが、認知症になった私が本当に事務職の仕事ができるのか、とても不安でした。
「認知症」イコール「終わり」ではない
私は認知症になってから、多くの人たちとの出会いがありました。笑顔で元気な認知症当事者との出会いもあり、この人のように生きてみたいと思ったことが、前向きになるきっかけでした。そして、私が選んだのは、認知症を悔やむのではなく、認知症とともに生きるという道です。悪いことばかりではありません。また、「認知症」イコール「終わり」ではないことに気づきました。
認知症をオープンに
生活していて困ることは、私が認知症当事者と誰も気がつかないことです。見た目には普通の人と何も変わりがないからです。そこで私は認知症をオープンにしようと思いました。しかし、色々と葛藤がありました。まだまだ認知症に偏見を持っている人が多いと思っていたからです。子どもたちに話をすると、「パパは良いことをしているのだから、いいんじゃない?」と言ってくれました。私はその言葉で、オープンにしようと決めたのです。
人と人とのつながりがあれば
高校の部活仲間と会う機会があり、認知症になったことをはじめて話すと、「大丈夫。お前が忘れても、俺たちが覚えているから」と言ってくれました。これから多くの人の顔を忘れてしまうかもしれませんが、皆が忘れないと言ってくれる。だから忘れたっていいと思えるようになりました。認知症になっても、人と人とのつながりがあれば笑顔で楽しく過ごせることを知りました。
「介護者」ではなく「パートナー」
最初の頃、周りの人たちは「介護者」と思っていました。その後、何か違うと思うようになり、今は、サポートしてもらいながらも何かを一緒にする「パートナー」だと実感しています。今までは認知症というと、何もできなくなるので、やってあげなければと思う人が多かったと思います。何もできないと決めつけていたのではないかと考えます。
本当の自立とは
認知症当事者ができることを奪わないでください。時間はかかるかもしれませんが、待ってあげてください。一回でできなくても次はできるかもと信じてあげてください。できた時には当事者は自信を持ちます。失敗を恐れずに自立をする気持ちを強く持つことが大切だと思います。できることは自分でする。本当の自立とは、自分の意見をはっきり言って自分で決めること、できないことはできないと周りに頼み込めることだと思います。
大切な家族、必要な仲間
私が認知症と診断された11年前、当事者本人が相談する場所は一つもなかったんです。そこでつくったのが「おれんじドア」でした。「じゃあ、どうしたい?」と本人と常に話してみる。これ、家族では駄目なんですよ。家族って一番大切なものなんです。だから家族には本音は言いません。私もそうです。不安なことや困ったことって家族には言えないんですよ。家族が一番大切だからこそ言えないことも、仲間には言えるんですね。だから、本人の周りにたくさんの仲間が必要なんです。
安心して認知症になれる社会を
私は認知症の活動が仕事になりました。これは「認知症でもできる」仕事ではなく、「認知症になったからこそできる」仕事です。皆で支える社会、安心して認知症になれる社会をぜひ一緒に考えていきましょう。ご清聴いただきありがとうございました。
令和6年度 早良区人権を考えるつどい・人権講座 実績【会場:早良市民センタ-】
人権を考えるつどい
映画:「あん」上映
- 日時:7月11日(木曜日)
- 参加:午前305名 午後313名
第1回人権講座
- 「認知症とともに生きる~認知症フレンドリーシティ~」
- 講師:党 一弘さん
- 開催:6月20日(木曜日)
- 参加:会場160名 配信184回
第2回人権講座
- 「みんなちがってみんないい生き方を~金子みすゞの心とともに」
- 講師:ちひろさん
- 開催:9月18日(水曜日)
- 参加:会場305名 配信89回
第4回人権講座
映画:「桜色の風が咲く」上映
開催:11月14日(木曜日)
参加:午前303名 午後278名
このページに関するお問い合わせ先
部署: 早良区 総務部 生涯学習推進課
住所: 福岡市早良区百道2丁目1番1号
電話番号: 092-833-4401
FAX番号: 092-851-2680
E-mail:gakushu.SWO@city.fukuoka.lg.jp


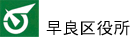
 東区
東区 博多区
博多区 中央区
中央区 南区
南区 城南区
城南区 早良区
早良区 西区
西区