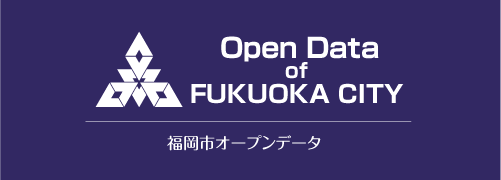平成17(2005)年3月20日午前10時53分、玄界灘を震源とするマグニチュード7・0の福岡県西方沖地震が発生しました。市は、この日の記憶を風化させないために、3月20日を「市民防災の日」と定めています。震災から20年、改めて地震への備えについて考えます。
市は、福岡県西方沖地震や平成28年に起きた熊本地震の教訓を踏まえ、公的備蓄の拡充や、ICTを活用した新たな支援体制の仕組みを整えるなど、災害に強いまちづくりを進めています。
地域防災課の杉谷俊介係長(41)に聞きました。

博多湾から市内の中心部を走り筑紫野市に至る警固断層を震源に、都市直下型の地震が起きた場合、約3万人の避難者が出ると予測されています。
市は、避難者3万人に対応できるよう、3日分の水や食料(27万食)の大半を博多区月隈の備蓄倉庫に保管しています。残りについては、発災後すぐに使用できるよう避難所となる公民館などに保管しています。
また、簡易トイレなどの生活必需品や、発電機、間仕切りなどを、地域防災の拠点となる校区・地区の防災倉庫に分散して備蓄しています。

■ 地域の安全・安心を支える自主防災組織
災害時には、住民同士の助け合いが欠かせません。市は、校区・地区単位で地域住民が主体となって災害に備える「自主防災組織」の活動に対し、防災活動の助言、助成、防災資機材の貸与などを行っています。現在、市内152の校区・地区で、自主防災組織が結成されています。
自主防災組織の皆さんは、日頃から各地域で防災知識の普及啓発や防災訓練に取り組まれています。その中には、市が平成17年から始めた、地域や企業の防災リーダー養成講座「博多あん(安全)・あん(安心)塾」の修了者も多く活躍しています。災害発生時には、高齢者などサポートが必要な人の避難誘導や、市と協力して避難所の運営などに当たります。

■ 一人一人が災害への備えを
市は、性別や障がいの有無などにかかわらず、さまざまな人に配慮した避難所の運営や、避難所の生活環境の改善などにも取り組んでいます。
市民の皆さん一人一人が当事者意識を持って災害に備えることで、被害を最小限に食い止めることができます。防災に関する知識と適切な行動は命を守ることにもつながります。いざという時に役立ててもらえるよう、市は、防災関係のハンドブックの配布や、出前講座・イベントなどを通して啓発活動を行っています。
大規模な地震が発生すると、一時的に防災への関心は高まりますが、時間の経過とともに薄れてしまいます。災害はいつどこで起こるか分かりません。皆で一緒に備えていきましょう。
■問い合わせ先/地域防災課
電話 092-711-4156
FAX 092-733-5861
玄界島での防災訓練。今年の3月20日(木曜日・祝)は、例年よりも規模を拡大し、防災訓練を実施
いざという時のために
玄界校区自治協議会 井上公加(きみかず)会長(70)の話

西方沖地震では、島のほとんどの家屋が被害を受けたにもかかわらず、島民全員が無事でした。
玄界島では、皆が顔見知りです。誰が避難所に来ていないか、すぐに分かります。全員が避難できたのも、日頃の防災訓練や、いつでも声を掛け合える関係性、自分ができることは率先して行うという意識があったからだと思います。
島では、被災した3月20日に毎年防災訓練を行っています。地域や職場で実施される防災訓練にぜひ参加してみてください。
避難所の生活環境の向上に取り組みます
大規模な災害が発生すると、慣れない環境での避難生活を余儀なくされることもあります。
避難所では、▽トイレを使えず我慢してしまう▽パンやおにぎりなど冷たい食事ばかりになる▽冷たい床で雑魚寝状態が続くと体調を崩す恐れがある▽仕切りのない状態でプライバシーが守られない―などの課題が災害のたびに取り沙汰されています。
これらを改善し、被災者の負担を減らして、できる限り良好な状態で過ごしてもらえるよう、市は避難所の生活環境の改善に取り組みます。
■問い合わせ先/地域防災課
電話 092-711-4156
FAX 092-733-5861
【トイレ、キッチン、ベッド(TKB)を改善】
T 清潔なトイレ

水なしでも衛生的に使用できる簡易トイレを増やします。洗面台なども搭載された、移動式トイレカーの導入も検討しています。
K 温かい食事(キッチン)

被災者の心を癒し、力を与えられるよう、キッチンカーなどで温かい食事をできるだけ早く提供します。
B 生活空間(ベッド)

心と体が休まる空間を確保するため、簡易ベッドやパーティション等を増やします。
母の視点で防災を考える
防災サークル「Haha+AID(ハハエイド)」代表の因幡那水さん(48)の話

普段から、災害が発生した時の行動や避難生活を想像して実践する「せいかつ防災」を提案しています。備蓄品で食事を取ったり、ポーチの中に自分と家族の必要な物をまとめたりすると、備えておくべきものが明確になります。
防災を日々の暮らしの中に取り入れ、一人一人に合った自分らしい備えが無理なくできるようになればいいと思います。Haha+AIDでは、防災を「日常生活を守ること」と捉え、食事の大切さなどを意識しています。被災時に温かい食事が取れれば、心の安定にもつながります。市の「TKB」の取り組みにも期待します。
成長を続ける天神のまち 都心部の安全対策
市内では、都心部の機能を高め、新たな空間や雇用を生み出すプロジェクト「天神ビッグバン」と「博多コネクティッド」が進行しています。
建て替えの時期を迎えたビルが、耐震性の高い先進的なビルに建て替えられることで、市民はもちろん、働く人や訪れる人の安全・安心につながります。4月にオープンする「ワン・フクオカ・ビルディング」(通称ワンビル)もその一つです。

西日本鉄道福ビル街区開発部の金子晃子係長(36)に防災対策について聞きました。

ワンビルは、商業テナントやホテル、オフィスなどが入る、地下4階・地上19階建ての大型複合ビルです。地震のエネルギーを吸収する最新型の制震装置を85カ所に設置し、福岡県西方沖地震を上回る震度6強の揺れにも耐えられる構造になっています。
建物1階の出入り口に防潮板等による浸水対策を施し、万が一の水没を防ぐために主な受変電設備を5階に配置しました。災害が発生しても、停電時にはガスで発電し、ガスも止まった時には、重油での発電が3日間可能です。トイレも、下水管が断絶した場合に3日間使用できるよう計画しています。
災害発生時には、天神地区の帰宅困難者に一時滞在施設として1階と6階のフロアを開放します。555人の受け入れが可能で、3日分の水や食料、防災ブランケットなどを備蓄しています。食料は、子どもや高齢者、外国人などにも対応できるようさまざまな配慮を行っています。
●これからの天神
西方沖地震当時、私は学生で、日頃からよく訪れていた場所が被災した様子を見てショックを受けました。ワンビルの防災対策が、天神を訪れる人の安心につながればうれしいです。
天神地区を安全・安心なまちにしたいという思いは、どの事業者も同じです。災害対策はもちろん、にぎわいの創出や景観形成など、ビルごとに工夫がなされています。先進的な街へと成長を続ける天神に、当社も貢献していきたいと思います。
ワンビルがたくさんの出会いや交流の場、新しい文化やビジネスを創造する場になってほしいと願っています。

【外出時に地震が発生したら】
災害は、時間と場所を選びません。とっさの行動で命を守りましょう。
●デパートなど=手荷物やかごで頭を保護し、商品の落下やガラスの破片に注意する。落ち着いて店員の指示に従い行動する。
●エレベーター=全てのボタンを押し、止まった階で外に出る。閉じ込められたら、非常ボタンやインターホンで連絡を取り、救助を待つ。
●路上=手荷物などで頭を保護し、広い場所へ避難する。街では、ガラスや看板などの落下物、自動販売機の転倒に注意する。住宅街では、ブロック塀や門柱から離れる。
【もしものために備蓄しよう】
災害が発生すると、水道や電気、ガス等のライフラインをはじめ、水や食料等の供給が途絶えることが考えられます。万一に備え、生活必需品を3日分以上そろえておきましょう。
●備えておきたいもの
水や乾麺、缶詰など常温で長期間保存できる物がお薦めです。カセットコンロやガスボンベなどがあれば、温かい食事を取ることができます。備蓄には、普段から少し多めに購入しておき、使用した分を随時買い足す「ローリングストック」がお勧めです。消費(使用)期限を気にせず、常に一定量を備蓄できます。
簡易トイレ(携帯トイレ)、懐中電灯、携帯ラジオ、モバイルバッテリー等も備えておきましょう。
詳細は、市ホームページ(「福岡市 家庭での備蓄」で検索)で確認を。
■問い合わせ先/地域防災課 電話 092-711-4156 FAX 092-733-5861
3月20日「市民防災の日」講演会
市は、3月20日(木曜日・祝)に市民防災の日講演会「福岡県西方沖地震 あれから20年」を開催します。
【第1部】基調講演「福岡県西方沖地震から20年『これまで』と『これから』」
講師は関西大学社会安全学部特別任命教授・河田惠昭(よしあき)氏。
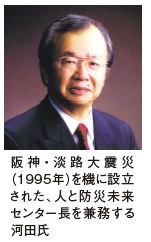
【第2部】パネルディスカッション「日頃の備えは大丈夫?~災害から学ぶ防災~」
河田惠昭氏、因幡那水氏(博多あん・あんリーダー会会長)、高橋淳夫氏(読売新聞西部本社)、古庄修治氏(元熊本市政策局長)、福岡大学学生団体「みらプロ」が、日頃の備えについて話します。司会はFBS福岡放送アナウンサーの若林麻衣子氏。
【日時】 3月20日(木・祝)午後1時30分から4時30分
【場所】 エルガーラ8階大ホール(中央区天神一丁目)
【定員】 600人(先着)
【料金】 無料
【申し込み】 3月14日(金曜日)までにファクスかメール(メール bousai01@city.fukuoka.lg.jp)に氏名・電話番号を書いて地域防災課へ。同講演会申込フォームからも申し込み可能です。
■問い合わせ先/地域防災課
電話 092-711-4156
FAX 092-733-5861
LINEで「とつぜんはじまる避難訓練」
市LINE(ライン)公式アカウントを使って、3月20日(木曜日・祝)から31日(月曜日)の間に抜き打ちでオンライン避難訓練を実施します。地震が発生したと仮定して取るべき行動や最寄りの避難所などを確認できます。希望者は3月13日(木曜日)以降に専用ページから参加登録してください。
■問い合わせ先/地域防災課
電話 092-711-4156
FAX 092-733-5861
防災アプリ「ツナガル+」の活用を
「ツナガル+(プラス)」は、災害時に役立つ市の防災アプリです。災害時には、避難所の開設状況や混雑状況が分かります。市が開設する避難所以外の場所にいる人も、市に支援を求めることができます。
■問い合わせ先/防災推進課
電話 092-711-4153
FAX 092-733-5861