お母さんの健康管理
産婦人科を受診し,妊娠届出書を発行してもらいましょう。
妊娠届出書,身分証明書,マイナンバーが確認できるものを持って保健所に行きましょう。
母子健康手帳,妊婦健康診査・産婦健康診査助成券のつづりを交付します。

・妊婦健康診査は必ず受けましょう。
特に注意しなければならないのは貧血、妊娠高血圧症候群、妊娠糖尿病であり、どれも胎児の発育に影響し、母体の健康を損なうことがあります。
また、妊娠21週までは流産の、妊娠22週以降は早産の危険性にも注意しなければなりません。
そのためにもきちんと妊婦健康診査を受診し、医師の指導を守りましょう。
働きながら安心して出産を迎えるために,母性健康管理指導事項連絡カード(母健連絡カード)を活用しましょう。
「女性にやさしい職場づくりナビ」
※仕事が休みづらい等で困った時は、ご相談ください。
福岡労働局 雇用環境・均等部 指導課 TEL.092-411-4894
・お酒やタバコはやめましょう。
妊娠中の喫煙・飲酒は、胎児の発育に影響を及ぼします。
夫や周囲の人も妊婦や赤ちゃんのそばでは、喫煙をやめましょう。
・夫に協力してもらい、つわりをのりこえましょう。
・自分の生活のリズムをつくり、睡眠や休養を十分にとり、過労をさけましょう。
・栄養のバランスをよく考えて、食事をきちんととりましょう。
・薬を飲むときは、かかりつけの医師などに相談しましょう。
妊娠中の薬の影響についても十分説明を受け、指示された用量・用法を守りましょう。
※「妊娠と薬情報センター」において、妊娠中の薬の服用に関する情報提供が実施されていますので、主治医とご相談ください。出産時に使用される医薬品についても、十分な説明を受けましょう。
・歯の健康にも気を配りましょう。福岡市在住の妊産婦の方は歯科健康診査の助成があります。
・安定期に入ったら産院の指導のもと,乳房や乳首の手入れを始めましょう。
妊婦の心身の安定には、夫・パートナーや家庭の理解や協力が必要です。
妊娠の40週間(280日間)は、「父親」として育っていく大切な準備期です。
夫・パートナーは、積極的に妻に協力し「親になること、子どもとは」など話し合ってみましょう。
妊娠中も、シートベルトを正しく着用することによって、交通事故に遭った際の被害から母体と胎児を守ることができます。ただし、シートベルトを着用することが健康保持上適当でない場合は着用しなくてもよいこととされていますので、医師に確認するようにしましょう。
妊娠中にシートベルトを着用する場合には、事故などの際の胎児への影響を少なくするために、妊娠していないときとは異なるシートベルトの着用の方法が必要です。
- シートの背は倒さずに、深く腰掛けましょう。
- 腰ベルト肩ベルト共に着用するようにしましょう。三点式ベルトの腰ベルトだけの着用や二点式ベルトの着用は、事故などの際に状態が屈曲して腹部を圧迫するおそれがあり、危険です。
- 腰ベルトは、大きくなった腹部(妊娠子宮のふくらみ)を避けて、腰骨のできるだけ低い位置でしっかり締めましょう。
- 肩ベルトは、肩から胸の間に通し、腹部を避けて体の側面に通しましょう。また、肩ベルトがたるんでいると事故の際に危険ですから注意しましょう。
- 腰ベルトや肩ベルトが腹部を横切らないようにしましょう。
- バックルの金具は確実に差し込み、シートベルトが外れないようにしましょう。
- ベルトがねじれていないかどうか確認しましょう。
※妊娠中の正しいシートベルトの着用方法
ふくおか・まごころ駐車場制度(妊産婦)
障がいのある方や高齢の方,妊産婦の方など,車の乗り降りや移動に配慮の必要な方が,公共施設,店舗等の障がい者等用の駐車場などに車をとめ,安全かつ安心して施設を利用できるように支援する制度です。妊産婦で対象となるのは妊娠7か月から産後3か月までの方です。
福岡県ホームページ ふくおか・まごころ駐車場
| 健康診査 | 妊婦健康診査は必ず受けましょう。 特に気がかりなことがなくても、身体には様々な変化が起こっています。 少なくとも、4週間に1回は妊婦健康診査を受けましょう。 |
|---|---|
| からだの変化 | つわりがはじまり、流産をおこしやすい時期です。 |
| ワンポイント | 流産の危険がある時ですから仕事のしかたや休息のとりかたに十分気をつけましょう。 わからないこと、心配なことは主治医に相談しましょう。 |
| 健康診査 | 少なくとも、妊娠23週(6か月末)までは4週間に1回、24週(7か月)からは2週間に1回は妊婦健康診査を受けましょう。 特に、妊娠22週以降は、早産の危険性にも注意しなければなりません。 そのためにもきちんと健康診査を受診し、医師の指導を守りましょう。 |
|---|---|
| からだの変化 | 赤ちゃんからのメッセージ(胎動)を感じるようになってきます。 安定期に入り、お腹の大きさも目立ってきます。 |
| ワンポイント | 太りすぎや運動不足になりやすい時期です。積極的に戸外に出て散歩などをしましょう。 口の中を清潔にして、歯科健診を受けておきましょう。(福岡市在住の妊婦の方は歯科健康診査の助成があります。) 保健福祉センター(保健所)や病院(医院)のマタニティースクール(母親・両親学級)などに参加して、妊婦体操、呼吸法などの練習を始めましょう。そして、友だちの輪を広げましょう。 |
| 健康診査 | 2週間に1回は妊婦健康診査を受けましょう。 |
|---|---|
| からだの変化 | むくみやすくなり、妊娠線が目立ってきます。 |
| ワンポイント | 赤ちゃんを迎える準備はできていますか。 産後の授乳にそなえて、赤ちゃんのために、乳首の手入れをしましょう。 |
| 健康診査 | 1週間に1回は妊婦健康診査を受けましょう。 |
|---|---|
| からだの変化 | もうすぐ出産です。 赤ちゃんはいつ生まれてもれてもよいほどに成長しています。 |
| ワンポイント | 入院に必要な準備はできていますか。 |
| 健康診査 | 産後2週間,産後1か月をめどに健康診査を受けて、産後の身体の回復や産後うつ等の心の不調がないかをたしかめましょう。 心も身体も落ち着いたら,産後の歯科健康診査を受けましょう。福岡市在住の産婦の方は産後1年以内に1回,歯科健康診査の助成があります。 |
|---|---|
| からだの変化 | 気持ちが沈んだり涙もろくなったり、何もやる気になれないということはありませんか?その状態が長く続いている場合は産後うつかもしれません。病院(医院)や保健所に相談しましょう。 |
| ワンポイント | 母子健康手帳に添付されている出生連絡票のハガキを出しましょう。 保健師・助産師などによる新生児訪問指導があります。赤ちゃんのこと、お母さんのこと、育児のことなどについて相談ができます。 |

出産後は、赤ちゃんが生まれてうれしいはずなのに気分が落ち込んだり、赤ちゃんへの愛情がわかなかったりすることがあります。昔から「産後の肥立ちが悪い」という言葉がありますが、産後数か月間は気分の変化をきたしやすい時期です。
よく見られる気分の変化に『マタニティー・ブルーズ』と『産後うつ』があります。
『マタニティー・ブルーズ』は、ささいなことで不安になったり緊張したり、涙がでたり、気分が沈んだり、集中力がなくぼんやりする状態をいいます。出産後すぐから1週間ごろまでにみられますが、多くは1~2日で自然に良くなりますので心配はいりません。
『産後うつ』は、産後のお母さんの10-15%に起こるとされています。気分が沈み、育児や家事をする気力もありませんし、母親としての喜びや自信もなくなります。この状態が2週間以上続くようなら、家族に話して医師や助産師、保健師,子育て世代包括支援センター等に相談してみましょう。自分の気持ちを周囲の人に理解してもらうことは、とても大切なことです。重症の産後うつは専門家への相談と薬による治療が必要になります。軽症の場合は、周囲の方の支えだけで治ることもよくあります。
お母さんの心の健康は赤ちゃんが健やかに育つためにとても大切なことです。
お母さん自身はもちろんですが、周囲の方も出産後のお母さんの気分に注意してあげてください。
福岡市では産後うつなどお母さんの心身の不調を早期に発見し,適切なケアにつなげるため,産後2週間頃と産後1か月頃に行う産婦健康診査費用を公費負担しています(要件,上限あり)。産婦健康診査は出産した産科医療機関等で受けることができ,問診,診察,体重・血圧測定,尿検査,こころの健康チェックを行います。お母さんの産後の心と身体の状態を確認するために健診を受けましょう。
~新しい生命と母体に良い栄養を~

・食事は1日3回バランスよく
特定の料理や食品に偏らないバランスのとれた食事をとることが基本です。特に妊娠中期から授乳期は,普段より副菜,主菜,果物などを多くとるなどして,必要なエネルギーや栄養素をしっかりとりましょう。
・貧血予防のために
貧血を防ぐためには,毎日,栄養のバランスがとれた食事をとることが大切です。鉄分の補給については,吸収率が高いヘム鉄が多く含まれる赤身の肉や魚などを摂るように心がけましょう。また,鉄分の吸収を高めるたんぱく質やビタミンCが含まれる食品を摂ることも大切です。
・妊娠高血圧症候群の予防のために
睡眠,休養を十分にとり,過労を避け,望ましい体重増加になるように心がけましょう。毎日の食事はバランスのとれた内容とし,砂糖,菓子類はひかえめにし,脂肪の少ない肉や魚,そのほか乳製品,豆腐,納豆など良質のたんぱく質や,野菜,果物を適度にとり,塩味は薄くするようにしましょう。
・丈夫な骨や歯をつくるために
生まれてくる赤ちゃんの骨や歯を丈夫にするためには,カルシウムだけではなく,たんぱく質,リン,ビタミンA・C・Dの栄養素を含む食品をバランス良く摂ることが大切です。産後もバランスの良い食生活を継続し,赤ちゃんとお母さんの健康を保ちましょう。
・妊娠中の葉酸摂取について
二分脊椎などの神経管閉鎖障がいの発症予防のため,妊娠前から妊娠初期の女性は食事に加え,サプリメントなどによって付加的に1日あたり400μgの葉酸摂取が望まれます。ただし,摂りすぎには注意が必要です。
・妊娠中の食中毒予防について
妊娠中は免疫機能が低下し,食中毒などの食べ物が原因の病気にかかりやすくなっています。妊婦にとって特に注意が必要な病原体として,リステリア菌とトキソプラズマ原虫があげられます。また,お母さんに症状がなくても,赤ちゃんに病原体の影響が起きることがあります。感染を防ぐため,妊娠中は生ハムや加熱していないナチュラルチーズなどを避け,食品を十分に過熱して食べましょう。そして食中毒予防のために,日頃から食品を十分に洗浄し,加熱するなど,取扱いに注意しましょう。
| 体格区分 | 妊娠全期間を通しての 推奨体重増加量 |
妊娠中期から末期における 1週間あたりの推奨体重増加量 |
|---|---|---|
| 低体重(やせ) BMI 18.5未満 |
9~12kg | 0.3~0.5kg/週 |
| ふつう BMI 18.5以上 25.0未満 |
7~12kg 体格区分が「ふつう」の場合、BMIが「低体重(やせ)」に近い場合には推奨体重増加量の上限側に近い範囲を、「肥満」に近い場合には推奨体重増加量の下限側に近い範囲を推奨することが望ましい。 |
0.3~0.5kg/週 |
| 肥満 BMI 25.0以上 |
個別対応 BMIが25.0をやや超える程度の場合は、おおよそ5kgを目安とし、著しく超える場合には、他のリスク等を考慮しながら、臨床的な状況を踏まえ、個別に対応していく。 |
個別対応 |
※体格区分妊娠全期間を通しての体格区分は、非妊娠時の体格による。
※BMI(Body Mass Index)=体重(kg)/身長(m)2
魚介類は良質なたんぱく質や微量栄養素を多く含みます。魚介類の一部には食物連鎖を通じて高い濃度の水銀が含まれているものもあり,胎児に影響する恐れがあるという報告もあります。水銀濃度が高い一部の魚だけに偏って,毎日たくさん食べることは避けましょう。
- 厚生労働省ウェブサイト「これからママになるあなたへ」
- 健やか親子21(第2次)ホームページ「妊産婦のための食習慣」















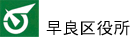
 東区
東区 博多区
博多区 中央区
中央区 南区
南区 城南区
城南区 早良区
早良区 西区
西区