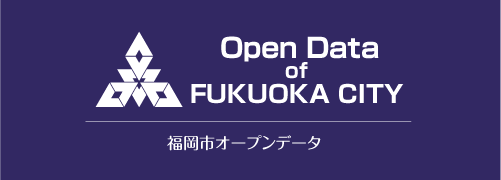子どもたちの健やかな成長のために 福岡市の給食
市は現在、12万2千人を超える児童生徒に学校給食を提供しています。子どもたちの成長に欠かせない「給食」への市の取り組みを紹介します。
市は、市立の小学校146校、中学校70校、特別支援学校7校に通う子どもたちに、毎日給食を提供しています。
小学校と肢体不自由特別支援学校は各校の給食室で、中学校と知的障がい特別支援学校では市内3カ所の給食センターで調理を行います。
徹底した衛生管理の下、各校の給食時間に合わせて調理が行われます。おいしく食べてもらえるよう工夫しながら、温かいものは温かく、冷たいものは冷たいまま、子どもたちに届けられます。

主食は、ご飯が週に3回、パンが週に2回で、児童生徒が1日に必要な栄養量のおよそ3分の1を、毎日の給食で摂取できるようにしています。
また、食材には市内産の旬の農水産物等を積極的に使用し、安全性や価格、味などを審査の上、選定しています。給食室や給食センターに納品された食材は、品質や鮮度などを厳しくチェックします。

●バラエティー豊かな献立
学校給食の献立づくりは、栄養教諭が前年の夏ごろに翌年度の年間計画を立てることから始まります。
その後、月ごとの献立を半年前から検討し、学校長や栄養教諭、保護者代表、調理業務員などが話し合い、最終決定します。
子どもたちに毎日楽しく食べてもらおうと、季節を感じられる「白玉雑煮」「柏もち」などの行事食や、「ガパオライス」「チリコンカーン」といった世界の料理など、多彩なメニューを取り入れています。
小・中・特別支援学校の1カ月ごとの献立表は、市ホームページ(「福岡市 学校給食の献立表」で検索)にも掲載しています。
小学校給食の食物アレルギー情報がLINEで届きます
市LINE(ライン)公式アカウントを友だち登録し、「受信情報」→「学校」を選択してください。
アレルギー特定原材料等28品目の中から該当するアレルゲンと配信希望時間を登録すると、小学校給食の献立やアレルゲン情報が毎日届きます。
小学校の給食
■石丸小学校(西区)の栄養教諭・阪井裕美先生の話

お昼が近づくと、給食のおいしそうな匂いが教室まで漂ってきます。出来たての温かい給食を教室に運んで、配膳し、みんなで食べて、使った食器を戻す―。小学校での6年間、そんな一連の流れを毎日繰り返すことで、食の大切さや、作ってくれた人への感謝の気持ちが育まれていくのだと思います。
私たち栄養教諭は、各校で給食の管理や「食べること」に関する指導を行っています。苦手なものが多かった子どもが楽しそうに食べている姿を見たり、「おいしかったよ」と報告してくれたりすると、成長を感じてうれしくなります。


●安全性への配慮
食中毒を防ぐため、給食では原則、生の食材は提供しません。野菜なども85度以上で1分以上加熱します。ただし、ミカンやイチゴなどの果物やミニトマトは流水で十分に洗浄できるため、衛生面を考慮の上、生で提供しています。
また、食物アレルギーのある児童に対しては、「卵」「マヨネーズ」「ごま」「ごま油」の4種を除いて提供するなど、個別対応を行っています。
●楽しい給食
いろいろな食文化を知ってもらおうと、毎年テーマを決め、それに沿った献立を月に1度提供しています。今年度のテーマは「郷土料理」で、子どもたちは山口県の「チキンチキンごぼう」、沖縄県の「ゴーヤチャンプルー」などをおいしそうに食べていました。
食材は「地産地消」にこだわり、「姪浜のり」や「能古島の甘夏ゼリー」なども提供しています。毎日の献立を子どもたちはとても楽しみにしてくれていて、最近は食べ残しもほとんどなくなってきました。
「レバーとだいずの揚げ煮」も人気メニューの一つです。これをきっかけにレバーが食べられるようになったという話もよく聞きます。給食で出るレバー料理は、作り方を尋ねられることも多いです。
子どもたちが健やかに成長していけるよう、これからも子どもたちの声をしっかり聞き、安全で、安心な給食作りに生かしていきたいと思います。
「給食室探検」を行いました
夏休み直前の給食がない日に1年生を給食室に招待して、毎年「給食室探検」を行っています。この1日限りの体験が、給食室の仕事を子どもたちに身近に感じてもらういい機会になっています。

中学校の給食
給食センターは市内3カ所にあり、早朝から調理を開始して、出来上がった給食を専用の保温ケースに入れ、給食時間の30分前までに配送を完了します。
第1給食センター(博多区東平尾一丁目)では、中学校21校と特別支援学校2校に、約1万3千人分の給食を毎日提供しています。
■市立第1給食センターの阿部圭子センター長の話
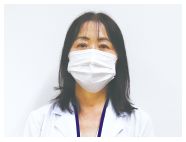
給食センターでは、「安全・安心」を第一に、厳しい衛生管理基準に基づき整備された施設で、食材の受け入れから調理・配送までを行っています。
調理エリアは、野菜の下処理や、揚げ物・焼き物・蒸し物、和(あ)え物、煮炊きなど、調理の工程別に分かれ、効率よく調理を行っています。調理エリアへ入る際には、専用の靴に履き替えたり、エアシャワーを使用したりして、ほこりや病原菌の侵入を防ぎます。給食を運ぶ大型のコンテナも、毎日洗浄・滅菌しています。


●一人一人の状況に合わせて
食物アレルギーのある児童生徒が安全に食べることができるよう、一般調理エリアとは別の専用調理室で、8種類のアレルゲン(卵・乳・小麦・そば・落花生・エビ・カニ・ごま)に対応した給食を専任の職員が手作りしています。
児童生徒それぞれに配慮した調理法で、通常の調理法の献立とできるだけ食感や味が変わらないよう工夫しています。特別支援学校に通う咀嚼(そしゃく)が難しい子どもには、食材を細かく刻むなど、飲み込みやすさに配慮して提供します。

●さらに新たな献立も
新しい献立もどんどん取り入れています。7月には、新メニューとして「回鍋肉(ホイコーロー)」や、デザートに「七夕ゼリー」が登場しました。
当日の献立の栄養価や豆知識なども校内放送でお知らせしています。また、毎年夏休みに生徒たちから献立を募り、10月に「学校給食コンテスト」を実施しています。優秀な作品は、実際に翌年度の給食で提供します。
うれしいことに、ここ数年、おかずの食べ残しがなくなってきました。これからも、食材の安全確保を行い、調理方法も工夫しながら、おいしく、より良い給食を作っていきます。

市はこれからも、子どもたちの健やかな成長のために、安全安心で「おいしい給食」の提供に取り組んでいきます。
■問い合わせ先/給食運営課 電話 092-711-4642 FAX 092-733-5865
毎日の献立画像をホームページに公開しています
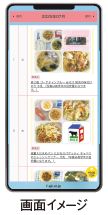
市は、全ての市立小・中・特別支援学校の毎日の給食献立の画像と内容を、ホームページ(「福岡市学校給食公社献立表」で検索)に掲載しています。
そのほか、給食ができるまでの詳しい工程や地産地消への取り組み、約130メニューのレシピ集など、市の学校給食に関するさまざまな情報を紹介しています。
■問い合わせ先/市学校給食公社 電話 092-555-2745 FAX 092-555-2749
「もっとおいしい給食プロジェクト」始動
市は、給食の質をさらに高めようと、「もっとおいしい給食プロジェクト」を立ち上げました。
プロジェクトの一環として、大学の先生や料理研究家、料理人、生産者など「食」の仕事に関わる民間の皆さんからのアイデアをもらうための意見交換会を、7月に実施しました。

当日は、舞鶴小・中学校(中央区)で給食時間の教室を見学し、実際に試食も行いました。
参加者からは「量は十分で、味付けもしっかりしている」「私たちの子どもの頃よりずっとおいしい」「器や盛り付けを工夫することで、見栄えももっと良くなりそう」などさまざまな意見が出ました。
市は、子どもたちや保護者の皆さん、給食現場の意見も取り入れながら、もっとおいしく、楽しい給食が届けられるよう、プロジェクトを進めていきます。
■問い合わせ先/給食運営課 電話 092-711-4642 FAX 092-733-5865
令和7年度2学期から開始 給食費の無償化について
市は、学齢期の子どもを育てる世帯の経済的負担を軽減するため、市立の小・中学校と特別支援学校(高等部を含む)に在籍する児童生徒の給食費を、今年度2学期から無償化します。
これまでは、保護者の皆さんからの給食費(小学校月額4200円、中学校月額5000円)と、市の負担で学校給食を運営してきました。2学期からは、全て市が負担します。
なお、アレルギー等の身体的事情により給食を「全停止」し、弁当等を持参している児童生徒については、主治医の意見を確認の上、給食費相当額を給付します。 ※宗教上の理由やその他信条によるもの、「一部のみ停止」、1カ月のうちに給食を食べる日がある場合は対象外。
■問い合わせ先/健康教育課 電話 092-711-4643 FAX 092-733-5865
-
この記事をシェアする
 (新ウィンドウで表示)
(新ウィンドウで表示) (新ウィンドウで表示)
(新ウィンドウで表示) (新ウィンドウで表示)
(新ウィンドウで表示) (新ウィンドウで表示)
(新ウィンドウで表示)