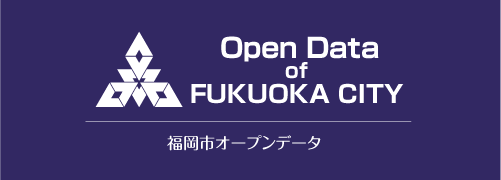無理なく、楽しく、できる範囲で地域活動に参加しませんか
市内の各地域では、防犯パトロール、防災訓練、子どもや高齢者の見守り、夏祭りなどさまざまな活動が行われています。それらは、住民の自治組織である自治会・町内会、自治協議会が中心となって行われています。私たちの暮らしを支える地域の活動を紹介します。
■自治会・町内会は身近な地域コミュニティ

市内には、約2300の自治会・町内会があります。
自治会・町内会は一定の地域を単位として、住民自ら設立した自治組織のことをいいます。互いに協力しながら、住みよいまちにするための活動を行っています。皆さんが自分の暮らす地域に関心を持ち、一人一人が少しずつ行動を起こすことが大切です。
自治会・町内会の活動は、住民の皆さんからの会費で支えられています。地域の人々が安心して暮らせるよう、防犯灯の設置やパトロール、清掃活動、住民同士の交流を深めるイベントなどの活動費に充てられています。
災害時など、いざという時に頼りになるのは、「ご近所とのつながり」です。日頃から声を掛け合う関係性があれば、困った時に支え合うことができます。
また、1人暮らしの高齢者や、核家族化で周囲に頼れる人がいない子育て世帯なども、近くに顔見知りがいれば、安心できます。
■校区でつくる自治協議会
一つの自治会・町内会で取り組むよりも、校区全体で行う方が効果的な活動もあります。
防犯・防災、子ども、環境、福祉、健康づくりなど、地域のさまざまな事柄について協議・運営しているのが、市内152の校区・地区に設立された自治協議会です。小学校区を単位として、校区内の自治会・町内会や体育振興会、自主防災組織など地域の団体等で構成されています。
■「ふくコミ」で地域の情報を発信
市は、各地域の自治会・町内会、自治協議会の活動などを紹介する地域コミュニティサイト(「ふくコミ」で検索)を開設しています。住所地から自治会・町内会等を検索できるほか、加入希望者には、地域への取り次ぎも行います。
■活発に意見を出し合ってみんなで楽しく

柏原6・7丁目町内会(南区)石田亘会長(50)の話
約830世帯が暮らす私たちの町内会では、役員と31人の組長が毎月公民館に集まり、町内や校区で実施する行事や、「道路に防犯灯やカーブミラーを付けたい」など住民から出された要望について話し合っています。
今年度から、ホームページで回覧板の情報を発信し、LINE(ライン)でも見られるようにしました。当面は紙の回覧板とデジタルを併用しながら、いずれは、欲しい人には紙で渡すようにしたいと考えています。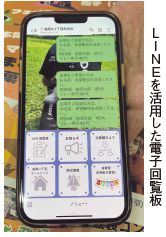
電子回覧板は、コピー代や回覧板を回す人の負担を減らす目的で始めましたが、始めてみるとメリットがいっぱいでした。スマートフォンなどでいつでもどこでも見られるだけでなく、情報が行き渡ることで、体育祭や夏祭りなどイベントへの参加者が増えました。若い世代が活動に関心を持つようになり、「ハロウィーンのイベントで高齢者宅を回って一緒に楽しみたい」「太鼓の演奏を取り入れて盆踊りをしたい」「自衛隊を呼んで防災訓練をしたい」などの意見も出るようになりました。
人と人とのつながりを大切にし、みんなが活動に参加したいと思える町内会にするのが目標です。住民の皆さんの心のよりどころになるようなまちにしたいと思っています。
市は、「共創による地域コミュニティ活性化条例」を制定し、地域住民と企業、商店街、NPO、学校等と協力し、地域の未来をつくる「共創」のまちづくりを進めています。
住民同士の助け合いや支え合いの基盤となる地域コミュニティへの期待は高まっています。地域づくりの主役は、そこに暮らす皆さんです。無理なく、できる範囲で構いません。気軽に参加してみてください。一緒に暮らしやすいまちをつくっていきましょう。
■問い合わせ先/コミュニティ推進課
電話 092-733-5161
FAX 092-733-5595
各校区の「公民館」は人が集まり、学び、つながる場所
市は、地域コミュニティの拠点として、小学校区ごとに公民館を設置しています。館内には、講堂や学習室、和室、集会室等があり、地域活動や生涯学習の場として利用されています。
●イベントや講座、サークル活動も

公民館主催のイベントや各種講座のほか、自主サークルやグループの活動が行われ、誰もが自由に参加できます。新たに学びたいことがあれば、仲間を集めて勉強会を開くこともできます
。
●地域の情報を発信
各種講座や地域の催しなどを掲載した「公民館だより」を毎月発行しています。ブログやSNSを発信している地域もあります。
●市公民館館長会会長・南幸盛さん(59)の話

公民館は誰でも気軽に利用できる施設です。仕事などで、日中は忙しい人も来られるよう、夜や週末にもイベントを開催しています。「公民館に来て良かった」と思ってもらうために、情報発信と笑顔での対応を心掛けていますので、分からないことは遠慮なくお尋ねください。
公民館の利用などに関する問い合わせは、市ホームページ(「福岡市 公民館」で検索)でご確認ください。
■問い合わせ先/公民館支援課
電話 092-711-4654
FAX 092-733-5595
自治協議会の活動事例
■インクルーシブ防災訓練~香椎下原校区(東区)~

インクルーシブ防災とは、あらゆる人を取り残さない防災のことです。
14の自治会・町内会がある香椎下原校区では、高齢者や障がいのある人など、避難時に支援が必要な人の個別避難計画を作り、日頃から民生委員と、民生委員をサポートする協力員が要支援者を見守っています。毎年防災訓練が実施されており、今年は、高齢者や障がいのある人などを含む約250人が参加し、校区で初めて要支援者の避難誘導訓練を行いました。
同校区の野中民生自治協議会会長(77)は、「日頃の活動を通して要支援者と顔見知りなので、スムーズに誘導できました。近隣の病院で働く作業療法士など医療の専門職が付き添ったことも、安心感を与えたようです。高台が多く、起伏に富んだ地域で、避難に不安を抱えている人も少なくありません。訓練はとても有意義で、人とつながることの大切さを感じました。今回の学びを生かし、皆さんが安心して住める地域をつくっていきます」と話しています。
■西南学院大学学生との共創~西新校区(早良区)~

36の自治会・町内会がある西新校区では、平成28(2016)年から西南学院大学小出秀雄ゼミを中心とする学生有志(西南まちづくりラボ)と一緒に、地域の人々が防犯パトロールを行っています。
これをきっかけに、学生が子ども向けのイベントを開催したり、自治協議会や小学生の子どもを持つ父親の集まり「おやじの会」が主催する催しを手伝ったりしています。また、自治協議会の役員も、大学に依頼されて普段の活動を紹介する講演や、地元の歴史を紹介するまち歩きを行っています。
小出教授(53)は「地域の人との交流は、学生たちにとっても、貴重な経験です。ここからまちづくりに関心を持つ学生が一人でも増えることを期待しています」と話します。
同校区の元村桂助自治協議会会長(69)も、「学生の参加に感謝しています。どの地域も活動の担い手が不足していると聞きます。私たちの校区では、学生やPTA、おやじの会などの協力を得ながら活動しています。できる範囲で構わないので、多くの人に参加してもらえるとうれしいですね」と話しています。
みんなで暮らしやすいまちに
●共創自治協議会サミットを開催
【日時】 11月29日(金曜日)午後1時30分から3時30分
【場所】 SAWARAPIA(早良区百道二丁目 旧ももちパレス)大ホール
【定員】 800人
【料金】 無料
▽博多区春町自治会の「地域猫活動」▽南区横手校区自治協議会の「子ども会の活性化」▽早良区高取校区の「外国人との交流や日本語教室」―の事例発表が行われます。NPOと地域が共働し、環境保全や高齢者福祉等の課題解決を目指した取り組みも紹介します。
詳細は、市ホームページ(「福岡市 共創自治協議会サミット」で検索)で確認を。
●ふくおか共創パートナー企業に登録しませんか
市は、地域でまちづくりを盛り上げてくれる、企業・団体・商店街等を「ふくおか共創パートナー企業」として登録しています。登録企業は、活動を通して地域の皆さんと顔なじみになり、企業を身近に感じてもらうことができます。また、活動の様子を市ホームページで公開します。
詳細は、市ホームページ(「ふくおか共創パートナー企業」で検索)で確認を。
■問い合わせ先/コミュニティ推進課
電話 092-733-5161
FAX 092-733-5595
地域の活動に参加して「ふくおかポイント」をためよう
市は、校区の清掃、夏祭りや運動会等の行事の企画運営など、地域のボランティア活動等に参加した人にポイントを付与する「ふくおかポイント」の実証事業を行っています。
活動の際に、スマートフォン等で二次元コードを読み取ると、ポイントを受け取ることができます。たまったポイントは、美術館や市民プールなどの利用チケット、非常用保存食セット、福岡マラソンの優先出走権など、さまざまな特典に交換することができます。
5月から次の九つの校区で実証事業を行っています。
▽東区=美和台、照葉▽博多区=那珂、弥生▽中央区=当仁▽南区=塩原▽城南区=堤丘▽早良区=西新▽西区=金武

●モデル校区を追加募集
来年度から実証に参加するモデル校区を12月ごろから追加募集します。詳細は各自治協議会あてに案内します。
ふくおかポイントの詳細は、市ホームページ(「福岡市 ふくおかポイント」で検索)でご確認ください。
■問い合わせ先/ふくおかポイント事務局(企画調整部内)
電話 092-711-4093
FAX 092-733-5582
金武校区での実証
金武校区では、祭りや運動会など校区で実施される主要行事を対象に実証を行っています。
9月に行われた「夕まつりinかなたけ」には、地域の住民が企画や準備、会場設営などに携わり、32人がポイントを受け取りました。
井長京子自治協議会会長(63)は、「地域の活動をより多くの人に知ってもらいたいと、実証事業に参加しました。地域の皆さんも楽しく活動しながらポイントを受け取っています。ふくおかポイントを知って参加した人もいました。この取り組みをきっかけに、地域の輪が広がってほしいですね」と話しています。