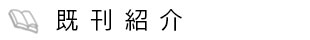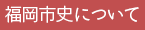
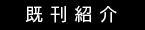
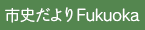
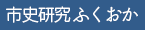
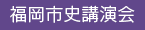
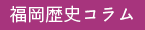
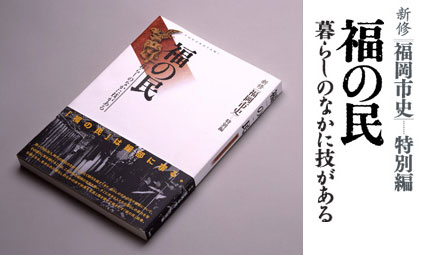
「福の民」は細部に宿る。
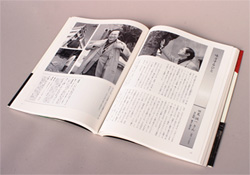 「おはようございます」と声かけあうのも、人と人とを結ぶための大事な技だ。「ハカタジカン」と言いながら、遅刻のおわびを言うのも、人と人との関係を守る知恵のひとつだ。そのような技や知恵は、家にも、街にも、仕事の場にも満ちている。それは福岡の街と民とが蓄えてきた大事な財産だ。けれども、暮らしのなかに溶けこんだ技や知恵は見えにくい。そのかたちも、子どもたちには子どもたちの世界があり、女には女の流儀があり、祭りには祭りの仕来りがあり、商いには商いの工夫があって、その場その場に応じて編み直され、さまざまな屈曲に富んでいる。そして、技や知恵が宿るのは、そのような屈曲に富んだ細部だ。
「おはようございます」と声かけあうのも、人と人とを結ぶための大事な技だ。「ハカタジカン」と言いながら、遅刻のおわびを言うのも、人と人との関係を守る知恵のひとつだ。そのような技や知恵は、家にも、街にも、仕事の場にも満ちている。それは福岡の街と民とが蓄えてきた大事な財産だ。けれども、暮らしのなかに溶けこんだ技や知恵は見えにくい。そのかたちも、子どもたちには子どもたちの世界があり、女には女の流儀があり、祭りには祭りの仕来りがあり、商いには商いの工夫があって、その場その場に応じて編み直され、さまざまな屈曲に富んでいる。そして、技や知恵が宿るのは、そのような屈曲に富んだ細部だ。
語ってもらおう。時代の変化のなかで、しぶとく時代を超えてきた、暮らしのなかの技や知恵について。その語りに耳をかたむけることは、これからの福岡の気風を養い、そこに生きる人たちの暮らしの底力を育む糧となる。
生きられた暮らしのなかの技や知恵を写真と聞き書きで描きだす「福の民」絵巻。
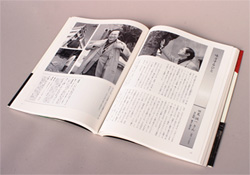 「おはようございます」と声かけあうのも、人と人とを結ぶための大事な技だ。「ハカタジカン」と言いながら、遅刻のおわびを言うのも、人と人との関係を守る知恵のひとつだ。そのような技や知恵は、家にも、街にも、仕事の場にも満ちている。それは福岡の街と民とが蓄えてきた大事な財産だ。けれども、暮らしのなかに溶けこんだ技や知恵は見えにくい。そのかたちも、子どもたちには子どもたちの世界があり、女には女の流儀があり、祭りには祭りの仕来りがあり、商いには商いの工夫があって、その場その場に応じて編み直され、さまざまな屈曲に富んでいる。そして、技や知恵が宿るのは、そのような屈曲に富んだ細部だ。
「おはようございます」と声かけあうのも、人と人とを結ぶための大事な技だ。「ハカタジカン」と言いながら、遅刻のおわびを言うのも、人と人との関係を守る知恵のひとつだ。そのような技や知恵は、家にも、街にも、仕事の場にも満ちている。それは福岡の街と民とが蓄えてきた大事な財産だ。けれども、暮らしのなかに溶けこんだ技や知恵は見えにくい。そのかたちも、子どもたちには子どもたちの世界があり、女には女の流儀があり、祭りには祭りの仕来りがあり、商いには商いの工夫があって、その場その場に応じて編み直され、さまざまな屈曲に富んでいる。そして、技や知恵が宿るのは、そのような屈曲に富んだ細部だ。語ってもらおう。時代の変化のなかで、しぶとく時代を超えてきた、暮らしのなかの技や知恵について。その語りに耳をかたむけることは、これからの福岡の気風を養い、そこに生きる人たちの暮らしの底力を育む糧となる。
生きられた暮らしのなかの技や知恵を写真と聞き書きで描きだす「福の民」絵巻。
壱
-
物語をつくる
ちゃんと報告させていただきます
言いたか言いの、コキたかコキ
最終的には親の背をみて子は育つ
これからのプラン? それが分かれば苦労はなかとですたい
申し送られる店
ここは基本、芸どころの街
あんなふうになりたい
玄界灘に打ち寄せるモノ
いまでは博多で唯一の造り酒屋になりました
あるしこ買うてこんか
絶対欲張らんようにね
ちょびっと先
茅と木賊
昔は炭、今は氷
このアーケードは日ぎり切って作ったと
黒子に徹します
コーヒー淹れて五十年
九大生のアタマを刈って半世紀
どうせ、追いつかないのだから
その夢が続くように
テンヤ師船
ゲーム・ソフトは、もう商いの感覚が違う
言葉で町をつくり続ける
修験道と喫茶店
本業の道楽
流れと、転々
トットットッて音がしてましたもんねえ
ミニチュア農工具の鍛冶職人
じぃっとしていたから、ここにおれる
お産によって強い母親が生まれるんです
いろんなものが、またいい
見定めない ごりょんさんの智恵
漁師なくして僕らの商売ないやないですか
-
太鼓の音が聞こえない
事業が好きなんです
単なる人形師やないとばい!
売る人の心を大切にしてあげないと
勉強しながら、職人とともに
いい筆でないと、いい字は書けないものなんです
ここに居っていいよ
足で重さを勘取る、これが案外難しい
師匠も弟子もおりません 博多を描く
みんな「お父さん」と呼びます
母は裏街道、娘は檜舞台
すぐ頼まるるもんで
「良うしてもろうとりましたけん」って言われりゃ…
だから今も空白のまま
道楽やなかばってん
私たちは中継点みたいなもんですからね
風にのせる
日本一の葬祭場でした
描いたら上手になる
わたしはだいたいがですね、エチオピア生まれですよ
九州の地下を掘る
木製容器が無くなってしまうことはない
なぁんの! 楽しみだけ
よりあって、おりあって
いつも博多の町の名物やった
古本屋はひとり三役
泥棒を捕まえたり、放火魔を捕まえたり
古物に命を吹き込む方法
とにかく「やめんめえや」って
-
小さな神様の生き残り戦略
俺たちのようなのば拝んでから
うどんのバランス
人の後ば掃わいたっちゃゴミは無かろう?
博物館をつくるには
味方するひと
道具も人も万能なんてありえない
化石みたいな時計屋さんなっとるけど
気をつかうんですよ
見るでわかる
可愛がってやんしゃあと
トマトが料理人生のはじまりだった
二代目の楽しみ
大切なのは渡し続けること
番をする
三拍子そろった食いしん坊
草鞋で救われとります
もうよかでっしょ! 不文律の妙 博多の茶飲み話から
細く長く堅く 紙屋の家訓
いま市内の風呂屋は二十一軒
みんな見ててね
声を届ける
酔太郎 店が客を選ぶ
私に順番が来たっちゃろう
人を街につなぐ足
おじちゃん、ただいま
お話を重ねると、よく分かりますね
県道沿いの船具屋さん
ありがとさん、ありがとさん
考えるまでもなく、うちに角打ちがあったんですね
何が出るのかわからないのが金物屋
引揚げ・ツタンカーメン・武田鉄矢
-
秒からはじめる
博多っ子純情
無理なら「しきらん」て言う
海が悪い時には陸が良い
「おおまん」なる伝統 時代の変化と博多商人
テンポと態度は変えてはいけない
博多には人の絆がある
女ですから、好みが入ります
オンテレメンピン
昔は「義理と人情」みたいなところがあった
それ、五半で大丈夫ですよ
百年、二百年のつきあいなんよ
家庭の料理が一番美味しいとよ
それが、私の最高の財産
中洲ふぜい
気に入ったものに失敗はありません
働いていたらね、マイナスのことはないです
謙虚に謙虚に 町内を創る
まちなかで動物を飼育すること
あれ誰な
どこもギュウギュウ
-
我々の仕事は、非常に大切な仕事だから
「部族」みたいなもんですね
一人でも読みたい客がいる本は置く
動き出したら、嬉しいんです
身も心も含めて人を支える
南に向く人、東に向く人、これは癖ですね
いっぱい持っとけばまたなんとかなるじゃないですか
ハカタイキしよります
職人気質をくすぐる
箪笥の肥やしっていう言葉があったとよ
愛宕さまへは月参り
ここ十年、三味線では食っていない
ウチで食べるもんば出しよーと
本に浮力をあたえる
そら、真似でけん
私どもは、一着の着物に何十年と関わるんです
見ぬふりして見る
時計っていうのは、一つ部品がないだけでも動きませんから
見出しのたたぬ記事を書く
山笠を書く
人ばっかり疑ごうても、ダメです
やってみたもんじゃないとわからん
商売がたきっていう感覚がないけん
叱る人
色ごとはむずかしい 博多帯を売る
ページ
訂正箇所
誤
正
17
目次11行目
クラブ「カレン」支配人
クラブ「カレン」経営者
43
本文下段2行目
母もそんなうふうにして
母もそんなふうにして
115
注「吉四六劇団」1行目
野呂裕二
野呂祐吉
115
注「吉四六劇団」3行目
松下龍一
松下竜一
144
本文上段6行目
赤瀬川源平
赤瀬川原平
164
注「享保の改革」1行目
徳川吉宗による享保年間(一七一六~四五年)の幕政改革
徳川吉宗による江戸中期の幕政改革(一七一六~四五年)
171
注「香椎駅前」2行目
国道三号線以南
国道三号線以東
185
注「消防団」2行目
火事災害の召集
火事災害の招集
192
写真説明
(写真提供:長﨑玉恵さん)
(写真提供:長﨑玉江さん)
237
注「流」5行目
他の六流を加勢
他の五流を加勢
250
本文上段4行目
奈良屋幼児園
奈良屋幼稚園
280
本文1行目
福岡タクシー協会
福岡市タクシー協会
302
見出
クラブ「カレン」支配人
クラブ「カレン」経営者
302
本文2行目
仕事を探しに
削除
302
本文6行目
炭住街
社宅
302
本文7行目
やがて音信不通となった
終戦後、技術者として足止めされて、昭和二十六年まで帰国できなかった
302
本文9行目
「赤い靴」
「上海」
302
本文14行目
支配人
経営者
303
注「キャバレー『赤い靴』」
キャバレー「赤い靴」 空襲で焼け野原となった中洲の街に、最初のキャバレーが建てられたのが一九四八年。その後一九五〇年頃までに大型キャバレー三店が次々と開店し、中洲の夜は少しずつ賑わいを取り戻していく。キャバレー「赤い靴」は、この頃開店した大型店のひとつ。この店のほか、「キャバレー上海」「ダンスホール夜の城」「金馬車」「キャンドル」「クラウン」「舶来居酒屋」「夜来香」などが、一流店として人気を博した。
キャバレー 踊り場を設けて客にダンスをさせ、かつ、接待をして客に飲食させる接待飲食等営業の一形態。客はホステスと飲食やダンスをし、バンド演奏やショーを楽しむ。森田さんによれば、東中洲に最初にできたのは「国際キャバレー」(一九四八年)。五〇年に「上海」「赤い靴」が相次いでオープンし、五二年には「ハイハット」「カズバ」、その後も「金馬車」「大洋」ほか大型店が続々と開店した。六〇年代にかけては、サロンと呼ばれる店も多くあった(「サロン小麦」がその走り)。また、キャバレーに欠かせないのが音楽で、深見俊次とハッチャ・ジャズ・オーケストラ、中井末男とメディコ・キューバン・ボーイズ、バンドネオンの佐川峯、バイオリンの小林正之などが人気だった。当時キャバレーには専属の歌手がいて、客が歌を聴く時代だったが、現在はカラオケを置いて客が歌う時代になった、と森田さんは語る。
328
名簿中段17行目
山田裕爾 福岡市教育委員会委員長
山田裕爾 福岡市教育委員会教育長
329
名簿上段14行目
福間裕爾 福岡市博物館学芸課
福間裕爾 福岡市博物館学芸課学芸係長
平成23年4月作成