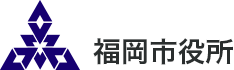予防救急
予防救急とは
救急車で搬送された事例の中には、「ほんの少しの注意」や「事前の対策」で未然に防げたかもしれないものもあります。
事故の原因や注意点、予防のポイントを知り、救急搬送につながるケガや病気を未然に防ぐ取り組みを「予防救急」といいます。
日頃からの「心がけ」と「環境づくり」で、救急車を呼ぶような大きな事故や病気にならないように「予防救急」にご協力ください。
家庭内での転倒・転落
普段生活して住み慣れている自宅にも危険がたくさん潜んでいます。
階段や小さな段差、電気のコードなどにつまずいて転倒したり、ベッドや脚立などから転落し救急搬送されることがあります。
特に高齢者の場合、骨折を伴うような重症になることもあります。
予防のポイント
- 階段などに手すりや滑り止めをつけましょう。
- ベッドに転落防止の柵をつけましょう。
- 日頃から整理整頓を心がけましょう。
- 歩きやすく、滑りにくい履物を選びましょう。
- 脚立などを使用して作業するときは補助者に支えてもらいましょう。
熱中症にご用心!
熱中症による救急搬送は、毎年、梅雨入り前の5月頃から増えはじめ、梅雨明けの7月下旬から8月上旬に急増します。
梅雨明け前後の蒸し暑い時期は体が暑さに慣れていないため、特に注意が必要です。
また、暑さに対する感覚が弱くなる高齢者の方や、体温調節機能が十分に発達していない小さなお子さんはかかりやすいと言われています。
熱中症は予防のポイントや応急手当を知っていれば防ぐことができ、万が一発症しても重症化を防ぐことができます。
熱中症を正しく理解し、予防に努めましょう。
予防のポイント
- こまめに水分・塩分を補給しましょう。
- 涼しい服装や帽子、日傘の活用など涼しく過ごす工夫をしましょう。
- 室温が28℃を超えないようにクーラーや扇風機を利用しましょう。
- 暑いときこそ体調管理!栄養バランスのよい食事をとり、十分な睡眠を心がけましょう。
- 暑くなる前から体づくりに取り組みましょう。
応急手当のポイント
- 涼しい場所へ移動し、服をゆるめ、安静にしましょう。
- クーラー、扇風機、うちわを使い、体を冷やしましょう。
- 首やわきの下、太もものつけねを、冷たいおしぼりやペットボトル、保冷剤、氷のうなどで冷やしましょう。
- 自力で水分がとれるようであれば、水分・塩分をこまめに補給しましょう。
- 意識がない場合や全身がけいれんしたり、まっすぐ歩けない場合などはためらわずに救急車を呼びましょう。
食事中の窒息・誤嚥 (もちなどののど詰め)
もちなどの食べ物による「のど詰め(窒息)」で救急搬送される事故が多く発生しており、特に高齢者に多い傾向にあります。
加齢とともに食べ物を飲み込みにくくなり、窒息や誤嚥が生じやすくなっています。
もちに限らず、肉類、ご飯、パン、果物など、様々な食べ物による事故が発生しており、中には薬の包装を詰めた事例もあります。
窒息や誤嚥は、重症度が高い事故のひとつで、命にかかわる場合もあります。
予防のポイント
- 食べ物を小さく切って食べやすい大きさにしましょう。
- ゆっくりよく噛んで、飲み物をそばに置いておきましょう。
- 急に話しかけるなど、慌てさせないように気をつけましょう。
冬のお風呂は要注意!
毎年,気温が下がる12月から2月にかけて浴室や脱衣室での転倒や失神など入浴中の事故による救急搬送が増加します。
「ヒートショック」が冬場に急増する入浴事故の原因のひとつとして考えられています。
「ヒートショック」とは,暖かい部屋から寒い部屋への移動など、急激な温度の変化により血圧が大きく変動することが原因で起きる
体の不調のことで、脳卒中や心筋梗塞、浴槽内での溺水などにつながることもあり、最悪の場合、命に関わる場合もあります。
特に高齢者の方や高血圧や糖尿病などの持病をお持ちの方などは注意が必要です。
予防のポイント
- 入浴前に浴室や脱衣室を暖めましょう。
- お湯の温度は41℃以下、湯に浸かる時間は10分まで
- 浴槽から急に立ち上がらないようにしましょう。
- 食後すぐ や お酒が抜けないうちの入浴は控えましょう。
- 家族に一声かけてから入浴しましょう。
みんなで予防 インフルエンザ
インフルエンザは、例年12月から3月にかけて流行します。
インフルエンザの流行に伴い、高熱などの症状で救急搬送される方も増加する傾向にあります。
かからないために「手洗い」、かかってもうつさないために「咳エチケット」を心がけ、みんなでインフルエンザを予防しましょう。
予防のポイント
- 流行期間中に繁華街などの人ごみへの外出は控えましょう。
- 手洗いを日常的に行いましょう。
- 十分に栄養や睡眠をとり、体力や抵抗力を高め、体調管理をしましょう。
- 加湿器などで適度な湿度(50~60%)を保つことも効果的です。
- インフルエンザ様症状がある場合は、無理して職場や学校へは行かないようにしましょう。
知っておこう!「急性アルコール中毒」の怖さ
お正月やお花見、歓送迎会などでの楽しいお酒も飲み方によっては一転し、「急性アルコール中毒」で救急搬送されることも…。
いわゆる「イッキ飲み」や「無理強い・強要」は命に関わる危険な行為です。
福岡市では、毎年1,500人以上の方が「急性アルコール中毒」で救急搬送されています。
節度ある飲酒を心がけ、楽しく安全にお酒と付き合いましょう。
予防のポイント
- 自分の適量を知り、その日の体調にも注意しましょう。
- 「イッキ飲み」(短時間に多量の飲酒)や飲酒の「無理強い・強要」はしない・させない。
- お酒の飲めない体質の方は、周囲の人に「お酒が飲めない体質です」と事前に伝えておきましょう。
- 意識がない、呼びかけても反応しない、呼吸がおかしい場合はすぐに救急車を呼びましょう。
子どもを事故から守りましょう!
子ども(0歳~6歳)は、周りの大人から見ると思いがけない行動をすることがあり、その結果、さまざまな事故に巻き込まれることがあります。
また、運動機能の発達とともに、いろんなことができるようになります。その一方で、事故にあうおそれが出てきます。
周りの大人が子どもの身の回りの環境にちょっと注意を払い、対策を立てておくことで、防ぐことができる事故があります。
起こりやすい事故と予防法を知り、子どもを事故から守る正しい知識を身につけて、子どもを事故から守りましょう!
窒息・誤飲事故 ( )内は発生しやすい年齢
- 就寝時の窒息事故 (0歳~1歳くらい)
- ブラインドやカーテンのひもなどによる窒息 (0歳~2歳くらい)
- 食事中に食べ物で窒息 (0歳~6歳くらい)
- おもちゃなど小さな物で窒息(0歳~3歳くらい)
- ボタン電池、吸水ボール、磁石などの誤飲 (0歳~3歳くらい)
- 医薬品、洗剤、化粧品、たばこ、お酒などの誤飲 (0歳~3歳くらい)
予防のポイント
- 1歳になるまでは、寝かせる時は、あお向けに寝かせましょう。
- ひもが首に絡まないよう、ひもは、子どもの手が届かないところにまとめましょう。
- 食べ物は小さく切り、食べやすい大きさにして、よく噛んで食べさせましょう。
- おもちゃなど小さな物、ボタン電池、磁石などは子どもの手が届かないところに保管しましょう。
- 医薬品、洗剤、化粧品、たばこやお酒などは子どもの手が届かないところに保管しましょう。
水まわりの事故 ( )内は発生しやすい年齢
- 浴槽に転落し溺れる (0歳~2歳くらい)
- ビニールプールやプールでの事故 (1歳以上)
- 海や川での事故 (2歳以上)
- ため池、排水溝、浄化槽での事故 (2歳以上)
予防のポイント
- 入浴時は少しの間でも子どもから目を離さないようにしましょう。入浴後は浴槽の水を抜きましょう。
- プールで遊ぶときは、必ず大人が付き添い、子どもから目を離さないようにしましょう。
- 海や川で遊ぶときは、ライフジャケットを着用させ、危険な場所で遊ばないように注意しましょう。
- ため池、排水溝、浄水槽など、転落したり溺れたりする危険な場所がないか確認し、遊ばないように注意しましょう。
やけど事故 ( )内は発生しやすい年齢
- お茶、味噌汁、カップ麺などでのやけど (0歳~2歳くらい)
- 電気ケトル、ポット、炊飯器でのやけど (0歳~2歳くらい)
- 暖房器具や加湿器でのやけど (0歳~2歳くらい)
- 調理器具やアイロンでのやけど (0歳~2歳くらい)
- ライターやマッチでの火遊び (2歳~6歳くらい)
予防のポイント
- 高温の飲み物や汁物を扱うときは、子どもの手が届かように注意しましょう。
- 電気ケトルやポットはお湯がでないように必ずロックし、コード類も引っ張らないように注意しましょう。
- 暖房器具や加湿器に直接子どもが触れないように安全柵などを活用しましょう。低温やけども要注意!
- 調理中や調理後のフライパンなどの調理器具、アイロンなどは子どもが触れないように注意しましょう。
- ライター等を使用した火遊びはやけどだけではなく、火災にもつながります。子どもの目に触れない場所に保管しましょう。
転落・転倒事故 ( )内は発生しやすい年齢
- 大人用ベッドからの転落 (0歳~1歳くらい)
- ベビーベッドやおむつ替え時の台からの転落 (0歳~1歳くらい)
- 椅子やソファからの転落 (0歳~1歳くらい)
- 階段からの転落、段差での転倒 (0歳~1歳くらい)
- ベランダ、窓や出窓からの転落 (1歳以上)
予防のポイント
- 寝ている間に動きまわったりしてベッドから転落し、けがすることがあるので注意しましょう。
- ベビーベッドやおむつ替えの台など、高さのある場所にいるときは目を離さないようにしましょう。
- 椅子の上で立ち上がったり、ソファの上に寝かせたりすることは転落につながります。注意しましょう。
- ハイハイする頃から階段からの転落が起きます。柵などを設置するなど注意しましょう。
- ベランダや窓の近くに踏み台になるものは置かないようにしましょう。
自動車・自転車関連の事故 ( )内は発生しやすい年齢
- チャイルドシート未使用による事故 (0歳~6歳くらい)
- 車のドアやパワーウインドに挟まれる事故 (0歳~3歳くらい)
- 車内での熱中症 (0歳~1歳くらい)
- 道路上などでの事故 (1歳以上)
- 自転車に子どもを乗せたままでの転倒や後輪に足を巻き込むスポーク外傷(0歳~5歳くらい)
予防のポイント
- 短時間の乗車でもチャイルドシートを使用しましょう。
- 子どもが自分でドアやパワーウインドを開閉しないようにロック機能を活用しましょう。
- 少しの間でも、子どもだけを車の中に残しておかないようにしましょう。(特に夏場は要注意!)
- 道路上は危険がいっぱいです。道路を歩くときは手をつなぐなど十分注意しましょう。
- 法令により自転車に子どもを乗せることは、6歳未満で、幼児用座席を設置した場合のみ認められています。正しく使用しましょう。
挟む・切る・その他の事故 ( )内は発生しやすい年齢
- キッチン付近で包丁、ナイフでけが (0歳~2歳くらい)
- カミソリ、カッター、はさみなどの刃物やおもちゃでのけが (0歳~2歳くらい)
- 小さな物を鼻や耳に入れる (0歳~2歳くらい)
- テーブルなどの家具で打撲 (0歳~3歳くらい)
- ドアや窓で手や指を挟む (1歳~3歳くらい)
- ドラム式洗濯機での事故 (2歳~6歳くらい)
- エスカレーター、エレベーターでの事故 (0歳~3歳くらい)
予防のポイント
- 包丁やナイフを使用したらすぐに収納場所に片付け、チャイルドロックをつけるなどの工夫をしましょう。
- カミソリやカッター、はさみなどは子どもの手の届かないところに保管しましょう。
- ビーズやプラスチックの玉など、小さな物を鼻や耳に入れて遊ぶことがありますので十分注意しましょう。
- テーブルなどの家具の角にクッションテープを取り付けるなど,衝撃を和らげる工夫をしましょう。
- ドアのちょうつがい部分に隙間防止カバーをつけるなど、注意しましょう。
- ドラム式洗濯機に子どもが入り、窒息する事故が起きています。必ずフタを閉め、ロック機能を活用しましょう。
- エスカレーター、エレベーターを利用するときは子どもから目を離さないようにしましょう。