○福岡市建築物における駐車施設の附置等に関する条例
昭和47年4月1日
条例第55号
(趣旨)
第1条 この条例は、駐車場法(昭和32年法律第106号。以下「法」という。)第20条から第20条の3までの規定に基づき、建築物に駐車施設を附置すべき地区、駐車施設を附置すべき建築物の規模等について定めるものとする。
(地区の指定)
第2条 法第20条第2項の規定に基づき、駐車場整備地区又は商業地域若しくは近隣商業地域(以下「駐車場整備地区等」という。)の周辺の都市計画区域内の地域内で条例で定める地区は、駐車場整備地区等に接続する500メートル以内の区域で市長が指定する区域(以下「周辺地区」という。)とする。
2 法第20条第2項の規定に基づき、周辺地域及び駐車場整備地区等以外の都市計画区域内の地域であつて自動車交通の状況が周辺地域に準ずる地域内又は自動車交通がふくそうすることが予想される地域内で条例で定める地区は、幅員15メートル以上の道路の境界線から当該道路の両側へそれぞれ100メートル以内の区域で、市長が指定する区域(以下「自動車ふくそう地区」という。)とする。
3 市長は、前2項の規定に基づき周辺地区又は自動車ふくそう地区を指定する場合には、その旨を告示しなければならない。
(駐車施設の附置)
第3条 次の表の(あ)欄に掲げる地区又は地域内において、(い)欄に掲げる用途に供する建築物であつて(う)欄に掲げる規模のものを新築しようとする者は、(え)欄により算定した台数以上の自動車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する大型自動二輪車及び普通自動二輪車(いずれも側車付きのものを除く。以下「自動二輪車」という。)を除く。以下同じ。)を収容することができる駐車施設を建築物又は建築物の敷地内に設けなければならない。ただし、義務教育諸学校その他規則で定めるものの用に供する建築物で、市長が特に認めるものについては、この限りでない。
(あ) | (い) | (う) | (え) |
地区又は地域 | 建築物の用途 | 建築物の規模 | 駐車施設の規模 |
駐車場整備地区等 | 建築物の全部又は一部を特定用途に供するもの | 特定用途に供する部分(以下「特定部分」という。)の延べ面積(駐車施設の用途に供する部分の床面積の合計を除き、観覧場にあつては屋外観覧席の部分の面積を含む。以下同じ。)と特定用途以外の用途(以下「非特定用途」という。)に供する部分(以下「非特定部分」という。)の延べ面積に4分の3を乗じて得た面積との合計の面積が1,500平方メートルを超えるもの | 延べ面積が1,500平方メートルを超える部分の面積に対してA平方メートルまでごとに1台 |
建築物の全部を非特定用途に供するもの | 延べ面積が2,000平方メートルを超えるもの | 延べ面積が2,000平方メートルを超える部分の面積に対して450平方メートルまでごとに1台 | |
周辺地区又は自動車ふくそう地区 | 建築物の全部又は一部を特定用途に供するもの | 特定部分の延べ面積が2,000平方メートルを超えるもの | 特定部分の延べ面積が2,000平方メートルを超える部分の面積に対して300平方メートルまでごとに1台 |
備考 (え)欄に規定するAは、次の式により算定して得た数値とする。
A=300+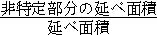 ×150
×150
2 前項の表の(あ)欄に掲げる地区又は地域内において、(う)欄に掲げる規模の建築物又は増築をし、若しくは特定部分の延べ面積の増加を伴う建築物の部分の用途の変更(以下「用途変更」という。)のための建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第14号に規定する大規模の修繕若しくは同条第15号に規定する大規模の模様替(以下「大規模の修繕等」という。)をすることにより当該規模となる建築物について、増築又は特定部分の延べ面積の増加を伴う用途変更のための大規模の修繕等をしようとする者は、第1号に掲げる台数から第2号に掲げる台数を減じて得た台数以上の自動車を収容することができる駐車施設を当該増築又は大規模の修繕等をした後の建築物又は建築物の敷地内に設けなければならない。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
(1) 増築又は大規模の修繕等をした後の建築物を新築したものとみなして前項の規定を適用した場合に設けなければならないこととなる駐車施設に収容すべき自動車の台数
(昭和51条例33・昭和62条例32・平成2条例24・平成8条例51・平成28条例64・一部改正)
第3条の2 次の表の(あ)欄に掲げる地区又は地域内において、(い)欄に掲げる用途に供する建築物であつて(う)欄に掲げる規模のものを新築しようとする者は、(え)欄により算定した台数を合計した台数以上の自動二輪車を収容することができる駐車施設を建築物又は建築物の敷地内に設けなければならない。ただし、規則で定めるものの用に供する建築物で、市長が特に認めるものについては、この限りでない。
(あ) | (い) | (う) | (え) |
地区又は地域 | 建築物の用途 | 建築物の規模 | 駐車施設の規模 |
商業地域、近隣商業地域 | 建築物の全部又は一部を特定用途に供するもの | 百貨店その他の店舗の用に供する部分の延べ面積が3,000平方メートルを超えるもの | 延べ面積に対して3,000平方メートルまでごとに1台 |
特定部分(百貨店その他の店舗の用に供する部分を除く。)の延べ面積が5,000平方メートルを超えるもの | 延べ面積に対して5,000平方メートルまでごとに1台 |
(1) 増築又は大規模の修繕等をした後の建築物を新築したものとみなして前項の規定を適用した場合に設けなければならないこととなる駐車施設に収容すべき自動二輪車の台数
(平成28条例64・追加)
(荷さばきのための駐車施設の附置)
第4条 商業地域内において、次の表の(あ)欄に掲げる用途に供する建築物であつて(い)欄に掲げる規模のものを新築しようとする者は、(う)欄により算定した台数以上の自動車を収容することができる荷さばきのための駐車施設を建築物又は建築物の敷地内に設けなければならない。
(あ) | (い) | (う) |
建築物の用途 | 建築物の規模 | 駐車施設の規模 |
建築物の全部又は一部を特定用途に供するもの | 特定部分の延べ面積が2,000平方メートルを超えるもの | 特定部分の延べ面積に対して6,000平方メートルまでごとに1台 |
(1) 増築又は大規模の修繕等をした後の建築物を新築したものとみなして前項の規定を適用した場合に設けなければならないこととなる荷さばきのための駐車施設に収容すべき自動車の台数
(平成8条例51・全改、平成28条例64・一部改正)
(平成8条例51・全改)
(平成28条例64・追加)
(平成2条例24・平成8条例51・平成28条例64・一部改正)
(駐車施設の規模及び構造)
第7条 第3条の規定により設けなければならない駐車施設のうち駐車の用に供する部分の規模は、駐車台数1台につき、幅2.3メートル以上、奥行5メートル以上であり、自動車を安全に駐車させ、かつ、円滑に出入りさせることができるものでなければならない。
(1) 当該建築物を新築しようとする場合 当該建築物の駐車施設に収容すべき自動車の台数に100分の1を乗じて得た台数(当該台数に1未満の端数があるときは、当該端数を切り上げて得た台数)
(2) 当該建築物について増築又は大規模の修繕等をしようとする場合 規則で定める台数
3 第3条の2の規定により設けなければならない駐車施設のうち駐車の用に供する部分の規模は、駐車台数1台につき、幅1メートル以上、奥行2.3メートル以上であり、自動二輪車を安全に駐車させ、かつ、円滑に出入りさせることができるものでなければならない。
4 第4条の規定により設けなければならない荷さばきのための駐車施設のうち駐車の用に供する部分の規模は、駐車台数1台につき、幅3メートル以上、奥行7.7メートル以上、有効高さ3メートル以上であり、自動車を安全に駐車させ、かつ、円滑に出入りさせることができるものでなければならない。ただし、当該建築物の構造又は敷地の状態から市長がやむを得ないと認める場合においては、この限りでない。
5 前各項に規定する駐車施設の構造その他の技術的基準は、規則で定める。
(昭和51条例33・平成8条例51・平成10条例51・平成28条例64・一部改正)
3 前2項の規定による承認を受けようとする者は、規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。
(平成8条例51・平成28条例64・一部改正)
(平成28条例64・追加)
(公共交通利用促進措置による駐車施設の規模の特例)
第8条の3 第3条の規定により駐車施設を設け、又は設けようとする当該駐車施設の所有者又は管理者が、建築物の利用者に対して公共交通機関の利用促進に資する措置(以下「公共交通利用促進措置」という。)を講じた場合であつて、当該駐車施設の周辺の道路の安全及び円滑な交通に支障を生じさせるおそれがないと市長が認めたときは、規則で定めるところにより、当該駐車施設に収容すべき自動車の台数を減じることができる。
3 前項の承認を受けて設けられた駐車施設の所有者又は管理者が、公共交通利用促進措置の全部又は一部を廃止しようとするときは、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。
4 第2項の承認を受けて設けられた駐車施設の所有者又は管理者は、規則で定めるところにより、公共交通利用促進措置の実施状況について、市長に報告しなければならない。
(1) 公共交通利用促進措置の全部又は一部を講じないとき。
(2) 第2項後段の規定に違反したとき。
(3) 前項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
(平成28条例64・追加)
(適用の除外)
第9条 建築基準法第85条に規定する仮設建築物を新築し、増築し、又は用途変更をしようとする者に対しては、この条例の規定は適用しない。
(平成8条例51・平成28条例64・一部改正)
(平成8条例51・平成28条例64・一部改正)
(立入検査)
第11条 市長は、この条例を施行するため必要な限度において、建築物若しくは駐車施設の所有者若しくは管理者から報告若しくは資料の提出を求め、又は部下の職員をして建築物若しくは駐車施設に立ち入り、検査をさせることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
(平成8条例51・平成28条例64・一部改正)
(罰則)
第13条 前条の規定に基づく市長の命令に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。
2 第11条第1項の規定に基づく報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は職員の立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、20万円以下の罰金に処する。
(平成8条例51・一部改正)
(平成8条例51・一部改正)
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和47年規則第52号で昭和47年4月1日から施行)
(経過措置)
2 この条例の施行の日から起算して6月を経過する日までに新築、増築又は用途変更の工事に着手した建築物については、福岡県駐車場条例(昭和39年福岡県条例第56号)の例によるものとする。
附則(昭和51年4月1日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月9日条例第32号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月29日条例第24号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成8年12月19日条例第51号)
この条例は、平成9年7月1日から施行する。
附則(平成10年12月28日条例第51号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月26日条例第64号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。